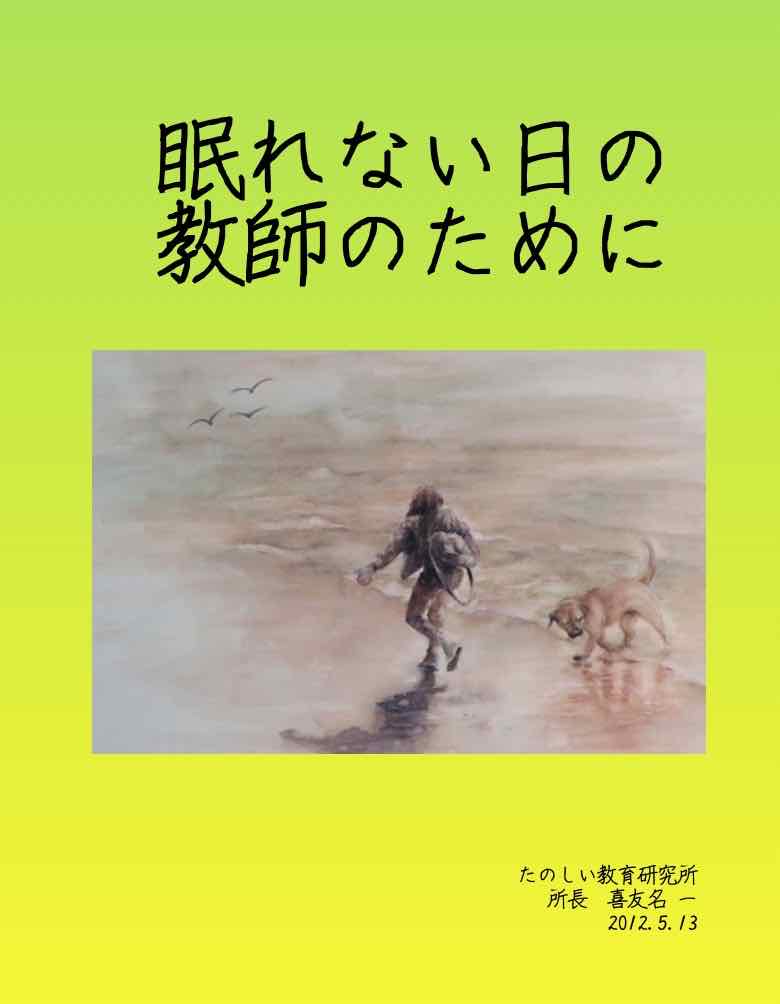その頃の社会全体が、科学や技術の進歩にたくさんの夢と希望を重ねていたこともあったのでしょう、子どもの頃から科学・技術に大きな魅力を感じていました。
今でも科学・技術は様々な発展を見せています。
巧妙な「疑似科学」の台頭、「科学・技術に疑問を提唱する人たち」の考え方もあって、現代社会は、わたしが子どもの頃の様に両手を上げて迎えいれる様子はありません。しかし革新的という意味では、今の方が多大な成果を上げていると思います。
ところで小学校の頃から、わたしの心に宿っていた大きなテーマが、進歩によってコンピュータにも「心」が芽生えるのかということでした。
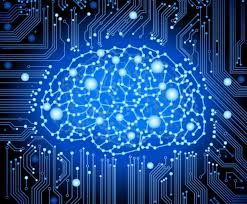 時は流れ、大学に入学した頃、やっとパーソナルコンピュータが普及し始めました。
時は流れ、大学に入学した頃、やっとパーソナルコンピュータが普及し始めました。
今のiphoneの持つ処理能力の 1/1000 にも満たないコンピュータが150万円くらいした頃です。
何とかそれを手に入れ、プログラムを打ち込みながらコンピュータを学ぶうちに、
「人間が体系づけた命令系の延長にあるコンピュータに心が宿ることはない」
というのが私の一つの結論になりました。
ところで最近、画像認識に関する画期的理論ディープ・ラーニング(深層学習/多層構造学習)をきっかけに、〈人工知能〉が気になって学び始めています。
コンピュータが膨大な画像の中から「これはネコだ」「この数は1だ」と認識するプログラムは、かつてのコンピュータ技術からブレイク・スルー(画期的進歩)し、それがグーグルやカナダ トロント大学の成果ではっきりしてきました。
表面的にはわずかな変化に見えるかもしれませんが、コンピュータ自身による《教師なし学習》の可能性が見えてきたのです。


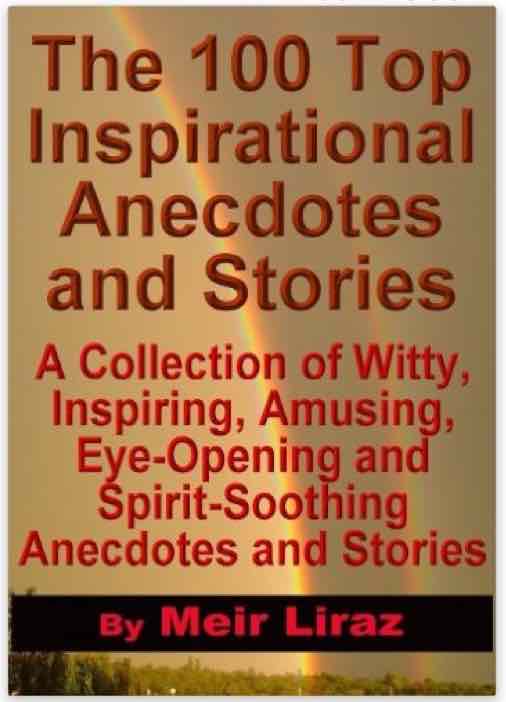 に似た内容が書かれています。
に似た内容が書かれています。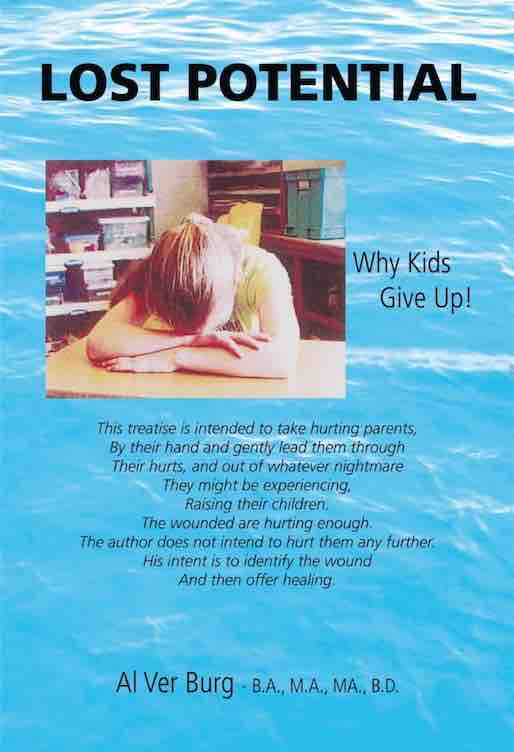
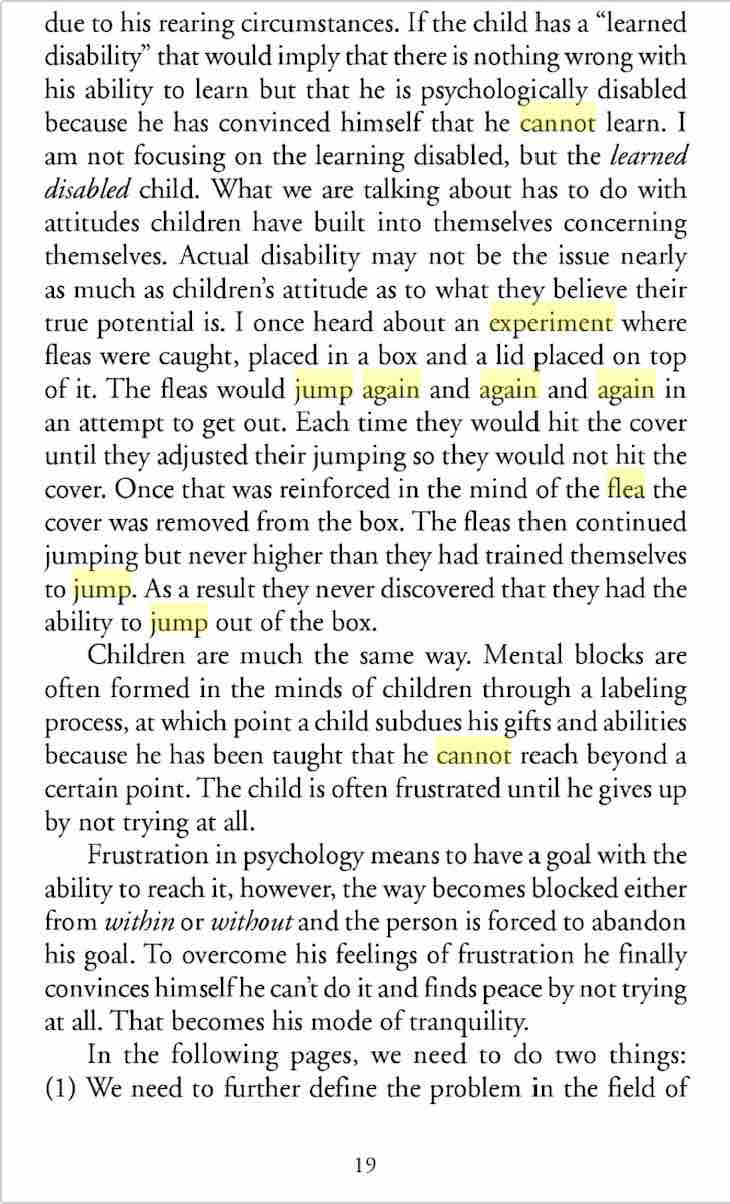 文章上から十行目にこうあります。
文章上から十行目にこうあります。