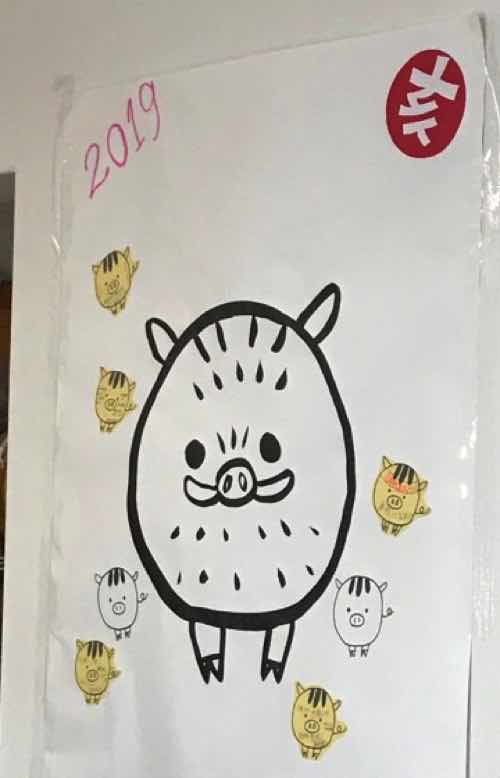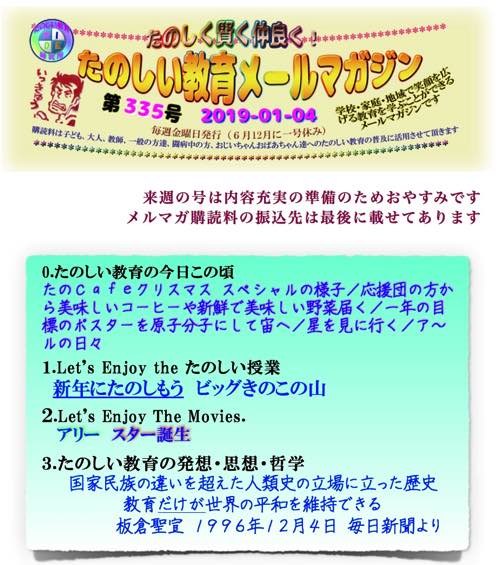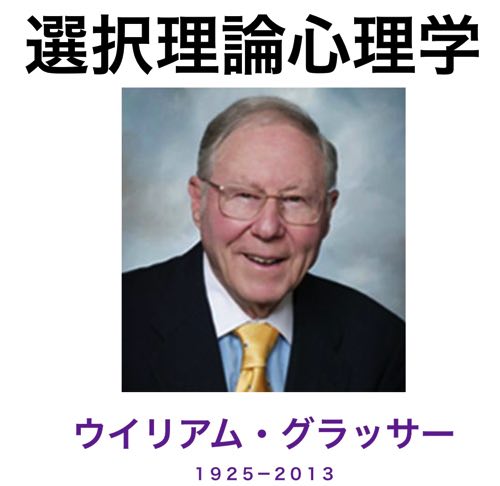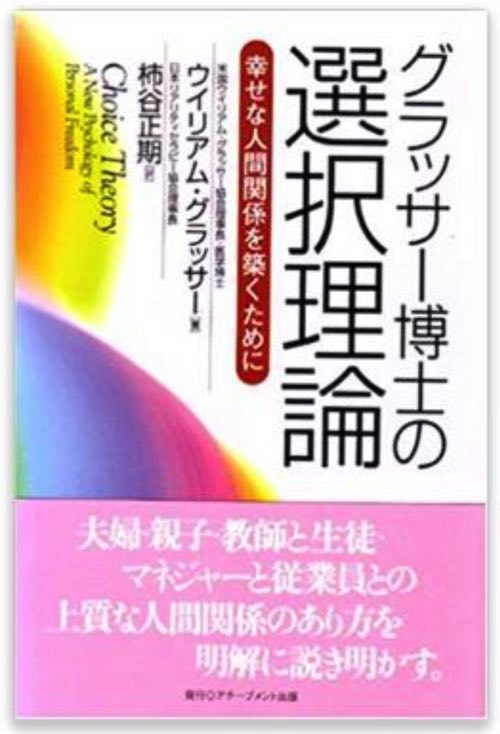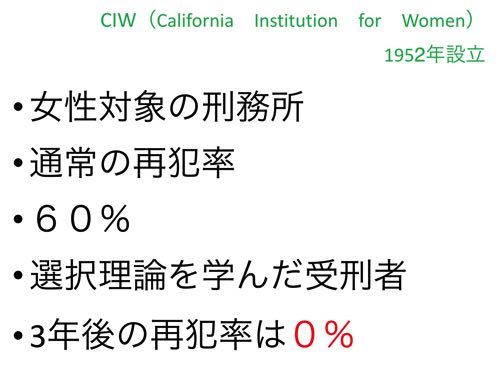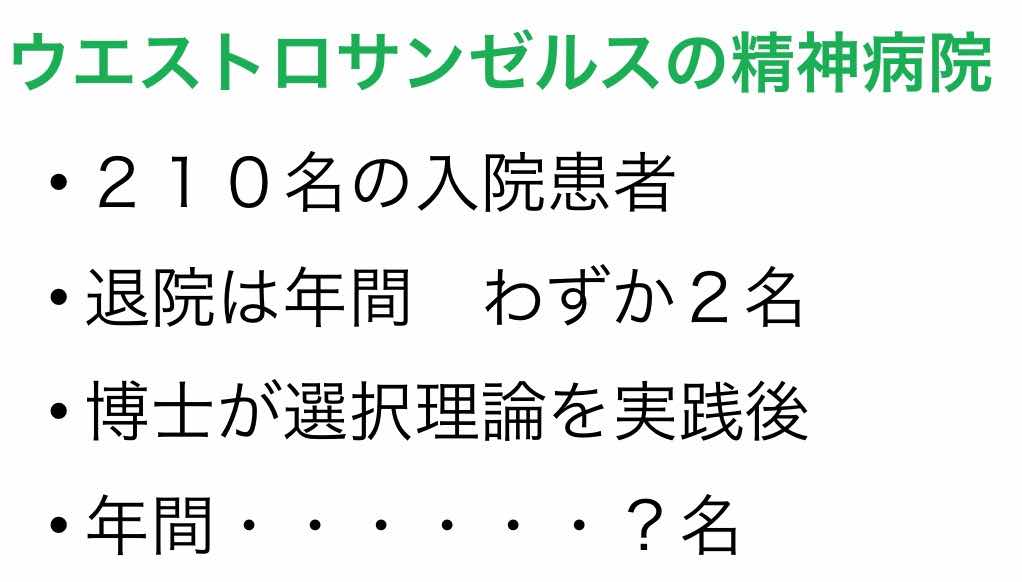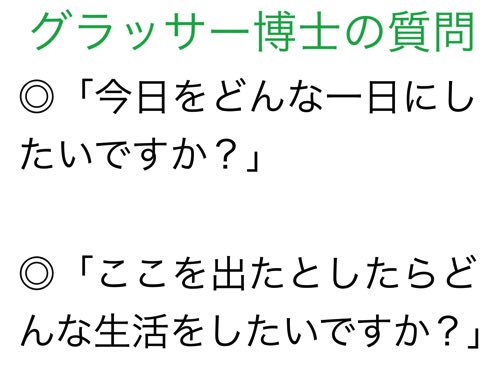2019年最初にRIDE( ライド:たのしい教育研究所 )が開発した教材は「RIDEスタースタンド」です。
大人気の講座〈宙たび〉仕様で作成しました。
※〈宙たび-3〉は募集人数300%に達し、締め切らせていただきました
わたしが「こんなカンジで制作できると思うんですけど」と大まかな話をしたところ、ミエ先生がその話を活かして原型を創り、キミ先生、タヨ先生が加わってサッと20個くらい作ってくれました。
これです、シンプルなフォルムが気に入っています。

このスタンドはスマホで星空の写真を撮るときに大活躍してくれます。
売られているスマホスタンドをいくつか仕入れて、仲間たちと星空の写真を撮って来たのですけど、手で支えなくてはいけなかったり、天頂あたりの角度は無理だったりと、どれも今ひとつでした。
そこでいろいろ考えていて閃いたのがこの〈RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )式の星空撮影スタンド〉⇨「RIDEスタースタンド」です。曲がりやすい針金を利用しているので、角度を変えるのも簡単にできます。
それで撮影した写真をご覧ください。
一眼レフなどの専用のカメラではなく、どれもみんなスマホで撮ったものです。

真ん中上側に〈オリオン座〉、その左下に大きく輝く〈シリウス〉が写っています。〈シリウス〉は全天にある太陽以外の恒星の中でもっとも光り輝く星です。
星空撮影の本やサイトのはほとんどには「星の写真を撮るにはまず一眼レフのカメラとしっかりした三脚を準備してください」と書かれていますから、これが庭先にスマホを置いて撮った写真だとは想像できないのではないかもしれません。
柔らか目の針金でシンプルに作ってあるので、星空の向きに簡単に角度を調整できます。
ほぼ真上の写真も撮ることができます。
これがそうです。

RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )のメンバーで夜な夜な星の写真をとって画像を交換しながら「たのしすぎるね」と話し合っています。
ジョイント部をもう少し改良して、明後日の〈宙たび-3〉の参加者にプレゼントする予定です。
いろいろな方たちの笑顔に結びつく結果がはっきりしたら、さらに量産して、欲しい皆さんに実費でお分けしようという計画もあります、ご期待ください。
毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックが元気のバネです➡︎一緒に〈たのしい教育〉を広げませんか。簡単な方法があります。ここのクリックで〈応援している〉の一票入ります!