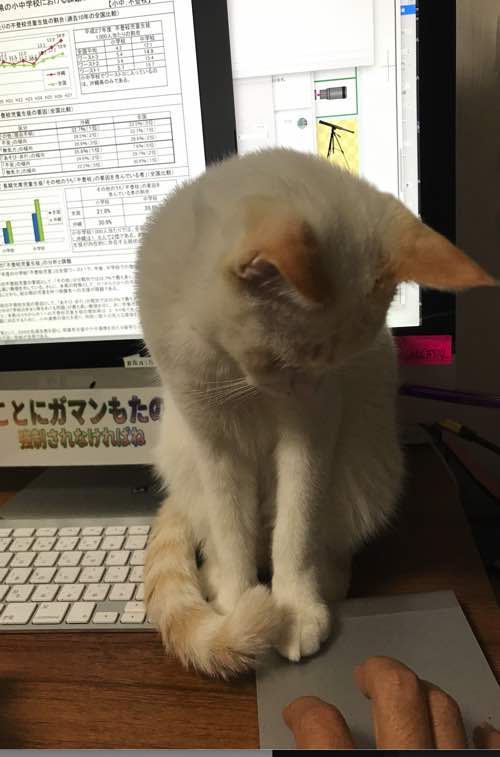この日はRIDE( ライド:たのしい教育研究所 )の師走がマックスの1日。お昼頃までは南の方で〈沖縄県児童館職員研修会 認定講習〉の講師を勤め、参加した皆さんにたのしんでいただきました。
昼から夕方にかけては中部で〈出前児童館〉。
夕方から夜は北の方で〈宙たび〉です。
私いっきゅうは朝早くからフル稼働で、研究所でまとめものをして帰途についたのは午前1時でした。
時系列を逆にして今回は〈宙たび〉の様子からお届けいたしましょう。
この日は「こんなに空を見たのは初めてだ」というくらい、朝から雲の様子を眺めていました。夜から〈RIDEの宙たび〉、星空をたのしむワークショップがあるからです。
あいにく今週はずっと雲がしっかり立ち込め、夜は星の光が見えません。
週間天気予報でも星空指数でも〈星はほぼ見えない〉ことがハッキリしています。
星を見る私たちに天気が合わせてくれるわけはなく、随分前に取られていた日程は残念な状況で幕をあけました。
案の定、スタッフと天体望遠鏡をセットしながらも雨が予想される空模様・・・
いつでもビニールで覆って片付けられる様にしています。

前回の〈宙たび- 1〉は、当初「数名で開催します」という依頼だったのですけど20名弱の参加者となりました。
その後、企画して下さった行政に、参加者の方たちからの感謝の言葉がたくさん届き、それと同時にRIDE(ライド)のたのしさが口コミで広がって、今回の〈宙たび-2〉は「制限を設けたものの結果的に30名程度に絞り込むのがやっとです」という主催者からの悲鳴に似たお願いを受け入れて開催することになりました。
希望者全員を受け入れたいところですけど、望遠鏡やものづくり教材の関係で、それでもせいいっぱいの受け入れです。主催者から「締め切りました」というお話が届いた皆さんには、私からもお詫びいたします。
さて〈RIDEの宙たび〉は雨天でもたのしめることは実験済みです。
それでも今日の空模様を見た参加者は「星の見えないワークショップなんて」と考えて、足を運ぶ人はほとんどいないのではないか、という予想もあって、5人の講師陣で会場に向かいながら「来てくれた人が2~3名で、現地スタッフを交えると3人で一人に教えることになったりして」という話をしていたくらいです。
ところがフタを開けてみるとびっくり、申し込んでくれた皆さんは全員参加。
12月の気候に天気の悪さが重なった寒い中でも、始まる前から熱気が会場いっぱいに満ちていました。
プログラムは〈星空の魅力〉を伝えながら「明日晴れたら、この手作り望遠鏡で月を見ましょう」という〈ものづくりコース〉もあります。
このサイトでも紹介した「衝撃的に簡単 手作り望遠鏡」を作ってみんなでたのしみました。もちろん参加者も大満足で、世界で一つのオリジナル手作り望遠鏡をたのしんでくれました。
これは10分程度で作成してあと、みんなでホールの外に出て、遠くのものを眺めているところです。


星は見えませんが、外に出て〈星をたのしむ4つのブース〉をたのしんでもらいました。これはRIDE( ライド:たのしい教育研究所 )オリジナルの発想で、私が全国、そして海外の観望会を回って感じて来た疑問やわだかまりを元に組み立てたプログラムなので、詳しく書くことは控えておきます。星は見えなくても、みんな子どもの様に喜んでくれている様子が伝わってくるのではないでしょうか。

そうやって4つのコーナーでじっくり皆んなで眺めていると、プログラム後半、ある方が「いっきゅう先生、星が出ています」と、みんなが見ている所とは別なところに輝く星を見つけてくれました。そのうち、なんとびっくり、雲の切れ間から星たちが姿を見せてくれていたのです。
そのうちに、見える星がどんどん増えていきます。
さっそく〈晴れバージョン〉で想定していたプログラムを導入。
「では皆さん、寝っ転がって、このきれいな星空を味わいましょう」と話し、A先生が、降った雨で濡れたビニールシートを拭いて準備してくれた二ヶ所に分かれてみんなで寝っころがりました。
 「あー、カシオペア(山形星)が見えた!」
「あー、カシオペア(山形星)が見えた!」
という声。
確かに出ています。
「すると、こっちに北極星(にぬふぁ星)があるはずですよ」とレーザーで示すと、そのうちに雲が晴れて、北極星(にぬふぁ星)も見えました。
「こっちにオリオンビール座、オリオン座が見えます」と、講師の一人Rさんの声。 どんどんいろいろな星の輝やきが見えてきます。
〈宙たび〉は「いろいろな星や星座の名前を覚えるプログラムではありません」という話は、今回も強調していますから、講師陣もそれを心得ていて、星座や星の名前は四つくらいです。星をたのしむなら、まずそれで十分です。
数分後、なんと隣のシートから「流れ星が見えタァ!」という声が響いてきました。
「それは〈心の目〉が見せた星ですかァ?」と大きな声で聞き返すと
「ほんと~ですゥ!」との声。
「見えた人、手をあげて~」というと「ハーイ」という声がたくさん聞こえてきます。
なんと半分以上の方たちが流れ星を見ることができたといいます。
私はその日、視力に合わないメガネを持って行ってしまって、ハッキリみることはできませんでしたけど、言われてみたらなんとなく一つの方向でスーっと流れたスジが見えた気がしましたから、それだったのかもしれません。
雲はずっと同じところにとどまっているわけではありません。
雲の厚い重なりも、風にのって動いているうちに、宙好きの人たちに美しい星空をプレゼントしてくれることがあるのです。
加えて〈宙たび〉の会場は沖縄本島北部。
名護市よりもっと北の空気がとてもきれいで星空を眺めるのに絶好の場所です。
その〈素晴らしい場所〉と〈宙たびの雨天対応プログラム〉だったからこそ、大きなクリスマスプレゼントをもらうことができたに違いありません。
雨がふったり止んだりの〈宙たび-2〉でしたけど、参加者の皆さんの評価は今回も満足度100パーセント。
RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )にとっても、すばらしい時間になりました。
この〈宙たび-2〉は実は私いっきゅう自身に、とても大きなプレゼントくれました。それに関しては想い大きいものがあるので、チャンスがあれば稿を分けて書かせていただきます。
毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックが元気のバネです➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆