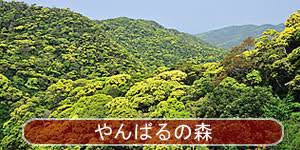たのしい教育研究所はウェブサイトの構築のアドバイザーではありませんが、時々、サイトの組み立てについての相談が来ることがあって、相手がたのしい教育に携わる仲間の場合には丁寧にお答えしています。
ちなみに私いっきゅうは記事を綴ることは大好きですが、サイト構築の専門というわけではありません。
RIDE(ライド)にはサイト構築専門のI先生がいて仕切ってくれています。
web上を検索すると〈人気サイトになるために〉という様な記事が林立しています。
たとえば・・・
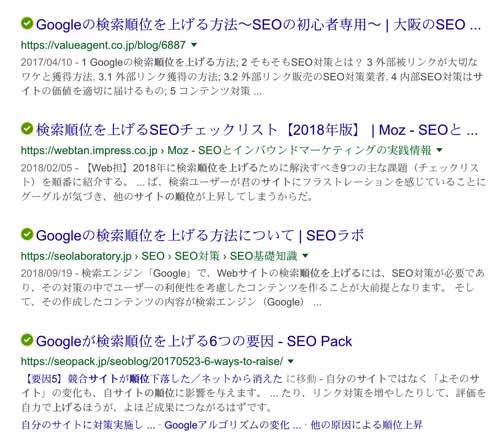 ※検索ランキングをアップする取り組みをSEOといいます
※検索ランキングをアップする取り組みをSEOといいます
実際、いろいろなノウハウが存在する様です。
ある程度上位にくると。ランキングを上げたいと考えている団体などをリサーチしているのでしょう、「もっとランキングを上げたいと思いませんか」という電話がくることがあります。
「年間100万円でランキング1位を保証します。ためしに一ヶ月 ◯万円 でためしてみませんか」という様な話です。
そういう仕掛けで上位に登ったサイトには特徴があります。何十、何百の順位が急激に伸びていくからです。
RIDE(ライド)の様に読者の方たちの人気のみに支えられているサイトは上がり下がりを繰り返しながら推移します。
つまりどんどん上昇していく一方のサイトと上がり下がりしながら推移するという動きの違いです。SEO専門会社の手をかりればグンとアップするのですけど、それがなくなると当然の様にグンと落ちるのです。
さてサイトの本質的な人気度をあげるために最も大切なのことは〈読みたくなるサイトの記事を綴っていくこと〉です。
上位のランキングは激しく動きます。
先日、読者の方から〈学問・科学系〉でRIDE(ライド)の順位が6位になっていましたという連絡が届きました。
久々にチェックしてみると確かにそうなっていました。
これもまた下がって、また上がってという動きを繰り返すことになりますが、ふりこの振れ幅の一方が、また上位に近づいたというのは嬉しい結果です。

これからも、みなさんに喜んでもらえる記事を綴っていきたいと思っています。
こういう内容を読みたいというリクエストがあれば遠慮なく送ってください。
毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックが元気のバネです➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆