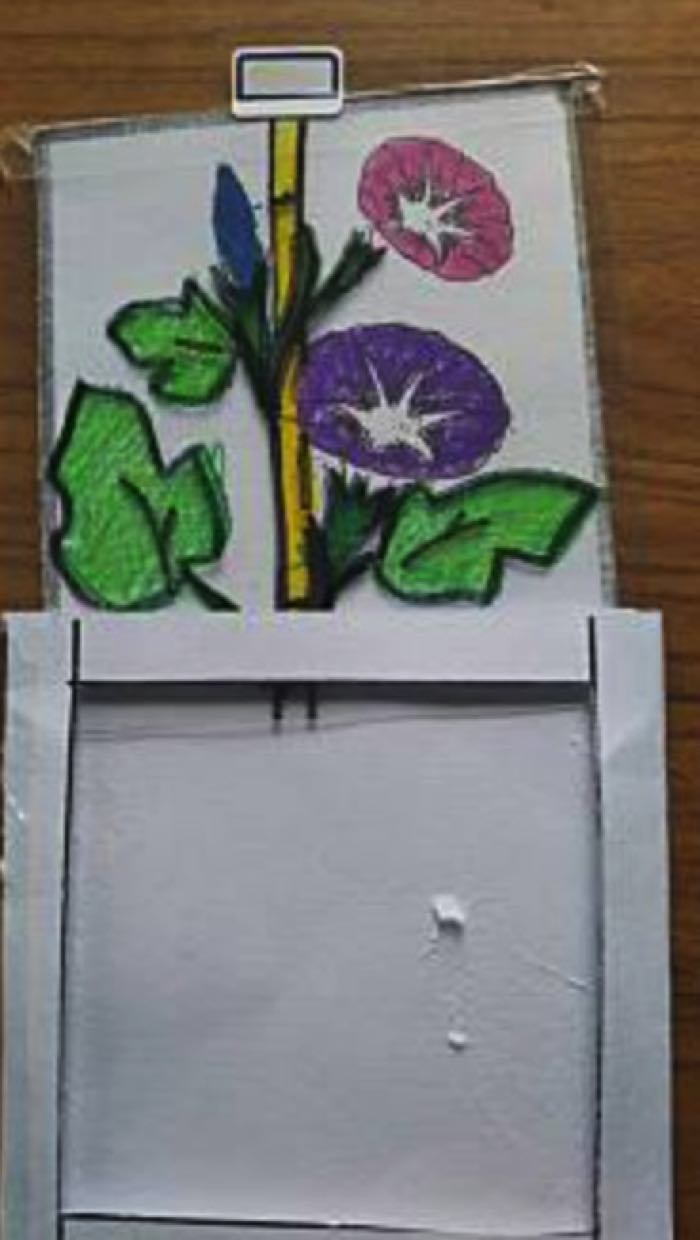今回は今までほとんど話したことのない私いっきゅうの発想法を紹介します。いずれ期が熟したらメルマガにしっかりまとめたいと思っています。その助走という段階ですけど、それでも骨格は伝えることができるとおもいます、お付き合いください。
教師をしながら自分自身に時々問いかけていたのが「自分は子どもの頃こういう先生に教えてもらいたかったか」「同じ学校にこういう先輩がいたらよかったと思える教師か」ということです。
教師になって右も左もわからないころ、こうやってたのしく授業している先生がそばにいたらどんなに良かっただろう、そういう先生からたくさんのことを学べただろう・・・、そういう教師に自分はなれているのだろうか?
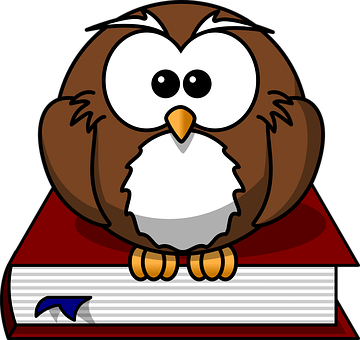
子どもの頃の私いっきゅうに、こういう様にカブトムシを紹介してくれる先生がいいたら、こういう様に磁石の魅力を伝えてくれたら、困っている時にこんな感じで話を聞いてくれたら、アドバイスしてくれたらetc. そういう先生に自分はなっているのだろうか?
もちろん人間は完全ではありませんから、失敗したり、立ち止まったり、別なところを向いていたり、いろいろなことがあります。
それでも目標が定まっていれば、ゆっくりそこに近づいていくことができます。
たくさん子ども達が、クラス全員の子どもたちが歓迎してくれる教師になる、という目標の前にまず、子どもの頃の自分が喜んでくれる教師なのかどうかという評価基準でとらえてみる。
たった一人を想定していても、きっとそれはいろいろな人たちの笑顔につながるというのが私の発想法の一つです。
それは過去を想定していながら実は未来を拓くことになります。
そもそも自分自身が受けて嬉しくない様なものを他の子ども達に授業して喜んでくれるでしょうか?
いるかもしれません、しかしその割合はかなり少数でしょう。
そうやって自分の力を磨いていくうちに、私いっきゅうがいろいろなところで実施する授業のほとんどは高い満足度を得るほどになってきました。
もちろんまだまだ発展途上です。
これからももっと磨いていきたいと考えています。しかしその時には必ずといってよいほど〈子どもの頃の私いっきゅうが、教師なりたての私いっきゅうが歓迎してくれるものになっているか〉という視点を根幹に据えています。
RIDEの講座で授業をするメンバーもどんどん増えてきました。その授業検討の時にも教材開発の時にも、子どもの私いっきゅうの感覚が顔を出します。子どもの私の感覚が「これはつらい」と声をあげたら、大人の今の私が率直にそう伝えます。そうやっているうちに、メンバーの力も着実に高まっていきました。
気に入った方はどんどん利用してください。
RIDEの発想法は、どこかに発表する場合には〈RIDEの発想法だ〉ということを伝えていただく手続きさえあれば、自由に利用してもらってOKです。
毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆