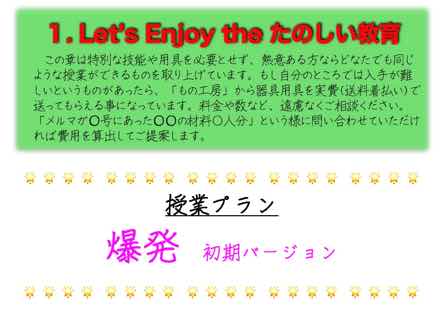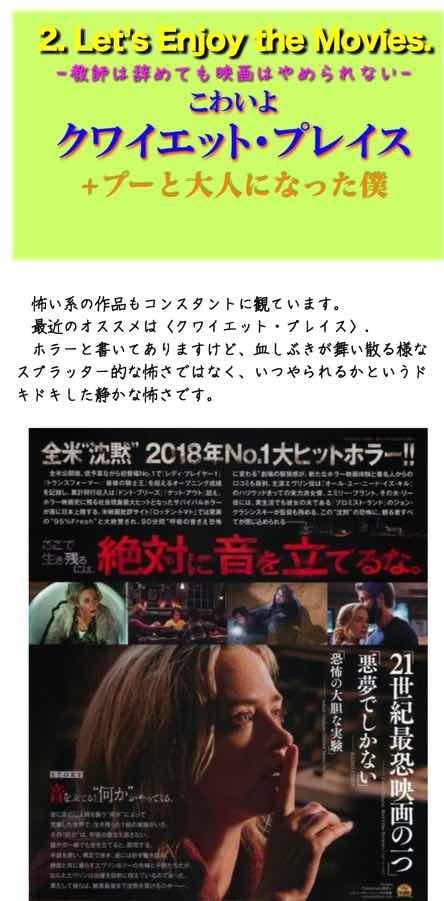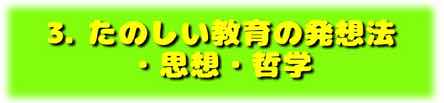RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )に勢いのよいニンニクが届いたので、アウト・ドアで重宝する〈ニンニク味噌〉を作ってみました。

作るのは難しくありません。
食材も特に決まりはなく、〈味噌〉と〈ニンニク〉をベースにして、キッチンにあるものを混ぜて作っていきます。
これは作りたての〈ニンニク味噌〉です。

トリ肉(ボイル済)やサラミソーセージも入れました。

他にもニラやゴマ油、ナッツを入れてみました。

食材を小切りにしてビニール袋に入れてまぜていくだけなので、作るのはとてもカンタン。

一週間くらい寝かせると味噌で熟成されていくのでニンニクもまろやかになっていきます。
でも作りたてでも美味しいですよ。
ご飯にのせたり、椀にスプーン一杯ほど入れてお湯をそそげば、そのまま味噌汁になります。
美味しいものづくりも〈予想チャレンジ〉、いろいろな人に味わってもらって評価が高ければメルマガに詳しく書こうと思っています。詳しく書くといっても、この写真を参考にして自分オリジナルで作ってみるとどうでしょうか。
毎日たのしいことに全力投球、RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )です。
みなさんの応援クリックが元気の源です。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆