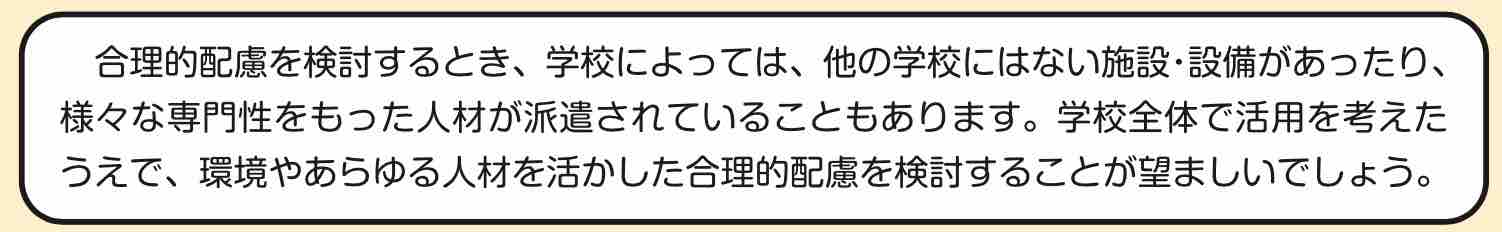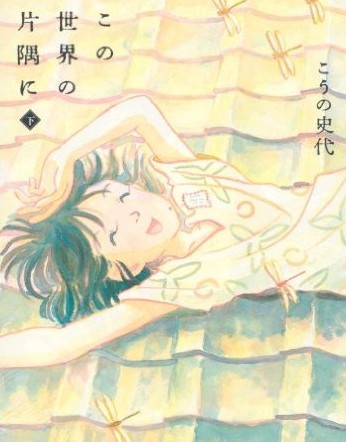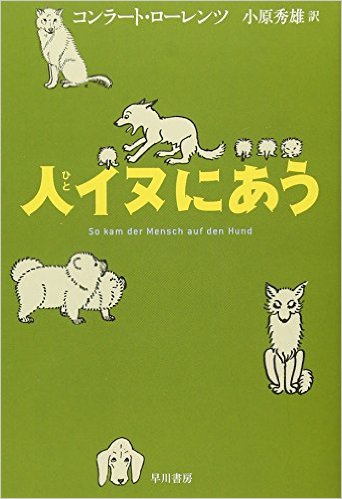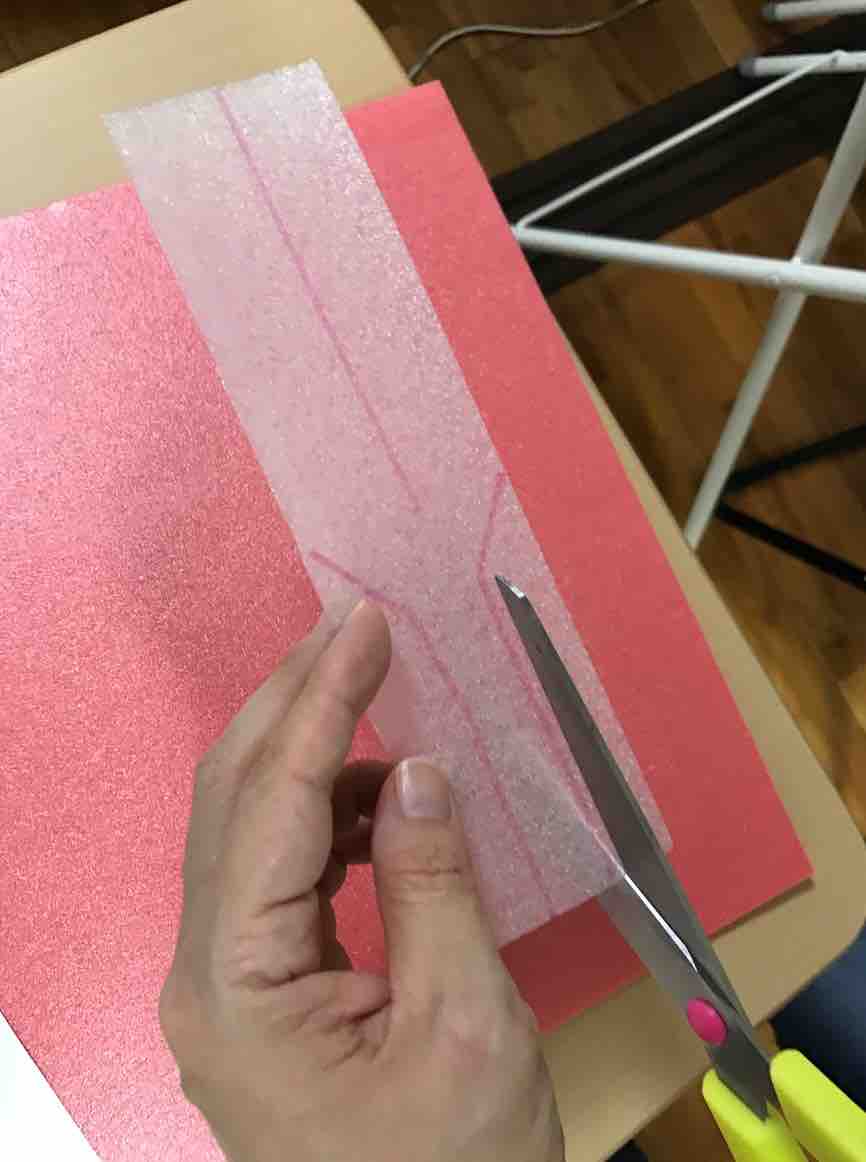インクルーシブ教育について若い先生方に話をしたところ「うまく整理できました」という評価・感想がいくつもあったので、少し書いてみます。時代が進むにつれて教育現場には「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」「自閉症スペクトラム」などいろいろな言葉も増えています。そういう言葉を理解する時に、歴史的変遷や、その言葉本来がもつイメージを把握しておくことも大切なことです。今回の記事は沖縄県 教育委員会「インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育」も併せてお読みください。教員採用試験でも狙われる内容だと思います。
※
いろいろなところで語っていることですけど、わたしが日本語の中で最もといってよいほど嫌いな言葉が「障害」という言葉です。ですから教育用語の解説の時に最小限で使うくらいです。「知的に少しハンディがある」「運動するにはハンディが大きい」など「ハンディ」という言葉で表現できますから、わたしの様な言語感覚の方はそれを用いるといいと思います。
ところがかつて特別支援教育の歴史の中では、〈障害〉という言葉より驚くべきことばが使われた時代がありました。ハンディのある子ども達をなんとかしたいという意図はあったと思いますが、それを〈廃人教育〉という言葉で表していたのです。明治期のことで、文科省のサイト「特殊教育の発展」にもしっかりと出ています。それ以前は、家の奥座敷から出さない様にしていたこともあったといいますから、それからみると大いなる進歩です。そして現在、そういう言葉が克服されたことは教育の大きな成果の一つでもあると思います。ただしいくら良い意図でも、相手を傷つけることがあることを知る意味でも、〈廃人〉という言葉がまかり通っていた時代があったのだということを、わたしたち教育者は知っていてもよいとおもいます。
そして未来においては「〈障害者〉という言葉を使っていた時代さえあったのだ」と言われる様なこともあるのだろうとおもいます。話は裾野を広げてしまいますが、かつて知人から「協力」を要請され、そのネーミングをどうにか変えられるなら一緒にやりましょう、と答えたことがありました。具体的な活動の名称は控えますが「性同一性障害者の差別をなくそう」という取り組みでした。性同一性を《障害》と呼んでいる時点でわたしは引いてしまいます。その様な方達を〈障害者〉と呼んだ時点で、わたしの様に差別を感じてしまう人もいるのです。「差別をなくそう」という人たちは、せめてそういう言葉からくるイメージを大切にしてもらえたらという気がしてしまいます。といっても、これはおそらくたくさんの人間の中でわたしくらいが感じていることなのでしょう。しかし未来的にはゆっくりとこのイメージが広がっていくという気がしています。
話を戻しましょう。
かつて呼ばれていた〈廃人教育〉という言葉はなくなり、それが特殊教育となり、特別支援教育と呼ばれる様になりました。
そして現在の特別支援教育の中ではいろいろなコンセプト(概念)が提唱されてきました。特徴的なものがこの三つです。
・ノーマライゼーション
・インテグレーション教育
・インクルーシブ教育
それらについて説明してみましょう。
a.ノーマライゼーションについて
ノーマルとは〈標準的〉とか〈普通〉という言葉ですから、ノーマライズするというのは〈標準的にする〉〈普通の状態にする〉というイメージの言葉です。ですから、ノーマライゼーションという言葉は、教育とは別のところで普通に使われています。
たとえばわたしも授業や講演で利用するために動画編集することがありますが、音量を均一化する処理です。大きい音や小さい音を、ある範囲の中に納めて、音割れを防いだり、聞こえない音を上げたりする処理を〈ノーマライゼーション〉と呼びます。
 教育で利用されるノーマライゼーションという言葉には、ハンディのある人たちも普通に暮らせる世の中にしようという理念が込められています。今では普通に使われているバリアフリーという言葉も、このノーマライゼーションの理念の中で提唱されてきました。
教育で利用されるノーマライゼーションという言葉には、ハンディのある人たちも普通に暮らせる世の中にしようという理念が込められています。今では普通に使われているバリアフリーという言葉も、このノーマライゼーションの理念の中で提唱されてきました。
b.インテグレーション教育とは
インテグレーションは〈統合〉という意味で、いろいろなものを併せていって完全な状態にするというイメージを持った言葉です。インテグレーションという言葉もごく普通に使われています。数学の「積分」のことです。数学史上の画期的アイディアの一つで、無限に小さい変数を扱う「微分/ディファレンシャル」と、極限まで分割したものを積み上げていく計算が「インテグレーション/積分」です。ちなみに車好きの人は知っている人も多いと思いますがHONDAがかつてインテグラという車を生産していたことがあります。インテグレーション(統合)という言葉の造語ですが、車のもつ良さを統合してより完全なものに、というコンセプトをもった車でした。
 特別支援でいうインテグレーション教育は、ハンディのある子ども達も、そうでない子ども達も一緒に(統合して)教育しようという理念をもった言葉です。ですから「統合教育」という名前で呼ばれることもあります。普通学級の子ども達もハンディのあるクラスの子ども達も、ある教科では一緒になって学習する交流学習も普通に行われていますが、これもインテグレーション教育の流れです。今、学校で一般に行われている特別支援的な学習はまだインテグレーション教育の段階に止まっていることがおおいと思います。
特別支援でいうインテグレーション教育は、ハンディのある子ども達も、そうでない子ども達も一緒に(統合して)教育しようという理念をもった言葉です。ですから「統合教育」という名前で呼ばれることもあります。普通学級の子ども達もハンディのあるクラスの子ども達も、ある教科では一緒になって学習する交流学習も普通に行われていますが、これもインテグレーション教育の流れです。今、学校で一般に行われている特別支援的な学習はまだインテグレーション教育の段階に止まっていることがおおいと思います。
c.統合(インテグレーション)から包み込む(インクルーシブ)教育へ
統合(インテグレーション)というよりも、いろいろな子ども達を包み込んで(インクルーシブ)教育することが大切である、ということで提唱されたのがインクルーシブ教育です。インクルーシブ教育・インクルージョン教育、両方とも全体を包み込むというイメージの言葉です。
ハンディのある無しで異なる教育を実施するのではなく、両者が一緒になっても、より豊かな教育が保証される様な教育を理念としています。ですから、かなりハードルが高い教育システムだということができるでしょう。
板倉聖宣(仮説実験授業研究会代表・日本科学史学会会長)がかつて沖縄で「頭がよいとか、そうでないとかいうことで結果に差がでる様なものではなく、どういう子ども達でも感動できる様な教育内容として仮説実験授業ができあがった」ということを語ってくれました。たとえば仮説実験授業の授業書「じしゃく」で、ハンディのある子ども達も普通学級の子ども達も一緒に授業したことがありましたが、どの子も感動してくれました。そして知識内容の定着も高いものがありました。そういうかなり上質な教育内容が伴ってはじめて可能となる教育だと思います。
インクルーシブ教育について沖縄県 教育委員会がまとめた「インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育」にもありますが、そのシステム的なものとして〈合理的配慮〉と〈基礎的環境整備〉とが重要なキーワードとして提示されています。※もちろん文科省の指針の元に作成されていますから沖縄県独自のものというわけではありません。
〈基礎的環境整備〉についてはいろいろと具体的なものが示されていますが、残念ながら〈合理的配慮〉についてはあまり具体的ではありません。そもそも〈配慮〉と言わず〈合理的配慮〉という言葉になっていること自体、「学校でその配慮をすることが合理的だと言えるのか」という価値判断を委ねたものなので、難しいものがあるのでしょう。
少し長くなりました。
今回はここまでにしましょう。
頭と身体とこころが喜ぶ教育 それが〈たのしい教育〉です。
たのしい教育を実践できる力のある先生たちを育てる活動にも全力を尽くしています。
あなたの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか-いいねクリック=人気ブログ!-