たのしい教育研究所(RIDE)のスポーツ系スタッフにヨガのインストラクターをしているAさんがいます。大学で教育を学び、海外での活動の経験のある熱意ある人物の1人です。
Aさんに「ヨガにあるスピリチャル的なものを削ぎ取って、純粋にスポーティーなものとして普及してはどうだろう」と相談し〈この動きよりはこう〉〈もっとゲーム的なものを増やしては〉という様にブラッシュアップして実施しているのがたのしい教育研究所(RIDE)型のヨガです。子ども達から大人まで学ぶことができます。
Aさんの素晴らしい指導で、子ども達のたのしさがどんどん高まっていくのを感じています。
これはいつもお母さんと一緒に参加してくれているTくん、股関節を伸ばしながら母親と語り合っています。とてもいい表情をしていると思いませんか。

これは円になってゆっくりと身体を伸ばしていくシーンです、周りの人たちとの力のバランスがとてもたいせつになっていくエクササイズです。

指導者のAさんが、一人一人に体幹を動かす時のコツを伝えてくれています。
これがとても有効に作用です。

余分な力がかかっている部分、そしてもっと力を入れた方がよい部分を的確に伝えています。

「ヨガはインドのラジオ体操です」という表現があるそうです。
はじめにも触れましたが、ヨガにはスピリチャル的なものが結びついた形が多く見受けられます。
特に神様という言葉を使わないにしても〈宇宙の精神と一体になって〉という様な言葉かけを聞くことがあって、その形を公立の学校教育に導入するのは無理があります。純粋にエクササイズとして提供する〈RIDE型ヨガ〉を数ヶ月試みてきましたが、学校教育の中でもかなり効果をあげられるものの一つであることは間違いないと思います。
興味のある方は8月の出前児童館にぜひご参加ください。
毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆

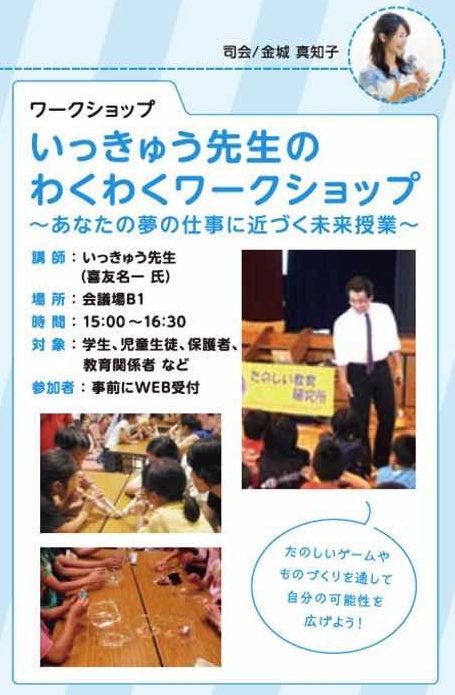




 出前児童館では私いっきゅうはサポート係で他のスタッフが指導してくれるのですけど、2日目の出前児童館で担当のOさんがおやすみすることになりピンチヒッターで私が担当しました。
出前児童館では私いっきゅうはサポート係で他のスタッフが指導してくれるのですけど、2日目の出前児童館で担当のOさんがおやすみすることになりピンチヒッターで私が担当しました。 わたしが手を取って回し方を二、三回コーチすると
わたしが手を取って回し方を二、三回コーチすると
 もちろん床に置いて、ビューンと走らせることもできる様になりました。
もちろん床に置いて、ビューンと走らせることもできる様になりました。
 別室で授業展開のブラッシュアップをしている私のところに、とてもたのしそうな声が響いてくるので「何してるんだろう」と思って見にいくと、こういう地道な作業をしながら、自分の身近に起こったおもしろかった話で盛り上がっていた様子。
別室で授業展開のブラッシュアップをしている私のところに、とてもたのしそうな声が響いてくるので「何してるんだろう」と思って見にいくと、こういう地道な作業をしながら、自分の身近に起こったおもしろかった話で盛り上がっていた様子。