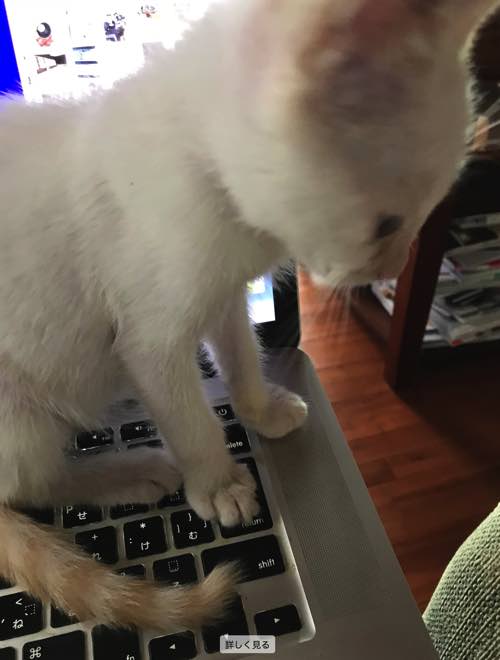たのしい教育は〈たのしさというスパイス〉をふりかけることで、子どもたちが少しは勉強してくれるだろう、という様な小手先の手法ではなく、教育を根本的に改革するものとして提唱しています。それは「たのしくてもっと勉強したい」という構造であり、新学習指導要領に謳われた〈自主的・対話的で深い学び〉も「たのしい教育」の元でこそ成立すると考えています。
現在は、明治期に近代的な教育制度がスタートして以来、新しい時代へ向けて大きな変革が始まっているのです。
文科省の国立教育研究所でその始動を感じ取っていた板倉聖宣は、仮説実験授業という画期的な教育方法と共に、時代の変化をわたしたち教育者に伝え続けてきました。
今から五年前、科学技術振興機構(JST)の講演に呼ばれた板倉聖宣は、こういう話をしています。わたしにとっては何度も聞かされてきた内容で、特に新しい話ではありませんが、こういうことを聞いていない方達には刺激ある内容だと思います。紹介させていただきます。
※

一番重要な今日的課題は〈日本は明治以来初めて、教育の供給過剰に陥った〉ということでしょう。
これは余り認識されていないことですが重要な問題です。
明治以来の歴史の中で、教育だけはなかなか需要が頭打ちにならなかったので、いつまでたっても上級学校がいばっていて、「勉強するまで入学させないよ」という入学試験の差別制度を保ってきました。
しかし10年近く前、それ以来から、急速に大学院が供給過剰になって、上級学校に行けば行くほど得をするという時代は終わりました。
そしてみんな勉強しなくなりました。
明治以来、入学試験を軸にして日本は教育を発展させてきました。入学試験があって初めて日本の教育が成り立っていたのです。
ところが入学試験が機能しなくなってきた。
これは見方をかえればチャンスです。
しかし一部では、いまだに入試で生徒を勉強させようとしている。
入試がだめならTOEFLというようなことで「受かったら得する試験を課して勉強させる」という構造を維持しようとしています。
しかしそういう方法は供給過剰のときには機能しないのです。
日本の教育は〈入試はいけない〉といいながら入試に頼ってやってきました。このことを認めて、かつ、その構造が機能しなくなっていることを認識して新しい方向性を考えないといけないんです。
しかしそこのところがうまく認識できてないから、今いい加減なことをやっているのではないかと思います。
板倉聖宣2013.7.7
仮説実験授業研究会ニュースより抜粋
※
新しい時代は変革の痛みを伴うものですが、〈たのしい教育〉は、ゆっくり着実に〈たのしさ〉という旗幟を掲げて歩いて行きたいと考えています。それは多くの人たちの感動と希望を原動力にして進めていくもので、決して闘いや苦しみの中で進めていくものではありません。
みなさんの周りの子ども達が〈こういう勉強ならもっとやりたい〉〈もっといろいろなものも学びたい〉と思ってくれる、それは未来の希望以外の何ものでもないでしょう。
そして、このサイトを毎日読んでくださっているたくさんの皆さんが、その未来の希望を大きく支えていると考えています。
最近は「こういうものを読みたい」「以前書いたあの話の続きを書いてもらいたい」という様なリクエストもいろいろ届く様になってきました。
ますます読み応えあるサイトにしていきたいと感がています。
ご意見、リクエストがありましたら遠慮なくお寄せください!⇨こちら
毎日たのしく全力投球、RIDE( たのしい教育研究所 )です! この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆