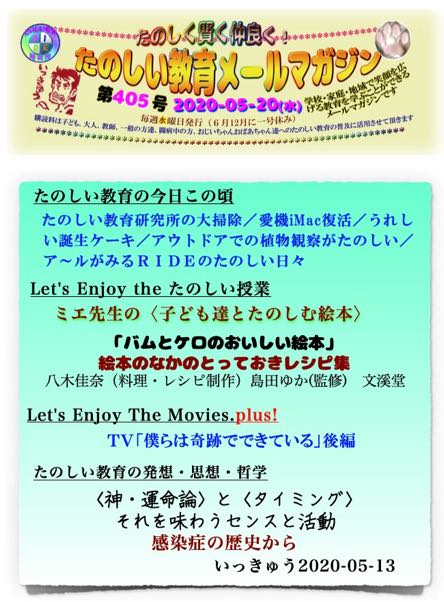研究所でワークショップを開いていると、箱いっぱいのトウモロコシをかかえた応援団のAさんが来てくれました。沖縄は梅雨の季節、雨の降り続く中、朝早く起きてAさんが収穫して持ってきた、おいしいトウモロコシです。ありがたいことです。

そのままでも美味しく食べることができます。
瑞々しいので、かじると歯の先ですぐにプチプチとはじけます。
Aさんの話によると、このヒゲも一緒に食べるとよいとのこと。

それにしてもたくさんのヒゲがついています。
このヒゲはトウモロコシのどこにつながっているのでしょう?
予想してみませんか。
とうもろこしのひげはどこにつながっている?
予想
ア.上の方
イ.下の方
ウ.真ん中
エ.その他
どうしてそう思いましたか?
では、よくみてみましょう。
こういう写真を見ると、上の方にヒゲが繋がっている様にも思えますね。

ところがよ〜くながめてみると、あることに気づきます。
今朝とりたての新鮮なトウモロコシをみてください。

もう少し大きくしてみてみましょう。
一粒一粒にヒゲが一本ずつつながっています。

トウモロコシのヒゲは〈めしべ〉です。
めしべの先(柱頭)に花粉がついて、実(タネ)が育っていくのです。
私たち人間は〈動物〉です。
自分で動いて食べ物なを手にする道を選びました。
植物はその場にとどまって生きていく方法を選びました。
動物からみて、不思議なこともいっぱいあります。
みなさんも自分でいろいろ調べてみませんか。
何をやるにも予想チャレンジがたのしい教育です。
P.S.
研究所に来てくれた皆さんに、トウモロコシをお分けしています!
毎日たのしく全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。一緒にたのしい未来をつくりましょう。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!