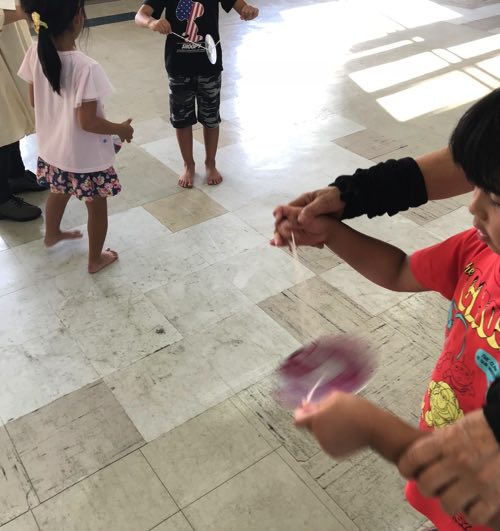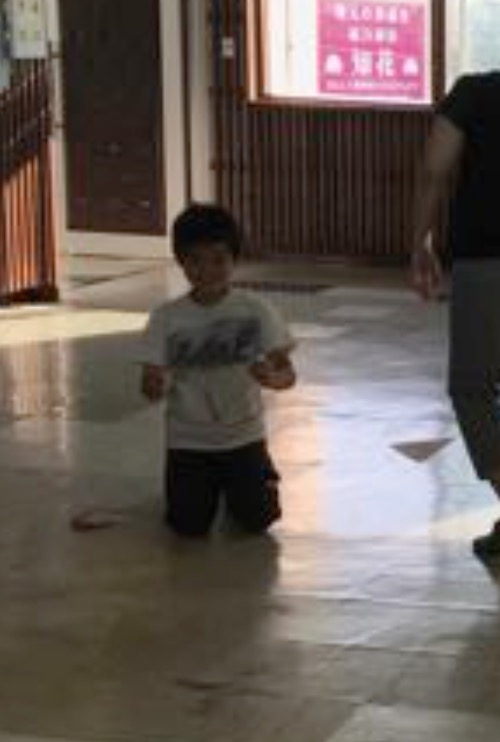教育の場で走り回っていると、いろいろな方たちから〈子どもたち批判〉〈若者批判〉を受けることも多々あります。
「いっきゅう先生、最近の子ども達はひ弱で困るんですよ」という意見から始まって
「何でも長続きしない」
「いじめ方が陰湿だ」
「ゲームばかりやっている」
「何をやりたいのだかわからない」
「昔は先生のいうことをしっかり聞いたのに、聞かない子がたくさんいる」etc.

わたしのスタンスは決まっていて「今の子どもたちは素晴らしい」「今の若者はすばらしい」という考えです。大抵はこういう受け答えになります。
「長く教育現場にいましたけど、全体としてみると明らかに、わたし、いっきゅうの子どもの頃や◯◯さんの子どもの頃よりも、とても良くなってきていると思うんですよ」
そう話しはじめて「たとえば・・・」と例示する内容は事欠きません。
決定的なものは〈近頃の若者は〉という授業プランにまとめてありますから、興味のある方はプランを入手してください。送料込650円でお頒けしています。
ところで、日本の科学をリードしてきた「長岡半太郎」という人物がいます。
1865年8月19日生まれですから、明治(1868年〜)に変わる少し前に生まれました。
彼は、ノーベル賞を受賞した湯川秀樹や朝永振一郎、鉱石などから有用な金属を採取・精製・加工する冶金学の父と言われる本多光太郎など、たくさんの科学者を育て、自らも〈土星型原子モデル〉を提唱して世界の物理学者から注目された人物です。

板倉聖宣は科学史家でもあって、長岡半太郎についてかなり深く研究しています。
「長岡半太郎でさえ〈学力がない〉と批判されていたのだ」ということを板倉聖宣の講演記録で読んだことがあります。
古い時代の教育文化を背負っている人たちから見たら、新しいことを学んでいる人たちは〈自分たちが学んだものを基準〉にして「学力がない」といってしまうのだと、という話です。
「たのしい教育メールマガジン」で以前紹介したのですけど、多くの反応が帰って来た一つです。
少し紹介しましょう。
2003年8月6日 塩尻市総合文化センターでの講演会からです。論点がずれない様に途中を抜粋しています。
板倉聖宣
私は、みなさんが非常識に思える事をたくさん言う可能性があります。
私は基本的には「考えてからしゃべる」ということはなくて、「しゃべってから考える」という(笑)大変ズルイ思考法を取っております。
せっかくこれだけの人が聞いてくれるところで話すのですから、「これはよさそうだ」と思ったことは口に出してしまう。そうするとみなさんが反応して、嫌な顔をされたり、いい顔をされたりされる。
それで「ああ、これはいいらしいな」とか「これは少なくとも仲間にはいいかもしれないけど、みなさんには分らないことらしいな」(笑)と言うようなことで、その後の私の原稿にそれを反映することになります。ですから、私はしゃべったその当座はその話には無責任であります。私の話が分らなかったら「分んない!」と言ってくださって結構です。そしたら私も気がついて、もっと丁寧に説明をしたり、「あ!それは間違いでした」と言うかもしれません。
私の考えを結論的に強く言ってしまうと、「学力というのは年がら年中低下するに決まっているのだ」、「学力は低下するのに決まっているのに、ことさら〈学力低下〉などと言うのは何か魂胆があるに違いない」と言うことでございます。
例えば、私の詳しく研究した人に長岡半太郎という人がいます。日本の物理学の伝統を確立した人です。
明治20年に東京帝国大学を卒業した人でありますから、幕末に生まれて、そして親父さんは大村藩士という肩書きで、明治の初めに元藩主にくっついて海外旅行をして、その親父さんが帰って来てすぐに息子の半太郎の前に座って、「これまでの教育は間違っていた。これからはこれでなければいかん」と、海外から持ち帰った外国の教科書を示して、「これからは、これで勉強しろ」と言われたというほど、明治の初めに恵まれた状況で新しい科学を勉強した人であります。
その長岡半太郎さんの時代、東大の授業は英語です。
教科書も英語だし、教師の大部分は外国人です。だから英語はペラペラしゃべれたりもしました。
明治の初めにあって抜群の学力があったことになります。
しかし、その長岡さんでさえ「学力が低下した」と、みんなから言われたのです。
なぜか?
関心のある方は、自分で「なぜか?」の続きを考えてみませんか。
続きは次回に掲載しましょう。一緒に〈たのしい教育〉を広げませんか→このクリックで〈応援票〉が入ります!