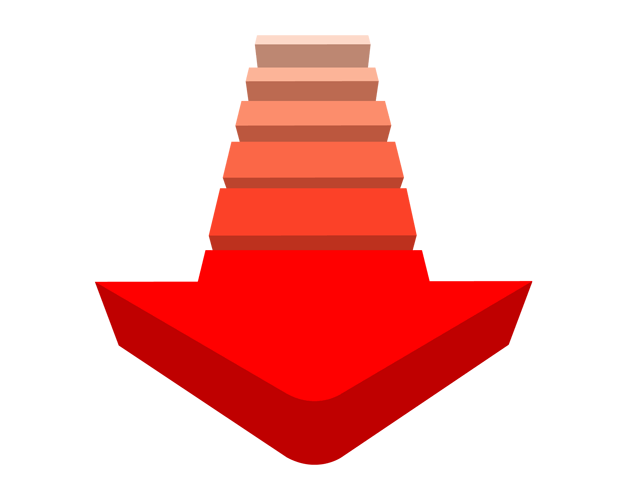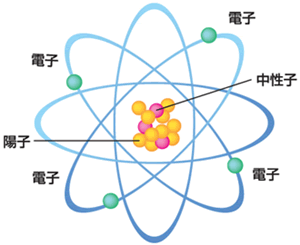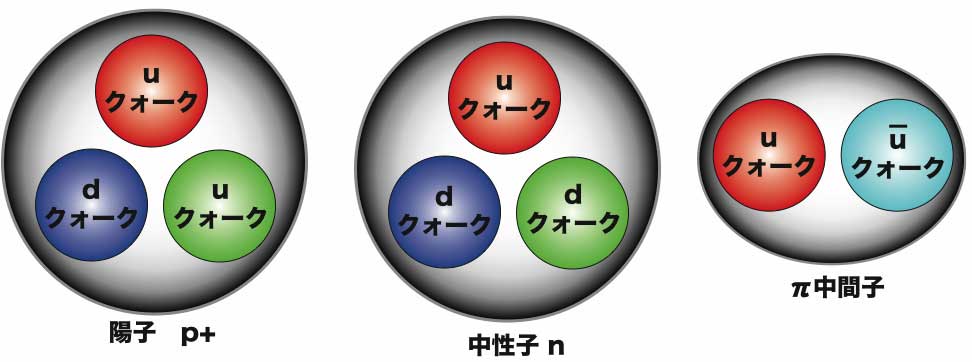たのしい教育を学びに来ている方達に講義をしていると、研究所のチャイムがなりました。
行ってみると、応援団のCさんが段ボールが3つに入った新鮮な野菜を持ってきてくれました。
いつもあたたかく研究所のスタッフを気遣ってくれる方です。
「先生、旬のもの食べて、ますますがんばってよ!」
そう言って、それぞれの段ボールにいっぱい入った、ジャガイモ、玉ねぎ、大根をプレゼントしてくれました。
ありがたく頂戴して、いろいろな方達に分けても、ジャガイモがこんなに残っています。研究所に来てくれた方達にお分けします。

美味しい野菜と応援してくださる方達の気持ちに、気力も充実する今日この頃です。
たのしく賢くなる教育方法と教育技術を広め
沖縄からノーベル賞を!
「たのしい教育研究所」です。

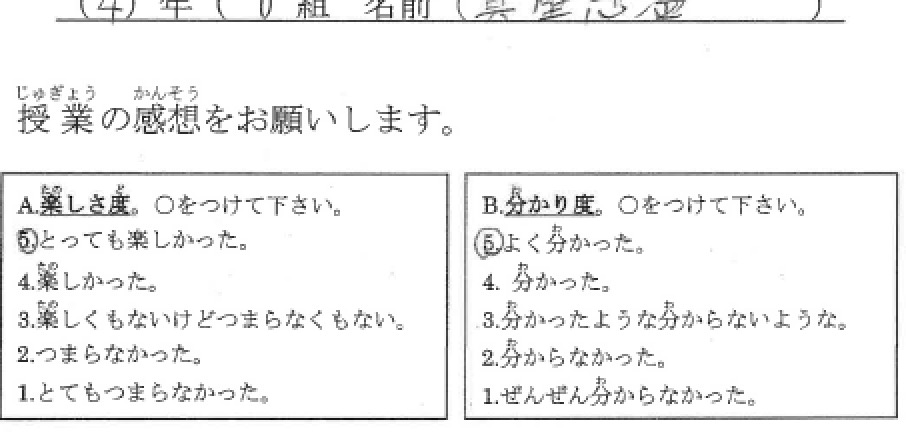
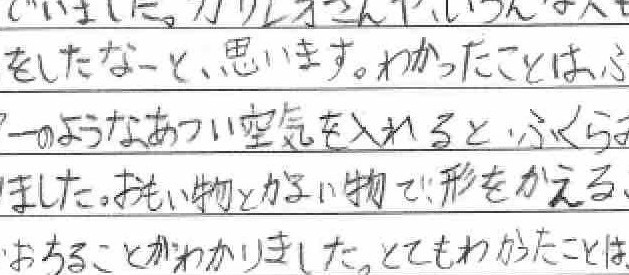
 いろいろなところから科学教育に関する相談や依頼が届きます。
いろいろなところから科学教育に関する相談や依頼が届きます。