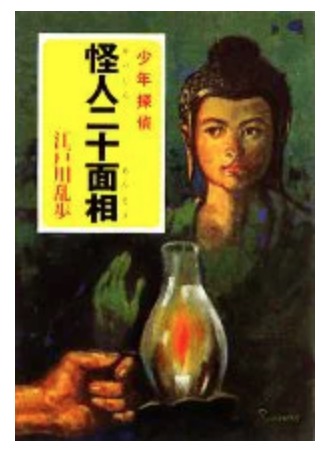おかげさまで、たの研の活動はいろいろな処から注目をうけ、活動の幅が広がっています。たの研には看護師資格をもったメンバーもいるので、コロナ対策も万全で、たの研がかかわった活動でコロナ感染者は出ていません。
コロナが騒がれ始めた頃に、いろいろな人たちからアイディアをもらったのがたのしい教育研究所の教材を各地で楽しんでもらえる様な〈たの研バス〉です。〈たの研キャラバン号〉という仮の名前をつけてあるのですけど、読者のみなさんでいい名前を思い付いたらご提供ください。
たの研の応援団の方から格安で譲っていただいたアルファードが一時期それを担ってくれていたのですけど、車体が大きく、もっとコンパクトで駐車しやすいタイプを探しはじめています。
たの研の大仕事が終わって、データの整理をはじめている時に、いただいた資料がいくつも出てきました。
こういうタイプだと中古を手に入れて四、五年はたのしめそうです。

公民館とか児童館などから要請があれば「では来月の第3日曜日の午前中にうかがいます」など月に二、三回くらい回るという感じでいけそうです。

メニューの基本形は
・ものづくり
・読み語り
・科学実験
・ゲーム
の4本立てです。
感染症が心配される頃なら一人一つのメニューに限定しておいて、落ち着いたら要望にあわせていくつかたのしんでもらう。
もちろん親子でOK、いかがでしょう。
 一番必要なのはチームリーダーです。たの研の主要メンバーは来年三月までスケジュールが埋まっています。沖縄にお住いの方で、興味のある方は、ぜひたの研の講座を受けにきませんか。修行を積んで、キャラバンのリーダーになってもらえたら嬉しいです。
一番必要なのはチームリーダーです。たの研の主要メンバーは来年三月までスケジュールが埋まっています。沖縄にお住いの方で、興味のある方は、ぜひたの研の講座を受けにきませんか。修行を積んで、キャラバンのリーダーになってもらえたら嬉しいです。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!