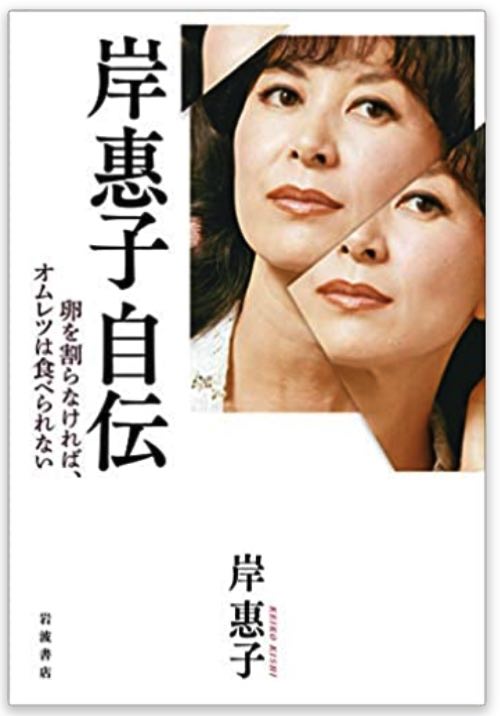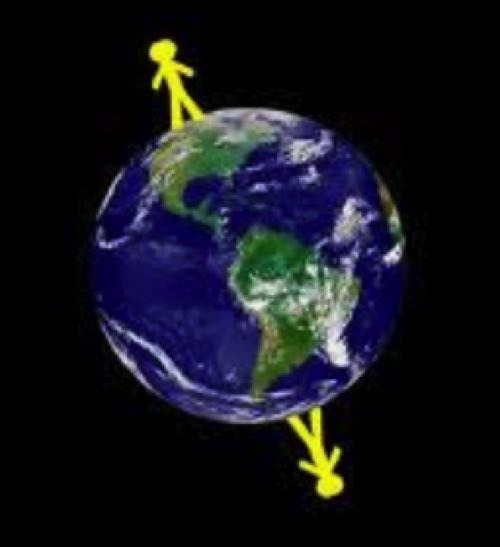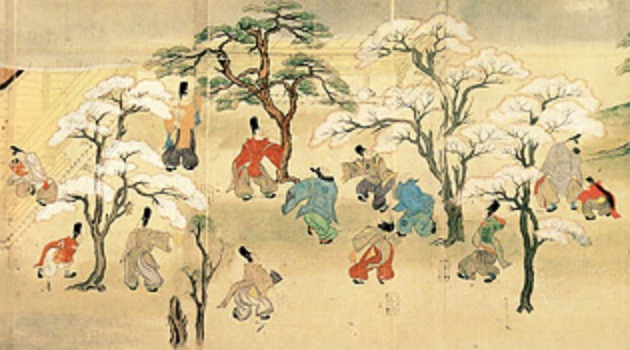前回の記事からの続きです。二週間前に発表されたのでJAXAの快挙についてはご存知の方もいると思います。太陽系内の〈小惑星りゅうぐう〉からとってきた石からアミノ酸を発見したという記事です。
初代ハヤブサで持ち帰ったのが砂つぶより小さなかけらだったことを考えると飛躍的な成果です、それも初代ハヤブサの世界的快挙があったからこそ成し得たことであるのは間違いありません。

この岩石からアミノ酸が見つかったということがニュースとなり世界をかけめぐりました。その後何か追加発表があると思っていたのですけど出てきません。いくつか質問も来ているので、そろそろこのサイトに書いておこうと思います。
※
地球の生命については〈地球〉という閉ざされた環境の中で誕生したという仮説のほかに〈地球外から隕石などによってやってきた〉という説がありました。私の学生時代には〈怪しげな説〉の一つとして扱われていました。
どうしてそういう説が出てきたかというと、地球で発見される隕石の中から〈アミノ酸〉が見つかったからです。〈アミノ酸〉というのは私たちの身体をつくっている〈タンパク質〉のピースです、アミノ酸が組み合わさってタンパク質になるのです。
アミノ酸にはいろいろな種類があって、たとえばこういう構造をしています。赤は酸素O、青は炭素N、灰色は炭素C、白は水素Hです。黄色も見えますね、硫黄Sです。
栄養ドリンクなどに配合されている〈アスパラギン酸〉もアミノ酸の一つです。下の図で上の段の中央がそれです。
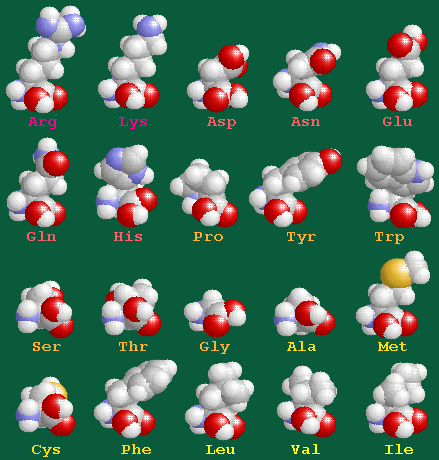
http://www.ecosci.jp/amino/amino2j.html
これまで地球上で発見された隕石からこういったアミノ酸が見つかってはいたのですけど「それは地球上で組み合わさったものだろう」ということで真剣に取り合わない科学者たちもたくさんいたのです。
アミノ酸は地球ができあがる頃のドロドロのスープ状の海の中でいろいろな原子が組み合わさってできたのであって、宇宙から来たのではない、というのです。
今回のハヤブサが届けてくれた岩石から、現在までに〈アスパラギン酸〉ほか11種類のアミノ酸が発見されました。厳重なカプセルに入れられて戻った岩石を研究室で分析したものなので、地球上で混ざったのではない、考えられます。

中日新聞より
つまりこれで私たちの生命のタネは宇宙からやってきたという説が有力になったのです。
それでもまだ科学者たちの中には「地球上の基本的にアミノ酸があまりにもたくさん発見されすぎている、これはやはり地球上で混ざったものではないか」と主張する人たちもいます。
これぞ〈The 科学〉です。
簡単にいろいろな説を信じるのではなく、別な仮説も成り立つということで対立研究をすすめていくわけです。
だから科学は信頼できるのです。
現在、JAXA(日本航空宇宙研究開発機構)とISAS(宇宙科学研究所)が全力で、その信頼性を追求しているところでしょう。
さてみなさんは、どちらの説が正しいと予想しますか?
この地球で生命が生まれ進化してきたのでしょうか。それとも宇宙から来た生命のカギが私たちの生命の扉を開いたのでしょうか。
もちろん私は宇宙派です。
この私の身体が宇宙からきたものだというのはウルトラマンみたいでたのしいということもあるのですけど、もともと太陽系そのものが〈超新星爆発〉で散った岩石たちが遠く離れた場所で再結集してできたものです。生命のタネが宇宙から来たものでないと考えるのが自然でしょう。
気づいている人はあまりいないようですけど、このことは〈神が地球の生命をつくった〉という創造説とも対立します。もともとダーウィンの進化論がそれを決定的に否定したのですけど、今回のことで生命のタネが宇宙から隕石によって飛んできたのだということになれば、ますます創造説が遠ざけられるでしょう。
どっちに転んでもたのしさ深まる今日この頃です。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!