まだ続く新型コロナ騒動で、いろいろなことを感じ考えることができました。たのしい教育との関わりの部分で少し書いてみようと思います。
1.自分の頭で考える人たちが増えてきた
まず「行政トップの判断に対して地方が独自に対応した」ということはとても大きな変化だと思います。特に教育の世界では〈上意下達(じょういかたつ/上の意向が下に伝わっていくこと)〉があたりまえだったのですけど、それに逆らう判断がいくつも出たということ、これはとても大きな変化です。
たのしい教育はそれぞれの教育関係者たちが、子ども達の笑顔と賢さの方向に自分たちでいろいろな工夫や判断を加えてすすんでいく教育です。
その意味ではとても明るい変化だと思います。

「もしも感染者が出たらどうする」と責められたこともあったでしょう。しかしそれも含めて責任をとる決断というのは、組織のトップとして〈かくありたい〉胆力です。
組織のトップだけでなく、教育に関わる、たとえば一人一人の教師が自分の頭で考えていくという力もきっと育っていることでしょう。
2.地球は実質的に一体化しているという実験結果
今回の新型コロナは、これまでそれぞれの国だけで押さえていたデータを、世界中にオープンにしてくれました。もちろん全ての国というわけではありませんけど、これだけたくさんの国々の感染者数がどんどん明らかにされたことは今までありません。
時間と共に地域を広げてウィルスが広がっていく様子に、世界中の人たちが驚きをもって見つめたことでしょう。実は今回のコロナウィルスだけが特別ではなく、毎年流行するインフルエンザはもっと爆発的な広がりを見せているはずなのです。
世界は人の流れという1つとってみても強く有機的に繋がっています。どの国も「うちの国ファーストだ」とは言えないのです。
〈自分の国だけは〉〈自分の国だけで〉という発想・行動ではどうにもならないことを実験結果としてハッキリ見すえて、地球全体として連携して進んでいくしかありません。
ウィルスによって命を落とした人たちもいます、しかしその命のことを思っても、これをきっかけに世界が協力して問題や課題を解決していく方向に進んでいけるなら、これからいろいろな紛争や感染症他によって亡くさなくてもよい命がどんどん救われていくことになるでしょう。
どっちに転んでもシメタを探して人間は生きていくのです。
3.慌ててはいけないということ
私は子ども達にも先生たちにも「たとえハブに噛まれたとしても慌ててはいけない」と語っています。実際、ハブに噛まれて、慌ててしまうと呼吸も脈も荒くなり、毒のまわりが早まります。〈困難〉でも同じで、毒が早くまわります。冷静な判断ができずに逆に解決を遅らせたり、混乱の度を深めてしまいます。
たくさんの人たちが落ち着いて、毎年流行しているインフルエンザ対策の水準を高くしていくことで、コロナウィルスなどの感染症対策にも十分効果があがります。
今回の騒動をきっかけにして、まず落ち着くということ、そして一人ひとりのウィルス対策力を高め、インフルエンザを含めて感染率を減らしていく取り組みをすすめていきましょう。
まだありますけど、これくらいにしておきます。
毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!












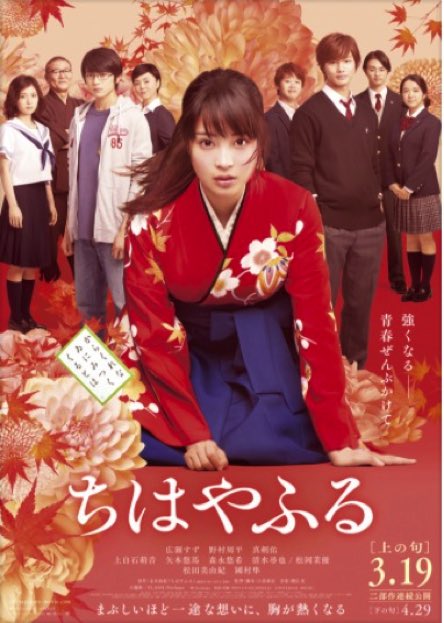
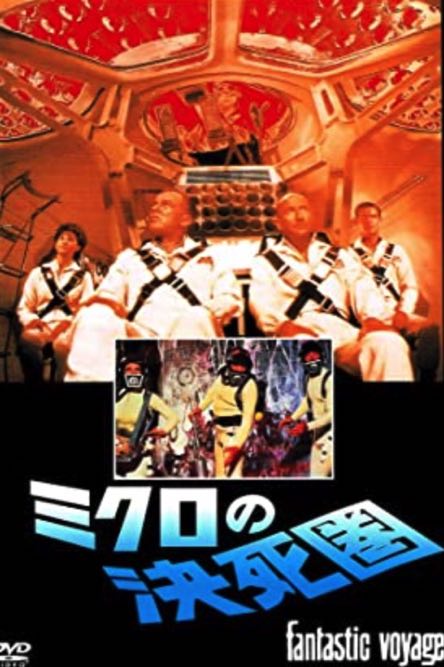
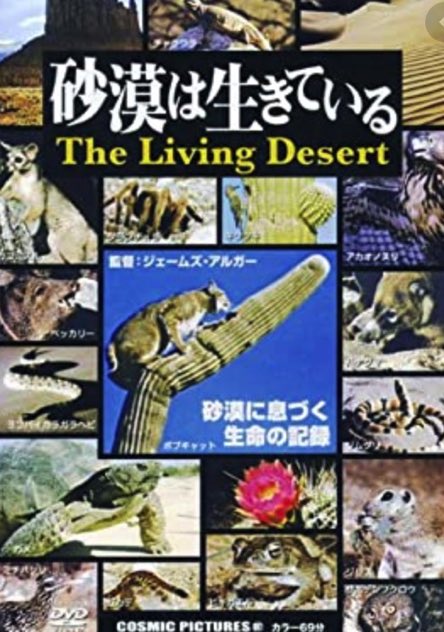


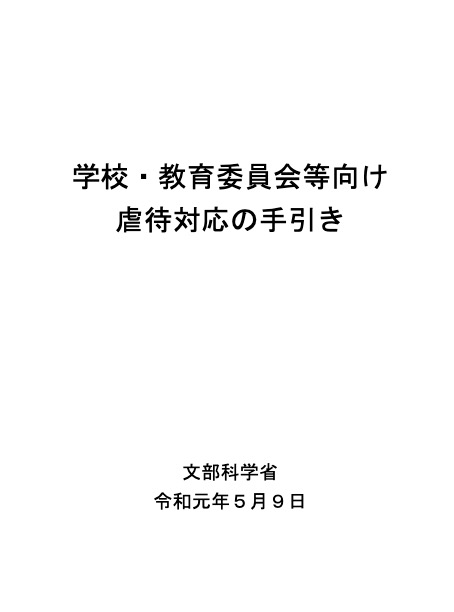
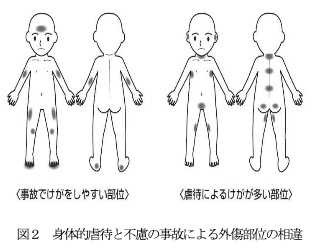 ※
※