ある会議のあと、参加していたメンバーの方から「きゆな先生、少し相談があるのですけど…」とお話がありました。自分の小学生の娘が〈担任の先生の指導が厳しすぎて学校に行くのがイヤだ〉と言っているとのこと。
〈声の大きさ〉〈ノートの書き方〉〈鉛筆の削り方と持ってくる本数〉まで厳しく指導するというのです。

その方は〈教師がいろいろなことを指導しなくてはいけない〉ことに理解を示しながらも、親として「〈学校に行くのを嫌がるまでの指導〉が許されるのか」という強い問題意識を持っている様です。
皆さんはそのことについてどう思いますか?
学校には決まりや目標がたくさんあります。
学年の目標や決まり、学級の目標や決まりもあります。
無いとは思いつつも、もしかするとそういう中に〈鉛筆の本数〉まで明記されているのかもしれません。
そう明記する必然性があったのかどうか分かりませんが、何か特別な事情があったとしましょう。
しかしその指導によって子どもが〈学校に行きたくない〉という状況があるとしたら、一体何のための指導でしょうか?
学校には〈学校に来ない様に〉という措置があります。
〈出席停止〉といいます。
義務教育の範疇で最も重い措置でしょう。
1つは〈学校保健安全法〉に基づいた〈感染症の予防〉のための措置です。
もう1つは「性行不良」であること「他の児童生徒の教育の妨げがある」と認められる場合です、〈学校教育法〉に明記されています。
法的に見ればこれ以外の事情で学校側に子どもを義務教育の場から遠ざける権利はありません。
どの子も教育を受ける権利があるのです。
それは憲法に保証されているからという以前に、現代社会で保証された基本的な人権の一つです。
鉛筆の数が足りないとか、ハンカチを持っていないとか、ノートの書き方が決まりに従っていない、あるいは書き方が乱暴である、そういうことで学校にいくことを拒む子どもが出てくるとしたら、やはりその指導は考え直す必要があると思います。
確かに、教師と子どもの間にはいろいろな行き違いが生じることがありますから、そういう行き違いは、できるだけ早く解消できる様に力を尽くすことが大事でしょう。
しかしそういう対処療法的な動きではなく、たとえば教師が〈たのしい教育〉を進めているなら、つまり子ども達が〈先生の授業ってたのしい〉〈先生の授業が大好きだ〉という様になってきてくれたら、いろいろな行き違いが、実はあまりトラブルにならなくて済むのも事実です。
〈たのしい教育〉に取り組むうちに教師も子ども達が好きになっていきますから、鉛筆の本数とか声の大きさで子どもを傷つけるのではなく、もっとたのしい指導で、子ども達を導いていける様になると思います。
その意味でも、たのしい教育研究所の活動にますます力を注いでいこうと思う今日このごろです。

学校と担任と、どの様に話をすすめて行けばよいのか、悩んでいる方は、一度教育カウンセリングをお申込みください。事例に即した、より解決に向かう提案もできると思います。
また、担任の先生で、どの様に子どもを含めて家族の方たちと話をすすめたら良いのか困っている方もお申込み下さい。長い教師経験とカウンセリング経験、そしてたのしい教育研究所の活動の中で、より確かな方法を一緒に探していきましょう。
一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる活動に参加しませんか。〈簡単な方法〉があります。このリンクのクリックで少しずつ拡がります!

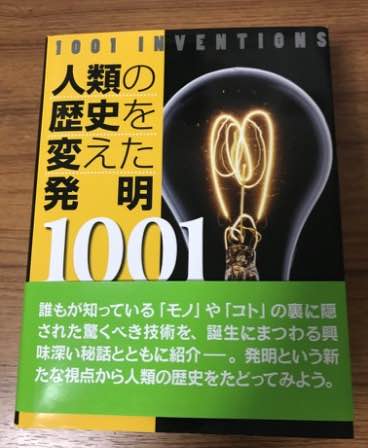
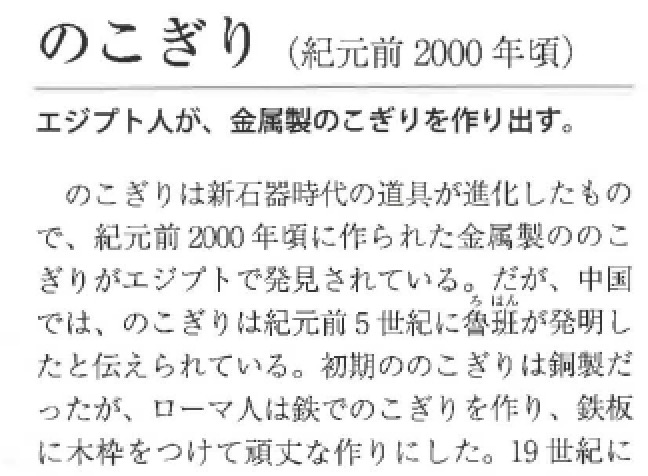
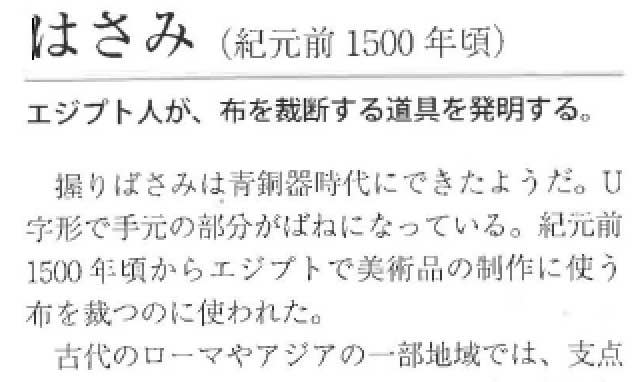
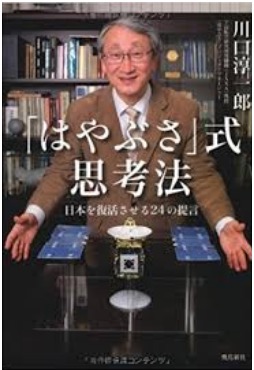

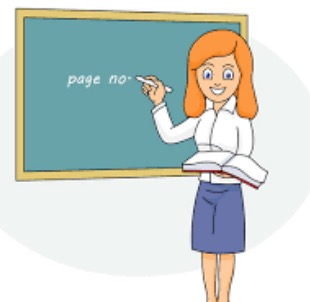 より豊かな、より幸せな社会が育つためには〈教育の力〉が高まっていくことが重要です。そして教育の力の高まりには〈力のある教師〉が増えていく事が必須です。力ある教師は〈子ども達の笑顔〉を広げ〈もっと学びたいという感動〉を伝えることのできる教師だと思うのですが、どうでしょう。
より豊かな、より幸せな社会が育つためには〈教育の力〉が高まっていくことが重要です。そして教育の力の高まりには〈力のある教師〉が増えていく事が必須です。力ある教師は〈子ども達の笑顔〉を広げ〈もっと学びたいという感動〉を伝えることのできる教師だと思うのですが、どうでしょう。