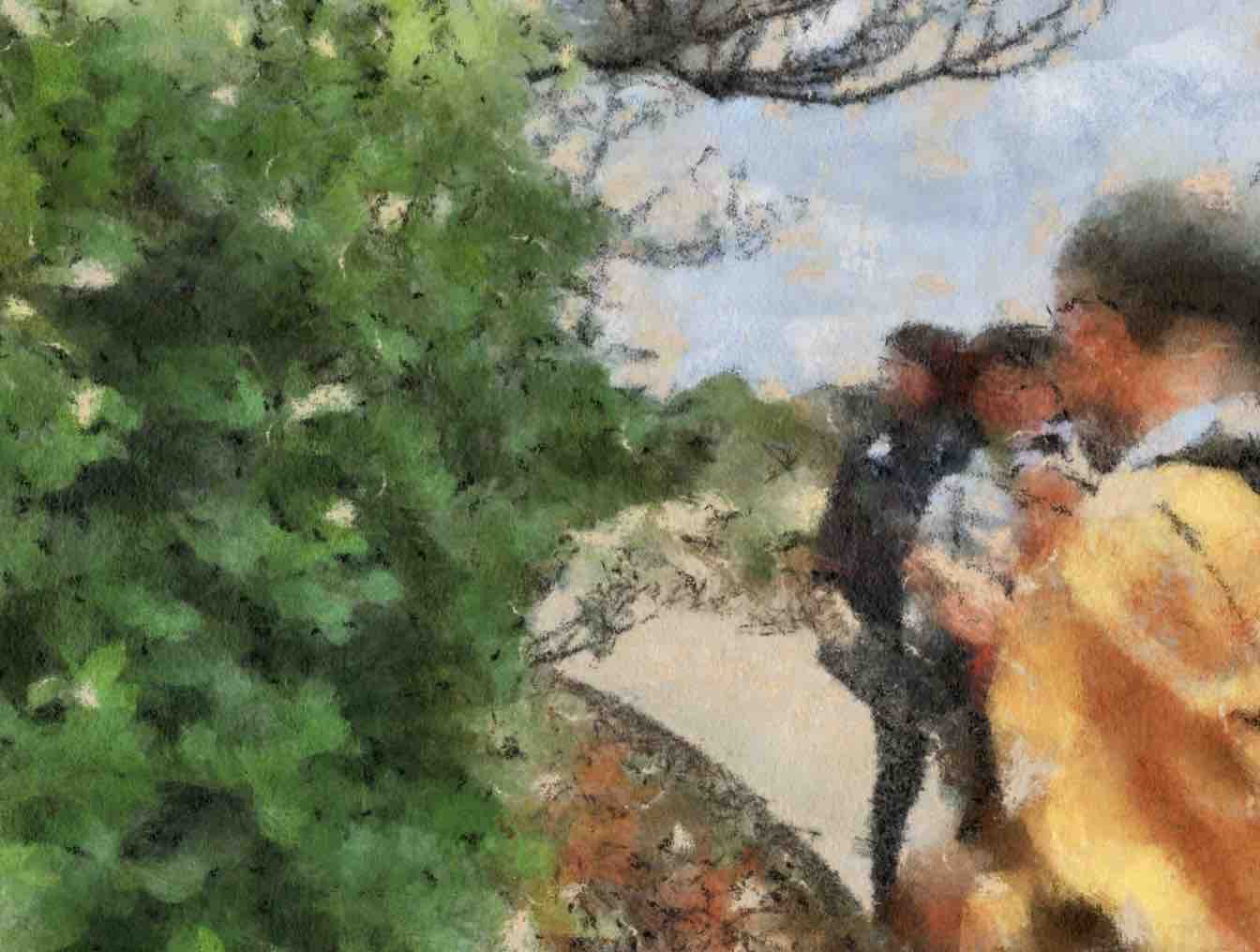学習習慣が大切だという話はいろいろなところで耳にする言葉です。しかし習慣より快感、つまり楽しく学んだ方が勝ちです。このサイトでも数々書いて来ましたが、誰かに止められても止まらないくらい研究にのめり込んだ人たちが〈社会〉を変えるほどの発見や開発をしてきたのです。
日々の学習にしても、7:30から8:30までは家庭学習の時間だという習慣でノートを広げるよりも、家に帰るなり図鑑を開いて調べたくなる様な、止められないくらいの学び方ができれば、その子はずっと高みに上っていくに違いありません。
以前、親子向けの講演会で〈ハヤブサ〉のJAXAプロジェクトマネージャー川口淳一郎さんと二人、舞台に座ったことがありました。どういう話を進めていこうかと事前の打ち合わせの時に共通の話題になったことも、この事と関連した話でした。
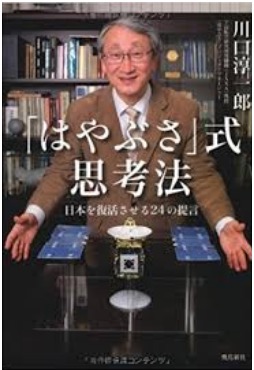
「子どもは〈これが大好きでたまらない〉というものを見つけて全力を尽くし、それでどんどん伸びていくということ、そして親はそれを応援していくということ、それは親にとっても子どもにとっても幸せなことだと思う」
そういう話をする私に呼応して川口さんは
「そうやってどんどん高みに登っていく人が一人出て来るだけで、他の人たちにとっても、ずっとよい。その人物は高いところから遠くまで見渡せる人だから。普通の人たちよりも成果が出せるだけではなく、危険なら危険だと気づくのも早い」
確かにその通りです。
そういう学び方は習慣で身につくのか?
習慣でこそ身につく、と考える人は少ないと思うのですけど、どうでしょうか。
習慣としての学習で身につくこともたくさんあるでしょう。しかし、新しい課題を突破できる程の智慧(ちえ)と元気は、それを学ぶことが大好きでたまらない、という人たちにこそ身につくのだと思うのです。
そういったきっかけを与えてあげるのが〈教師〉であり〈親〉でしょう。
先日、若い先生たちが研究所に学びに来ていた時、アインシュタインが子どもの頃〈じしゃく〉に驚いた話をしたところ興味深かげだったので、浮き上がった磁石を見てもらいました。
これを〈同極同士だから反発するのです〉と無味乾燥に学ぶのではなく、驚きと感動をもって学んでもらえる様な授業をしたいものです。

その日の先生たちの評価・感想の中にこういう一文がありました。
「今日、研究所でたくさんのことを学びましたが、一番ビックリしたのが〈磁石〉です。目の前でじっと見ていると本当にふしぎでなりません」
習慣で学ぶことで身につくこともある。そして、そういう中にあっても、感動として学ぶことを大切にしたい。〈感動〉とともに学ぶこと、つまりそれは〈快感〉として学ぶということです。
たのしい教育研究所は、子ども・大人・おじいちゃんおばあちゃんたちに、そういう笑顔を届ける組織です。興味関心のある方はぜひいろいろな講座、メールマガジン等で学んで頂けたらと思っています。一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる活動に参加しませんか。〈簡単な方法〉があります。このリンクのクリックで少しずつ拡がります!

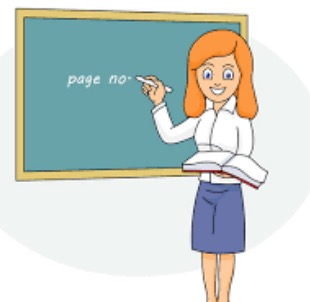 より豊かな、より幸せな社会が育つためには〈教育の力〉が高まっていくことが重要です。そして教育の力の高まりには〈力のある教師〉が増えていく事が必須です。力ある教師は〈子ども達の笑顔〉を広げ〈もっと学びたいという感動〉を伝えることのできる教師だと思うのですが、どうでしょう。
より豊かな、より幸せな社会が育つためには〈教育の力〉が高まっていくことが重要です。そして教育の力の高まりには〈力のある教師〉が増えていく事が必須です。力ある教師は〈子ども達の笑顔〉を広げ〈もっと学びたいという感動〉を伝えることのできる教師だと思うのですが、どうでしょう。