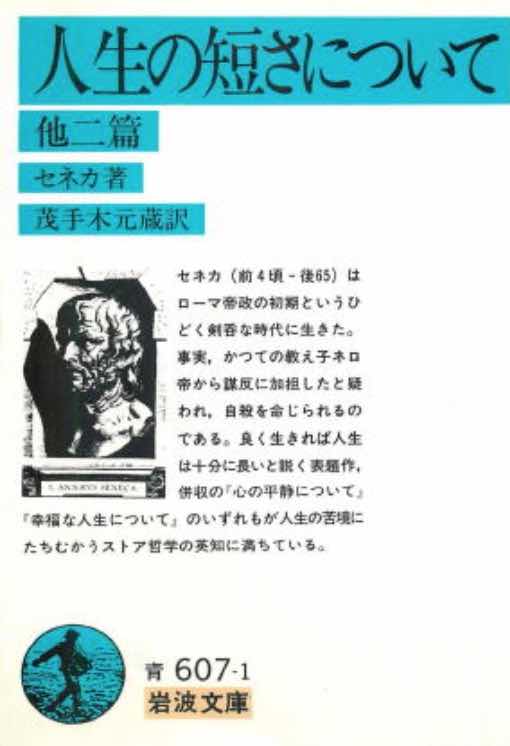以前書いた
野田俊作先生から学んだ〈瞑想〉のトレーニングコースの準備中
についての問い合わせや希望のたよりがいくつも届いています。
やっと準備が整い〈たの研〉冬の講座として12月26日(日曜日)に実施することになりました。
メルマガに書いた文章からピックアップして紹介します。
私いっきゅうのカウンセリングのスタートは亡き野田俊作先生から教えていただいた「アドラー心理学カウンセリング」です。
それまで大学や教員研修の中で数々学んできたロジャーズ派の非指示的カウンセリングやフロイトの精神分析をベースにした子ども理解などには全く満足できず、伊良波さんに紹介された本を頼りに著者の野田先生にコンタクトを取り大阪に何度も足を運びました。
幸い沖縄には私と同じ様にアドラー心理学を学んでいたSさんがいて〈アドラー心理学に基づいた親子関係ワークショップ〉を主催してくれていて、大阪で沖縄でという様に学ぶ時間と密度が増えていきました。
その結果として完成したのが「PEALカウンセリング」です。
今はPEALカウンセラーも出てきて独自にカウンセリングしてくれる様になりました。
瞑想には本来、宗教もスピリチャルも関係ない
これまで殆ど書いてこなかったのですけど、大阪ではカウンセリングと並行して野田俊作先生から瞑想のトレーニングを何度も受けてきました。
野田先生に「きゆなさん、本気でカウンセリングがうまくなりたければ瞑想のコースも並行してとるといいよ。自分の生き方だけでなく、クライエントさんに落ち着いてもらうレッスンとしても大切な技法になるから」と言われたことと、私が長く武道を続けていたことがきっかけです。
武道では修行の前と後、目を閉じて自分の心と向き合う時間を必ずとります。瞑想はそれとの整合性が高いのです。
カウンセラーは試験に合格して免状をいただきました。瞑想には免状はありません、けれど野田先生と二人で食事と杯を交わしながらから直接「瞑想のコースを開催する時の注意」ということで具体的に話をしてもらったことがあります。瞑想についても目をかけていただいたのでしょう。ところが、巷では〈瞑想〉に宗教やスピリチャル的なものをくっつけて伝える人たちが殆どです。霊的なものなど信じない原子論者の私は、それがイヤで、これまでほとんど瞑想について周りの人たちに伝えたことがありません。さわりを呼吸法として合格SVで軽く伝えているくらいです。
また〈たのしさ〉を突破口にして「予想・実験」によっていろいろな課題や困難を解決していく〈たの研〉には瞑想の必要性はあまり多くないと思っているからです。
瞑想の有用性
とはいえこれだけ複雑に絡み合った社会や多様多彩で濃さの異なる価値観を持ち合わせたたくさんの人間同士が付き合っていく中で、瞑想的なものが必要ないかというとさにあらず、大切なものだと思えます。
私自身も大切な判断をする時には瞑想的に心をしずめる時間をとります。
カウンセラーの弟子もできましたから、その人たちにも野田先生が私に残してくれたものを伝えなくてはと考える様になりました。
瞑想という言葉を使わない瞑想
そうやって考えているうちに〈瞑想〉という言葉をつかわず、その時の心の状態を表現する〈心を清ます〉という言葉を使えば良いというアイディアが湧きました。
清んだ状態・澄んだ状態を英語で〈Pure〉といいます、その動詞が〈Purify〉です。しばらくは「Purify=心を澄ます技法」として伝えていこうと思います。
ただしそれは武道と同じで、いくら文章を読んでも身につきません。野田先生から学んだそのままを実技として伝えていく必要があります。
この章で書けるのはそもそもピュリファイ(Purify)の技術でどうして憂鬱な状況や大きな決断を前にして冷静さを欠いている時、落ち着きを取り戻せるのか、ということです。
瞑想は本来スピリチャルも宗教も関係ない
瞑想的な話になりますから、なにやら怪しい話に見えてくるかもしれません、しかし原子論者の私が科学的実験的に思考をすすめてきたものです、安心して読み進めていけば、そこには宗教などは一切関係ないことに気づくでしょう。敬愛するノア・ハラリがこういう趣旨のことを語っています。
「宗教が瞑想を使うから瞑想は宗教的と一体だと思う人がいるかもしれないが、宗教は本によって考えを広めるから本は宗教と一体だという人はいないでしょう。瞑想は宗教と一体ではないのです」
ここまでにしておきましょう。
Purifyはたのしい瞑想技法です、興味のある方はお問い合わせください。
私いっきゅうのスーパーバイズ一回分の費用で3時間半の実技コースを受講できます。
指導:いっきゅう先生(喜友名 一 )
日時:2021年12月26日(日)09:00~12:30
場所:たのしい教育研究 第3ラボ
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!