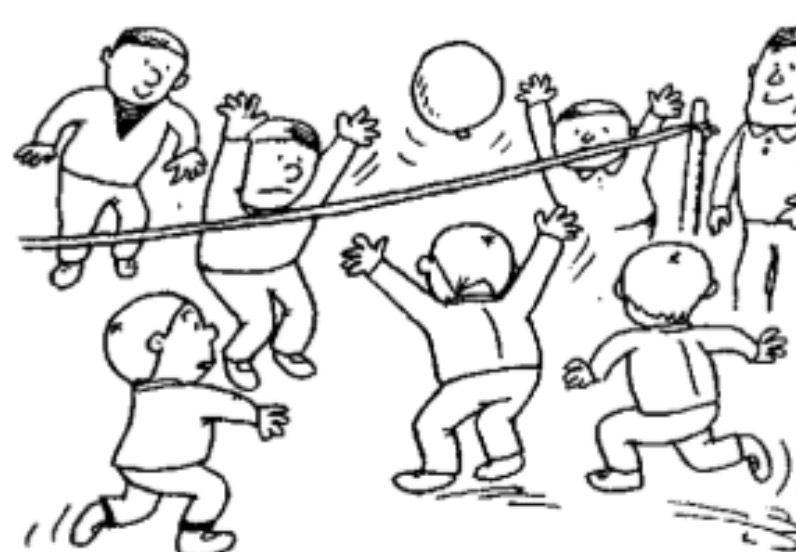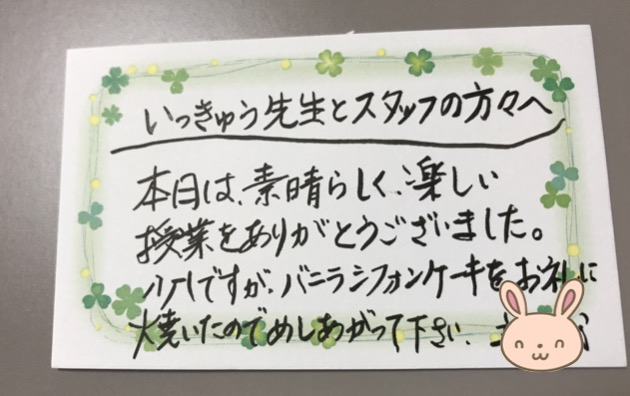たのしい教育研究所は月に5回ほど地域に出てたのしく授業を実施しています。その内容を詳しく知りたいという問い合わせも届き、興味を持ってくださる方たちが次第に増えて来ていることを肌で感じています。
何にしろ〈教育〉を通してたくさんの〈笑顔〉を見ることができるのは幸せです。
研究所ではご要望にお答えしていろいろなメニューを準備しています。このサイトをいろいろ見ていただけると、その幅の広さを感じていただけると思います。ぜひ過去の記事まで目を通してください。
研究所のスタッフはほぼ全員が教員免許を持っていますし、そのメンバーが学校の授業にかけるよりずっと多くの時間をかけ、これまで以上の工夫を加えて作り上げるメニューは毎回ほぼ100%の満足度を得ています。
これは〈体づくりと心ほぐし〉のゲームです。
みんなたのしそうに身体を動かしてくれます。
身体の調子が良く無い子が参加することもあります。そういう時は別なスタッフが個別に対応しています。

〈読み語り 〉も人気です。
いろいろなジャンルから選んでくるので、毎回新鮮で、子ども達もたのしみにしてくれています。
この時間はいろいろなプログラムでエキサイティングにたのしんだ子ども達がリラックスしてくれる時間でもあります。
参加人数によって一つのグループの数に違いは出てきますが、たいていこういう形で、ものづくりをたのしみます。
これも子ども達がとてもたのしみにしてくれていて、今回は人気アニメ〈ワンピース 〉を題材にした不思議カードを作りました。
手品にもなるので、作った後に、家族や友だちに自慢したくなるカードです。
 夏時間は2時間程度、次回からは冬時間で、日の暮れが早まるのにあわせて少し時間を短くします。
夏時間は2時間程度、次回からは冬時間で、日の暮れが早まるのにあわせて少し時間を短くします。
子ども達からは「学校に来てやってほしい」「毎週来てほしい」「もっと長くやってほしい」など嬉しい評価・感想がどんどん寄せられ、一緒に参加してくれる保護者の皆さんからの評価もとても高いものがあります。
費用なども必要ですが、中心になってくださる方の〈熱意 〉がもっとも重要です。興味のある皆さんは気軽るにお問い合わせください。スケジュールにもよりますが、児童館や公民館での1回のみの授業などの要請にもお応えできると思います。みなさんも〈たのしい教育〉を一緒に広げませんか ➡︎ このリンクをクリック