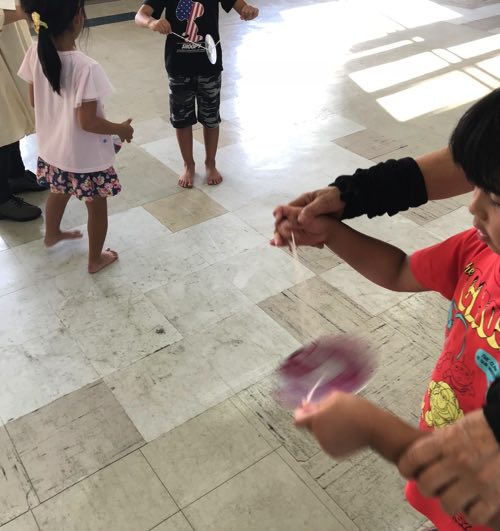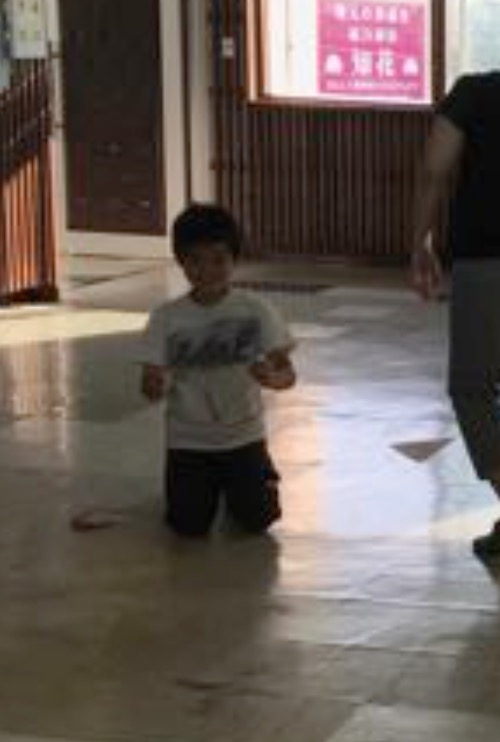たのしい教育研究所で星空の教材づくりをはじめています。
星に詳しい方たちと、時間の合間をぬって、お話を聞き訪ねているのですけど、「天体望遠鏡を貸してあげましょう」と、提供してくれる方がいました。
うれしいことです。
というわけで研究所には今、天体望遠鏡があります。

壁の地球に向けているのがわかるでしょうか。
もちろん近すぎて見えません。
※
みなさんは、最近、星空を眺めたことがあるでしょうか。
どの程度の規模のアンケートだったのか覚えていませんが「〈一年以上前〉という答えがもっとも多かった」という結果だったということを覚えています。
夜空を眺める、それはとても豊かな時間です。
「この広い野原いっぱい咲く星」と表現した歌や「星が森に帰る様に」と詠った歌があります。素晴らしい表現形だと思います。
万葉、飛鳥の歌人、柿本人麻呂は
天の海に 雲の波たち 月の船 星の林に 漕ぎ隠る見ゆ
という歌を残しました。
〈天の海〉とはわたしたちの銀河、天の川のことです。
月の船というのですから、三日月が浮かんでいたのでしょうか。
夜空をたのしむ時に「宇宙は膨張している」とか「ダークマターに満ちている」とか、科学上の新しい知識は必要ありません。
今の様に光の無い時代の私たちの祖先が、危険な夜の状況の中にあっても、星に見とれていた、その感覚はわたしたちのDNAの中にしっかりと刻まれているに違いありません。
こんな感じで、夜空を眺める人たち、家族が少しずつ増えてくるとよいなと思っています。一緒に〈たのしい教育〉を広げませんか→このクリックで〈応援票〉が入ります!