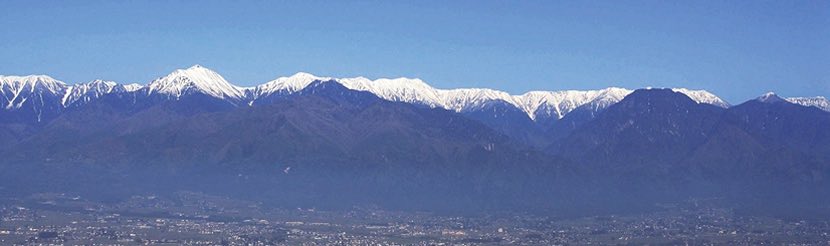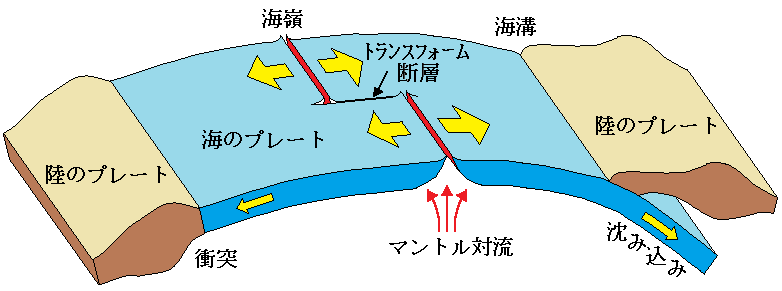前回の〈新聞紙は何回折ることができるか〉を読んだ、うれしい反応がいくつも来ています。今回はその続きとして〈巨大な紙を折る実験〉について書かせていただきます。
前回の実験を見ていただければ、新聞紙は何か力の強いものでプレスすれば8回折ることができる、ということがわかると思います。
新聞紙の二倍の大きさの紙なら9回、さらにその二倍なら10回、という様に〈折る回数〉が増えていくでしょう。
では問題。
〈サッカー場〉くらいある紙なら何回くらい折ることができるでしょう?

ひっかけクイズではありません。
本当にそれくらいのサイズの紙を折っていくとどうなるのか、という問題です。
予想してみましょう。
予想
ア.100回以上
イ.50~100回
ウ.20~50回
エ.10~20回
オ.その他
どうしてそう予想しましたか?
予想を立てると、それが正しくても間違っていても賢くなることができます。そして何より、たのしくなります!
実験結果は、後日UPします! Let’s Enjoy!
この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉を応援することができます !