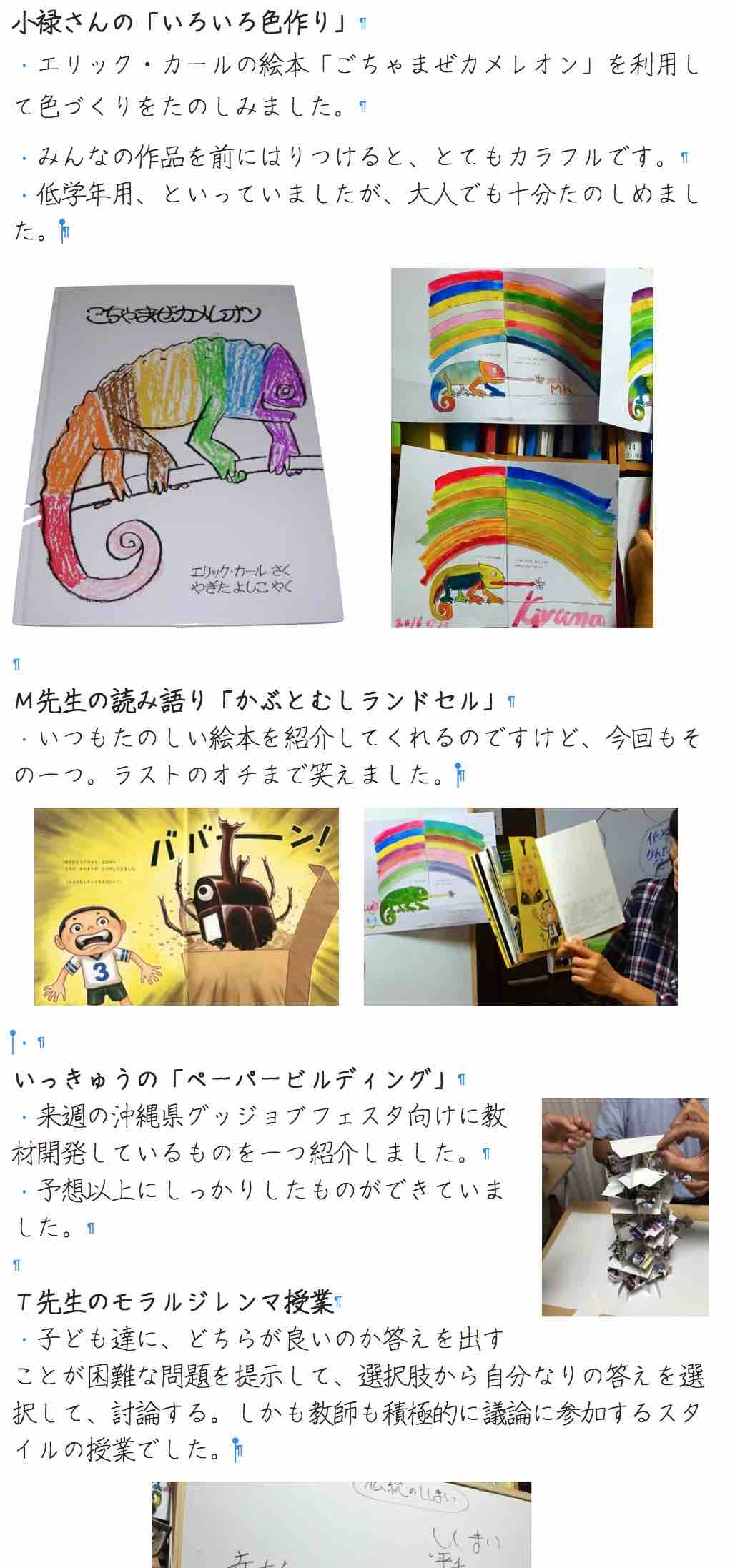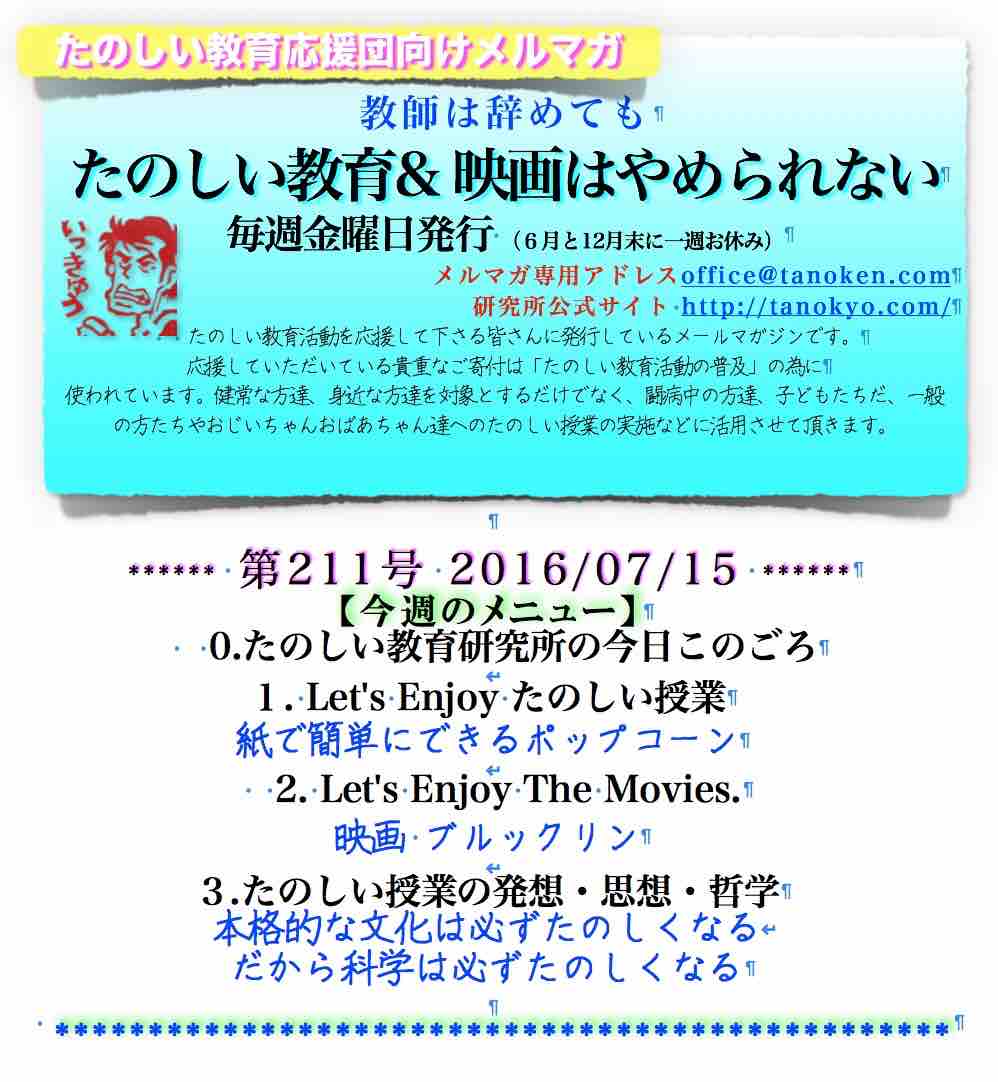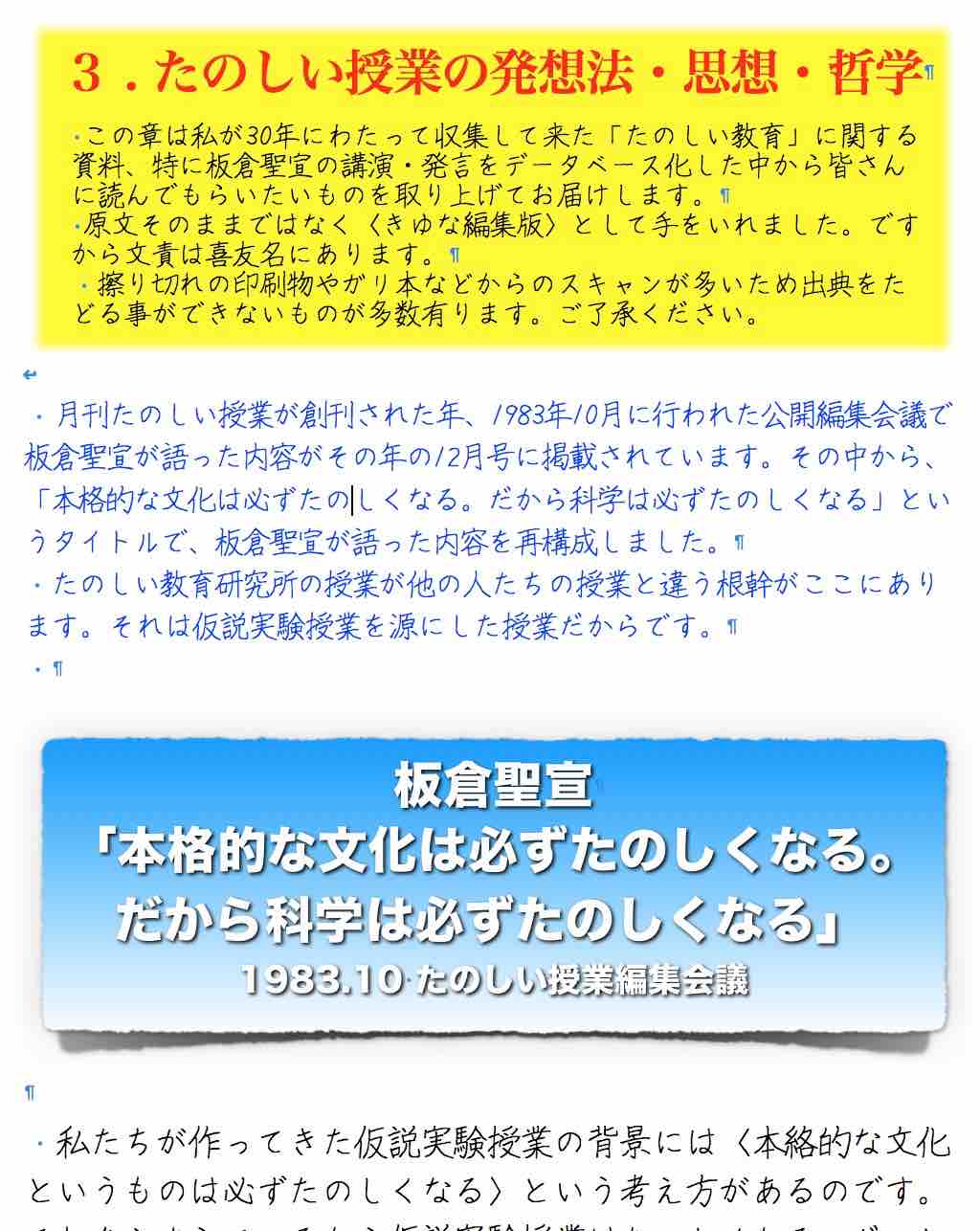たのしい教育研究所メールマガジンには、学校や家庭で簡単に授業できるものを掲載する章があります。
大人気です。
今回は私が小学校で勤めていた時に書いたレポートを掲載しています。
ごく普通の紙で簡単に作るポップコーンです。
子どもたちもとても喜んでくれます。
家で、おやつをつくる時にも重宝します。
一部を掲載します。
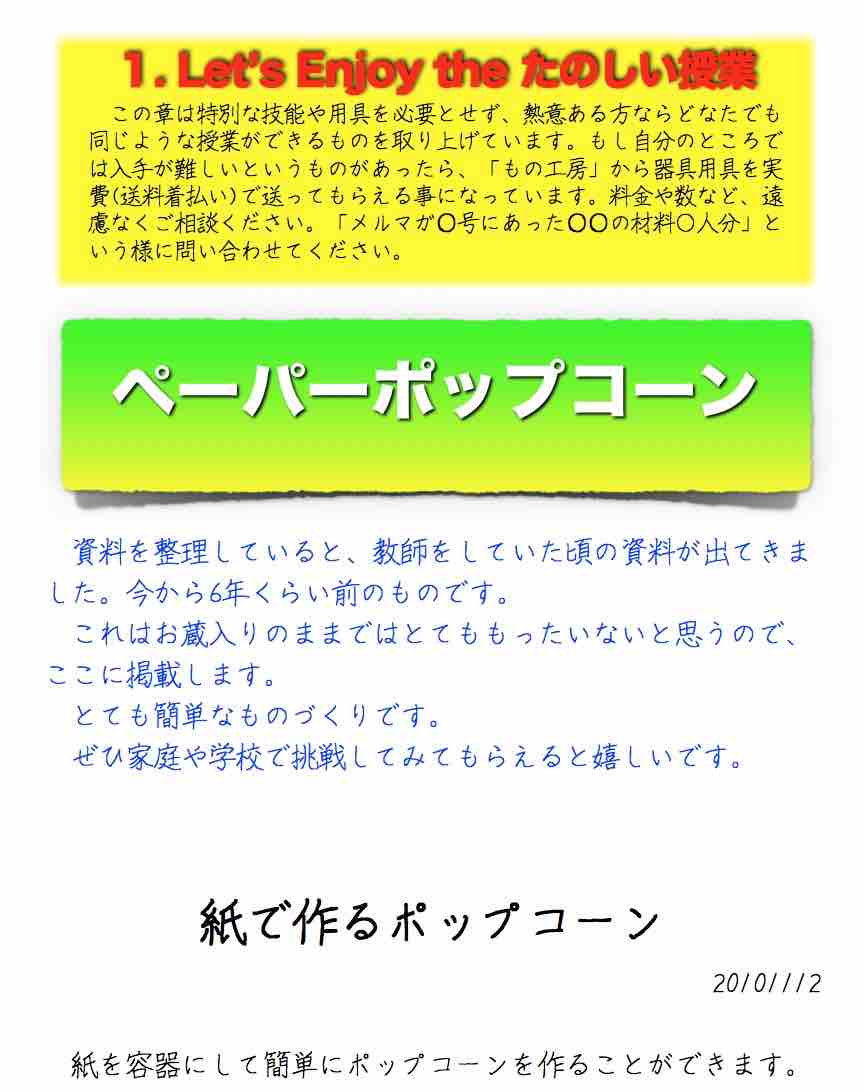
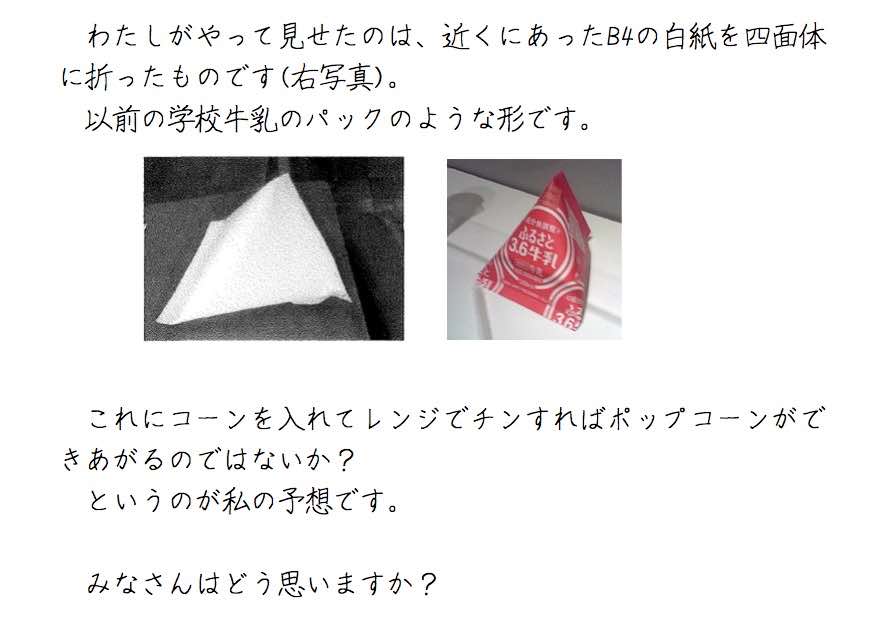
読みたい方は「応援団・サポーター」にご加入ください。
研究所の応援団・サポート月額は800円、年まとめとして9600円で振込んでいただいています。貴重な拠出金を何倍にもして、日本中に「たのしい教育」を普及させる活動に利用させていただきます。
申し込み ➡︎ こちら