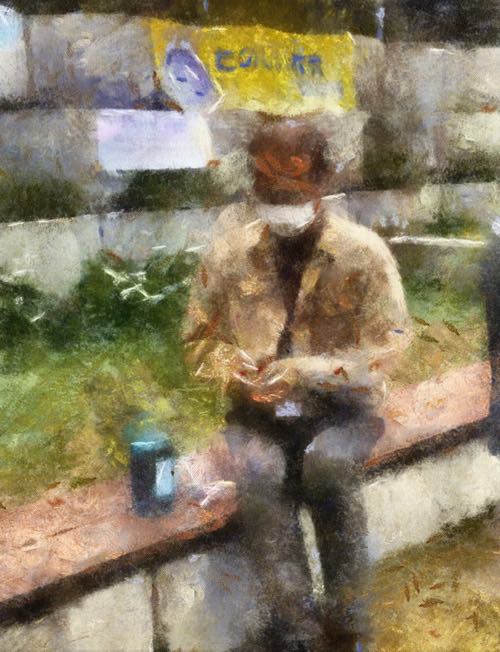たのしい教育研究所に張ってある干支のポスターにいろいろな人たちが今年の願い(目標)を書いています。
ほぼ80%くらいの達成率がある不思議なポスターです。

そのポスターに「猛牛! 人生を変える!!」と書いたKくんがいます。
昨日その嬉しい報告をしにきてくれました。
個人情報なので具体的には書けませんが、早くもその願い通り猛牛のごとく前に進み、人生を大きく変えました、おめでとう。

たのしい教育研究所はたくさんの笑顔に囲まれています。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!