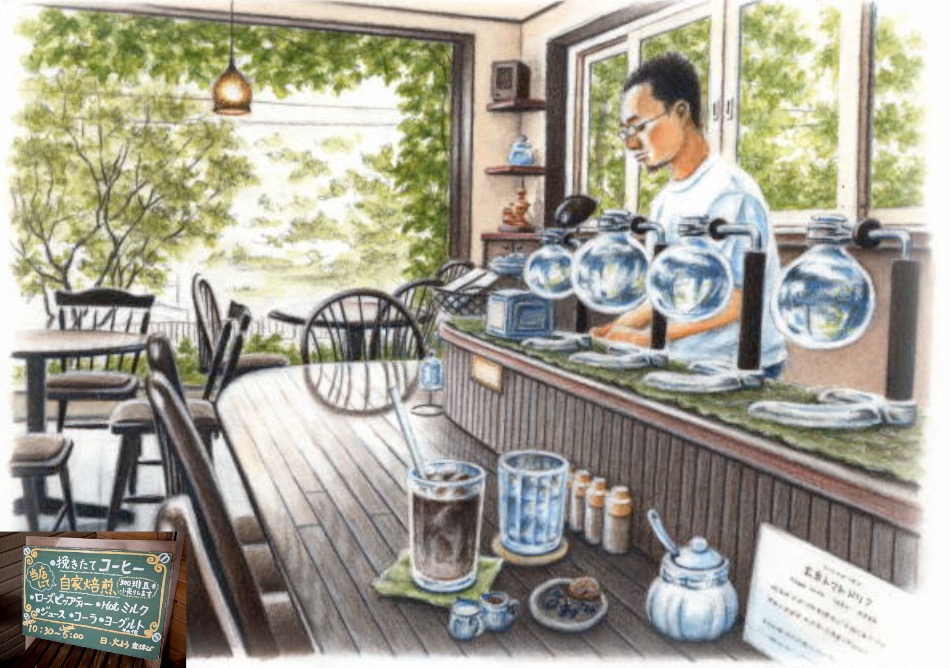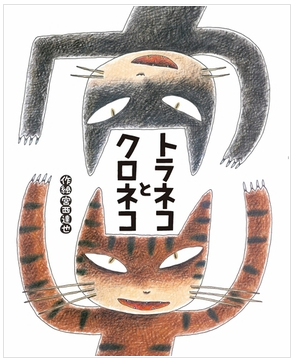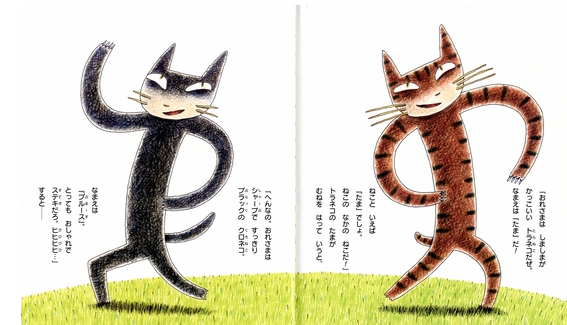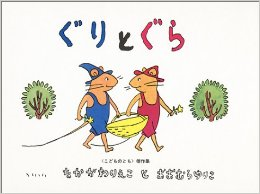前回、教員採用試験の特訓コースで取り上げた「コールバーグ」について書きます。彼は理論家であり実践家です。

「一問入魂」で触れた彼の「道徳性発達理論」も、とても興味深いものがあります。
webサイトから引用します。下線や強調は、きゆな です
http://www.eonet.ne.jp/~like-a-flowing-r/psychology1.htm
コールバーグの道徳性発達理論
道徳的価値観というものはどのようにして獲得されるのでしょうか?
ローレンス・コールバーグは、人は道徳的価値観を思考や推論を通して学んでゆくものなのだと考えました。そして、道徳性の発達を研究するために、コールバーグは様々な年齢の子どもたちにいろいろなジレンマ状態を提示しました。次のお話は彼が子どもたちに用いた道徳的ジレンマの一つです。
ある女性が癌のために死に瀕していました。もし彼女を助けられるとすれば、それはある薬を使った場合だけです。ある薬剤師がその薬を開発したのですが、彼はその薬に、薬の開発費用の十倍もの値段をつけました。この癌に苦しんでいる女性の夫は1,000ドルしかお金を準備できなかったのですが、薬剤師は2,000ドルを要求しました。夫は薬剤師にもっと薬を安く売ってほしい、あるいは後払いにしてほしいと頼んだのですが、薬剤師の答えはNoでした。失望した夫は、妻の命を助けるために、薬剤師の店に押し入って例の薬を盗んだのでした。
彼はどうすべきだったのでしょうか?彼の行動は正しかったのでしょうか?それとも間違っていたのでしょうか?そして、それはどのような理由からなのでしょうか?
子どもたちは「この夫はどうすべきだったか?」と質問されます。コールバーグは子どもたちの答えとその理由を分類し、道徳性の発達には三つの段階があると考えるようになりました。それぞれの段階は、夫の行動についての正否ではなく、その理由に基づいています。
前慣習的段階では、道徳観念は行動によってもたらされる結果(罰や報酬など)に基づいています。慣習的段階では、他人を喜ばせたいという思いや規則・法律に従うことが道徳観念の基準になります。そして脱慣習的段階では、個人的な道徳原理に基づいた道徳観念を持つようになります。コールバーグはこの三つの段階をさらに細分化し、全部で六つの道徳性発達段階を提唱しています。
------引用終わり
彼は、その理論を実際に授業プランにして提案しています。
それが「モラル・ジレンマ教材」です。
日本でも一時かなりブームになった「マイケル・サンデルの白熱教室」がありましたが、それはコールバーグのモラルジレンマを講演風にアレンジしたものです。
わたしも「たのしい道徳」ということで何度か「モラルジレンマ教材」をとりあげたことがあります。
もりあがりますよ(^^
今度の「たのCafe」で、コールバーグの理論をもとにしたモラルジレンマ教材を取り上げて、実際に授業してみます。
時間の都合のつく方はぜひ参加するといいですよ。
申し込み、必需です。
tanokyou☆gmail.com ☆を@に