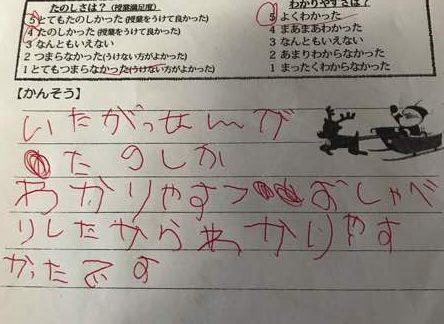スポーツたのCafeの準備運動で紹介した〈昆虫太極拳:こんちゅうたいきょくけん〉が人気です。

スポcafeを受講した先生たちが、さっそくいろいろな学校で子ども達とたのしんでいる様子がRIDE( ライド:たのしい教育研究所 )に届いています。
うれしいことです。


昆虫太極拳は〈ミツル&りょうた〉作で、四つの虫のポーズをとってたのしみます。
この四つのポーズです。
カマキリ

カメムシ
ダンゴムシ 
バッタ

RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )では、その原版でたのしんであと、グループワークでたのしめるアレンンジを加えてさらにもりあがりました。
ところである先生の学級でたのしんだところ、Aくんが「あれれ、先生このダンス、おかしなところがある」といったのだそうです。
みなさんは、このダンスのおかしなところに気がつきましたか?
実際に踊らなくても、この記事の中からそれがはっきりわかるのですけど、どうでしょうか。
研究所のスタッフもダンスの流れでたのしんでいてわからないかったのですけど、中途半端におかしいのではなく決定的におかしいのですよ。
この〈昆虫太極拳〉の作者のサイトや、それをいろいろなところでたのしんでいる人たちの記事を読んでみても、まだ誰も気づいていないようですから、Aくんは表彰状ものだと思います。
謎解きは次回のおたのしみに。
毎日たのしいことに全力投球 RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )です。
みまさんの応援クリックが元気のタネです。一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる〈簡単な方法〉があります。ここのクリックでブログ評価に一票入ります!