インクルーシブ教育・インクルーシブ体育の反響が続いています。ご期待に応えて今回も具体的な内容を紹介しましょう。
これは〈スポーツ色カルタ〉で汗を流している一コマです。
〈裏表で色の違うカード〉を自分のチームの色にひっくり返していくシンプルなゲームです。それを人数やコートの広さ、カードの枚数、時間などをRIDE( ライド:たのしい教育研究所 )のいろいろな先生たちが実験して、授業で利用できるように教材化したのが「スポーツ色カルタ」です。
顔がほぼ判別できない写真がいろいろあるので実際の写真も交えて紹介してみましょう。コート内に三色のカードがちりばめられています。

はじめのうち、立ち上がって見ている子ども達も、すぐに本気になって裏返しはじめます。

 実際にやってみると、まるで反復横とびの様に素早く動き回る子や、二枚一緒に裏返す子など、どんどん動きが進歩していくのがわかると思います。
実際にやってみると、まるで反復横とびの様に素早く動き回る子や、二枚一緒に裏返す子など、どんどん動きが進歩していくのがわかると思います。
大人の動きもなかなかのものです。
この二枚の写真は連続で撮ったものですけど、動きの素早さがわかるのではないでしょうか。


RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )の講座ではたいてい教材とセットで提供しています。
この〈スポーツ色カルタ〉のカードも参加者にプレゼントしました。もちろんみんなとても喜んでくれていました。
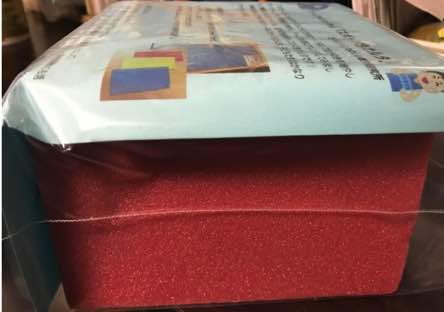
夕食後にいただいた教材を家族でたのしみました、というメールも届いています。簡単&画期的教材ですから、きっと学級でさっそく利用している人たちも多いでしょう。

そうそう、ゲームがかなりもりあがり、子ども達から「大人と子どもで対戦したい!」という提案がありました。
もちろん大人チームも受けて立つ、ということになり、休憩時間を工夫して対戦することになりました。
スポーツ色カルタは二チームでも対戦可能です。
参加者の比率は〈大人:子ども=5:3〉くらいです。
対戦の時には予想してもらうと、大人は圧倒的に大人が勝つ、子どもは自分達が勝つと思っています。
実際に勝負してみると、衝撃的な結果となりました。ここで書くのも忍びない程なので、あえてどのチームが勝ったか書きません。
気になる方はぜひ自分たちでトライしてみてください。
学校の先生 VS ◇年生チーム
◯◯家の大人 VS 子どもチーム
など、すぐに結果がわかると思います。
他にも〈RIDE(ライド)式吹き矢大会〉など、いろいろなメニューでたのしみました。これは吹き矢大会の一コマ、もちろん体育で取り上げるのもピッタリです。

吹き矢は外側の筋肉ではなく肺の筋肉を鍛えます。
肺の活動が活発になりますから、喘息にも良いのだというので〈全日本健康吹き矢協会〉という組織もできているくらいです。ちなみに沖縄にも支部がある様ですから、時間ができたら訪ねてみようと思っています。
毎日たのしいことに全力投球 RIDE(ライド)です。みなさんの応援クリックが賢い元気を育てます⇨この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆



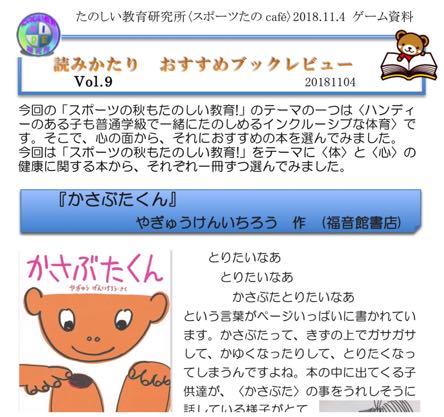
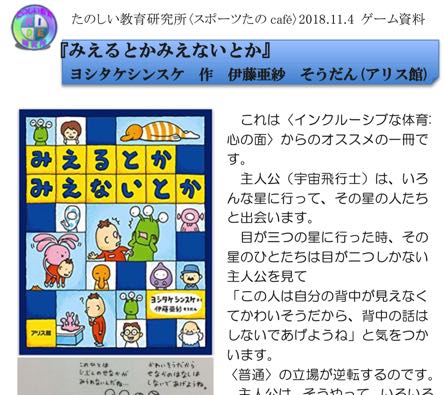





 ラジオ体操の様に〈全体美〉に時間をかける必要はありません。
ラジオ体操の様に〈全体美〉に時間をかける必要はありません。 大人も子どももみんなかわいくて、たのしくストレッチできます。
大人も子どももみんなかわいくて、たのしくストレッチできます。



