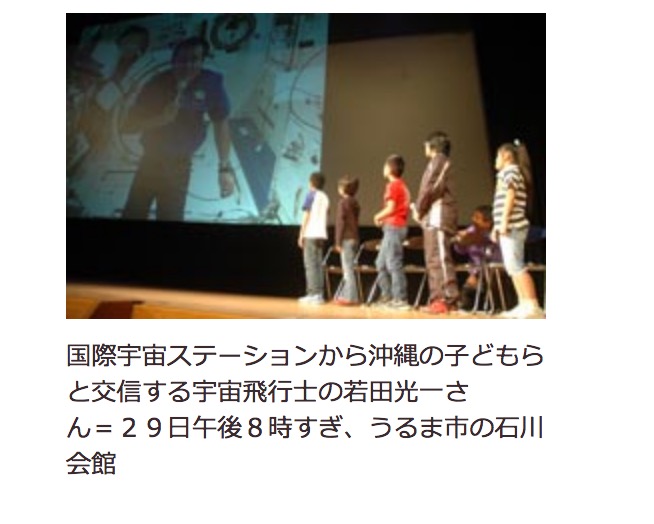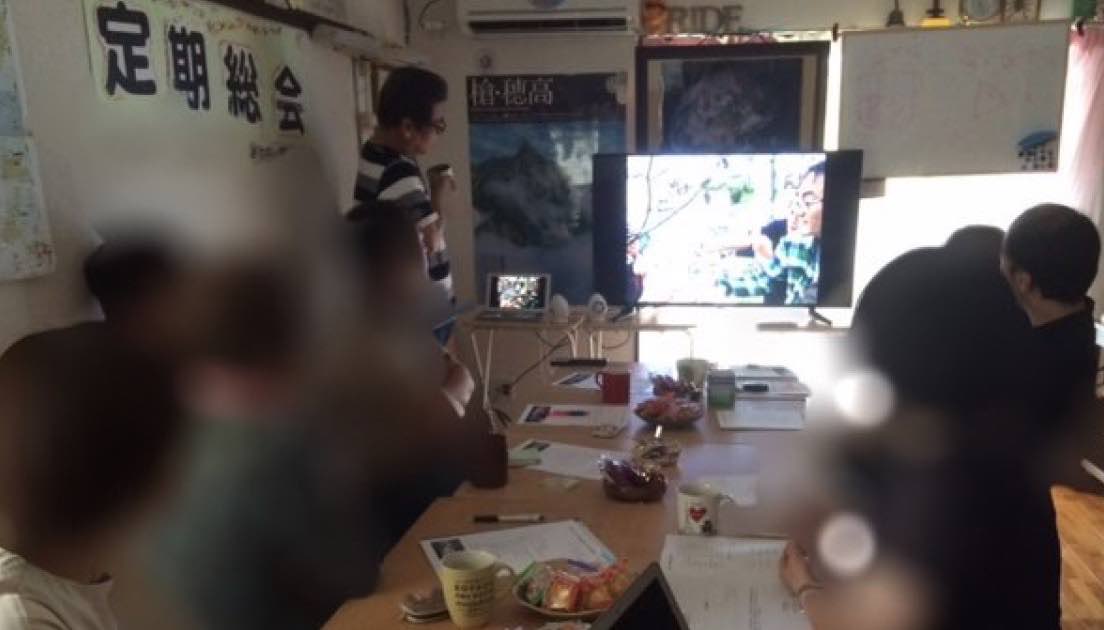つい最近のこと「喜友名先生の活動のことがずっと気になっていて、沖縄に戻って落ち着いたのでやっと連絡致しました」という元気な声で電話をかけてくれた方がいます。琉球放送の上村さんです。
上村さんとのつきあいは10年前に遡ります。
その頃は私もまだ現職の教師で、仲間たちとすすめてきた「たのしい授業in沖縄」がどんどんグレードアップしていきました。
わたしがNASAで開催された宇宙探査教育者会議で授業させていただいた時に知り合うことができた宇宙博士の的川泰信先生(今でもたのしい教育研究所の応援団長をしてくださっています)とのジョイント授業、固体燃料ロケットの森田泰弘先生とのジョイント授業、宇宙飛行士の古川聡さんとのジョイント授業という様に、超一流の方達と一緒に沖縄の親子向けの授業を推進していくことになりました。
そうしてとうとう〈宇宙ステーションにいる若田光一さんと交信授業をする〉というところまできました。JAXAとNASAが全面協力してくれて沖縄と宇宙とを結んで授業するわけです。
それを知ったいろいろなメディアから数々のアプローチがありました。当時の様子は、たくさんのテレビや新聞で取り上げてくれました⇨こちら
そういう中で「喜友名先生をテーマに番組を作りたい」と熱心にアプローチして下さったのが琉球放送の上村さんでした。
〈ひとりの教師の夢が宇宙への扉をひらいた〉というタイトルで番組を作成したいというのです。
具体的な予算案もできていて、会議も重なり、積極的に話がすんんでいたのですが、〈なるべく目立ちたくない症候群〉の私は、その時の上村さんの熱き思いをどの程度、どの様に受け止めていけばよいのかわからず、アメリカのNASAの宇宙ステーション運行スケジュールで、期日の確定が先延ばしになっているうちに、上村さんは突然、県外で仕事をすることになりました。
上村さんは、その時のことが十年間ずっと気になっていて、やっと沖縄に戻って落ち着いた今、私に電話してくれたのが冒頭の言葉です。
嬉しいことです。
10年を経て、お互いいろいろな役職を経験する様になった今、沖縄の未来、宇宙への魅力、そういった、あの頃の熱い思いが変わらずにいるお互いを確認する時間になりました。
たのしい教育で沖縄が日本一元気でたのしい県になり、世界に発信できる教育を推進する、という私の活動は、上村さんが放送という場で〈沖縄の魅力を県外、国外に発信する〉ことをテーマに推進して来た取り組みと重なるところがとても大きく、放送の世界で志を同じくする方がいることに、とても嬉しく感じたひと時になりました。
何より、そして10年経った今も、お互いがとても生き生きと活動していることがとても嬉しく、途切れることなくたくさんのことを語り合っていました。上村さんからの具体的な番組の提案もありましたが、私の多忙さと、若い実力ある教師を育てるワークショップへのウェイトのかけ具合、そして〈めだちたくない症候群〉の症状との兼ね合いもあり、すこしゆっくりと語り合っていきましょう、ということになりました。
実現できるできないは別にして、放送局で上村さんの様な夢と元気を伴った方がいることがとても嬉しくてなりません。きっと上村さんの周りにも、そういう方達がいるのだと思っています。
上村さんが「顔を出してもよいです」というので、熱く語りあった時のワンショットを掲げます。書類なども入っているので水彩画調にしておきます。
 1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!
1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!