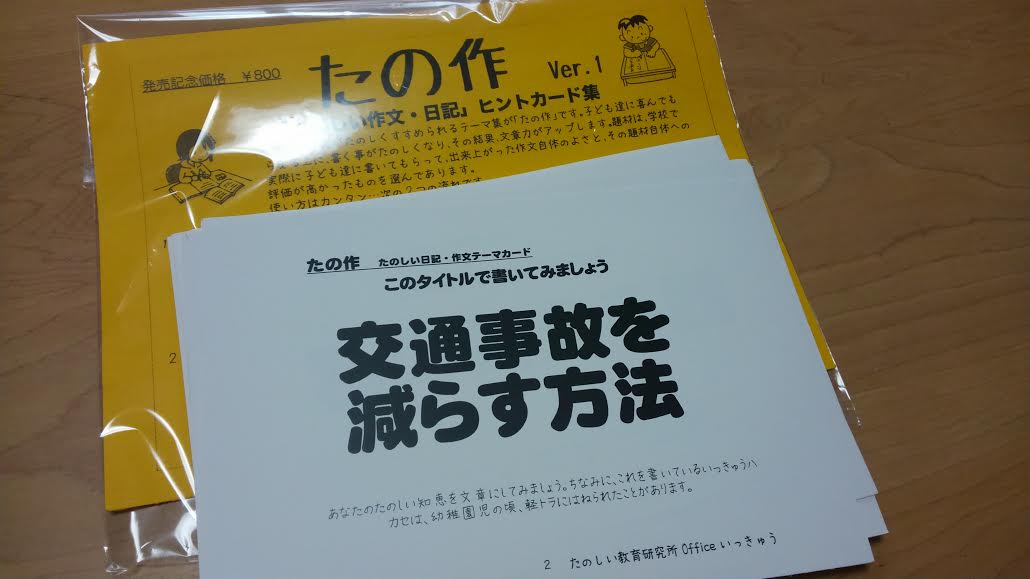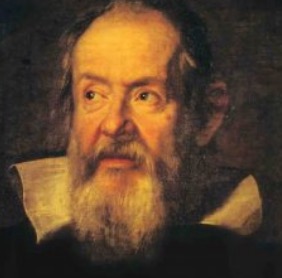先日、先生たちに向けての連続コースが修了した途端〈歯〉が痛くなりました。 コースに集中していて、自分の身体の痛みを感じなかったのでしょう。空手の試合終わってから骨の痛みを感じて、病院に行くと、骨折していたということもありました。格技を経験している人間なら経験した人もいると思います。
コースに集中していて、自分の身体の痛みを感じなかったのでしょう。空手の試合終わってから骨の痛みを感じて、病院に行くと、骨折していたということもありました。格技を経験している人間なら経験した人もいると思います。
〈痛み〉といえば、小学校で理科を教えていた頃のこと、休み時間に六年生とおしゃべりしている時「痛みなんかなければいいのにね、先生」という子がいました。ケガをしてずいぶん痛い思いをした様です。
「そうそう」と頷く子も多かったので、わたしが〈痛みがなくなったら、とんでもないことになるシリーズ〉ということでいろいろな話をしました。
・火傷してもわからない
・血が出ていてもわからない
・コンクリートブロックを殴っても痛くないから手加減せず、自分の手がボロボロになってしまうetc.
どんどん怖い話になっていったので途中で終わり、今度はみんなで「痛みがあってよかったシリーズ」になりました。
・画ビョウにちょっとささったくらいですむ
・熱いヤカンを触る前に、熱を感じて触らずにすむ
・相手の痛みがわかるから優しくなる
・「いたいー」っていうと周りの人たちが優しくしてくれる
etc.
話は変わりますが、たのしさくぶん指導〈たの作〉は大好評で、そろそろ「続 たの作」をまとめようという話が出ています。
続編のテーマもたくさん揃えてあります。〈痛み〉に関するものもその中にいくつか入っています。たとえば・・・
○ 今までで一番痛かった思い出について書いてみましょう
○ 痛くて得した思い出について書いてみよう
○ もしも痛みがなくなったらどうなる?
○ 痛みを消す方法
もちろん、テーマも大事ですけど、子ども達が書いてみたくなる様に投げかける言葉も大事です。それらを揃えて、年度内には新たな一冊ができるとおもいます。ご期待ください。こちらの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか-いいねクリック=人気ブログ!-