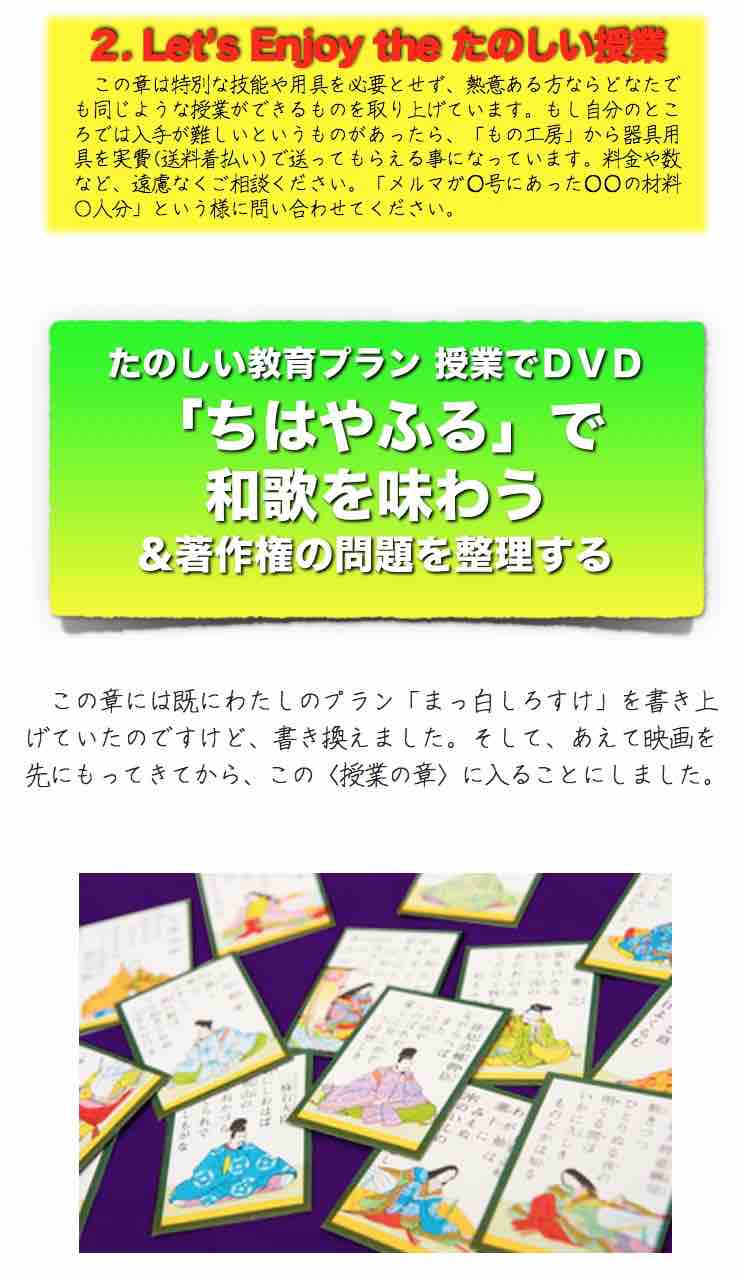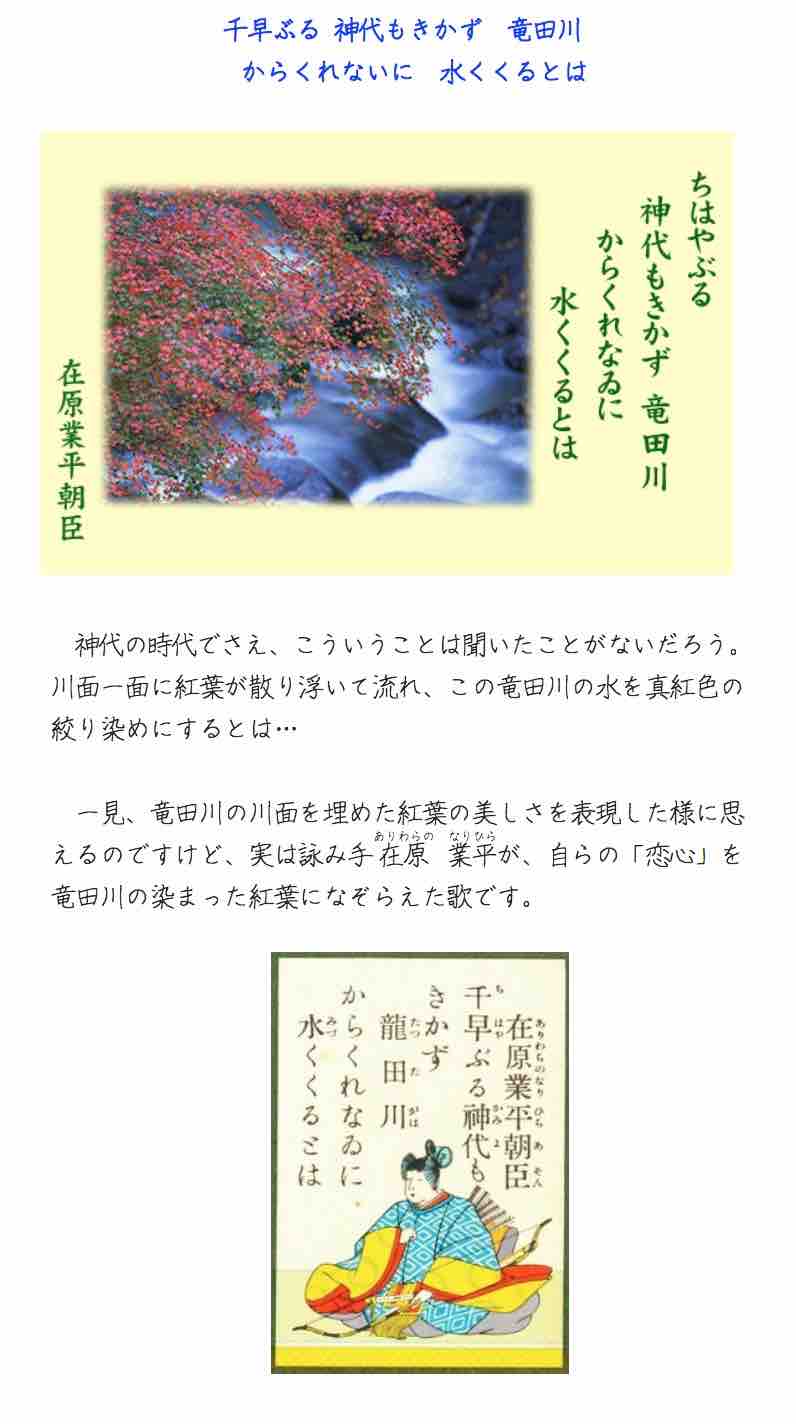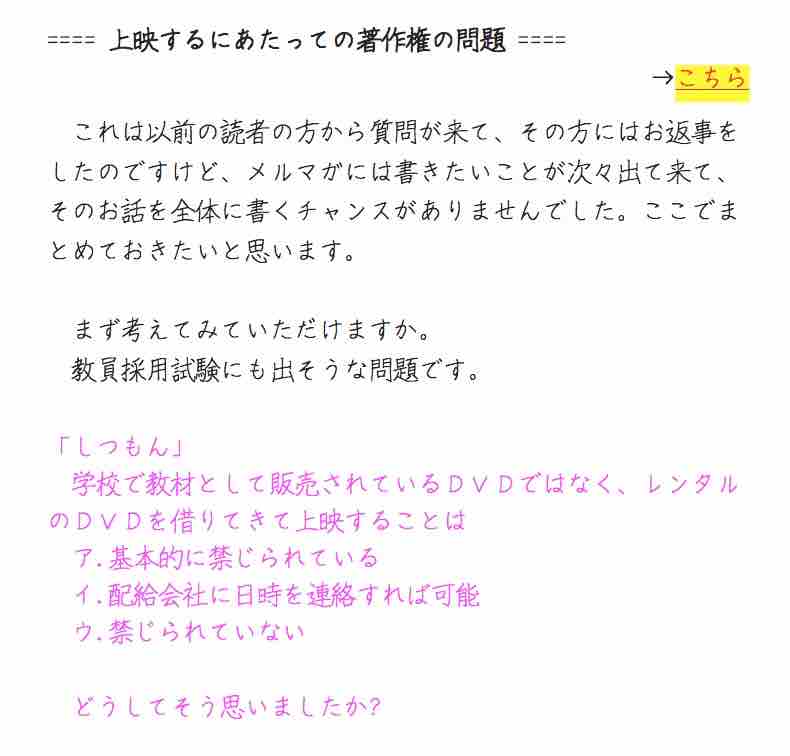研究所のスプーンは木製のものがほとんどで、普通の金属のスプーンはほとんど利用していません。あまっている金属のスプーンを見ていた時、ふと思い立って、やじろべえができないかためしてみました。
やじろべえというと、たとえばこういう様にバランスをとって立っているおもちゃです。
スプーンはカレー用の普通のスプーンです。
さて、どうやってやじろべえにしましょう?
単純に右と左をカーブにして作る、というのではなく、少し工夫してみました。
まず重心(重さの真ん中)を確かめてから、そこを中心にして右、左をペンチ2つでグイッグイッといくつかの折れ目を作ってまげたのです。
近くに「レンズの魅力」で利用する電球型の入れ物(100均ダイソー)があったので、それに乗っけると・・・
やじろべえになっていました。
飾り・オーナメントとしても使えそうです。
ご覧ください。
どこをどのように曲げるかなどについては、もっと何本ものスプーンで確かめて、いずれこのサイトで紹介したいと思います。
図工でも利用できないかと考えています。
たのしいこといっぱいの「たのしい教育研究所」
「沖縄県 教育」が大きなテーマです!