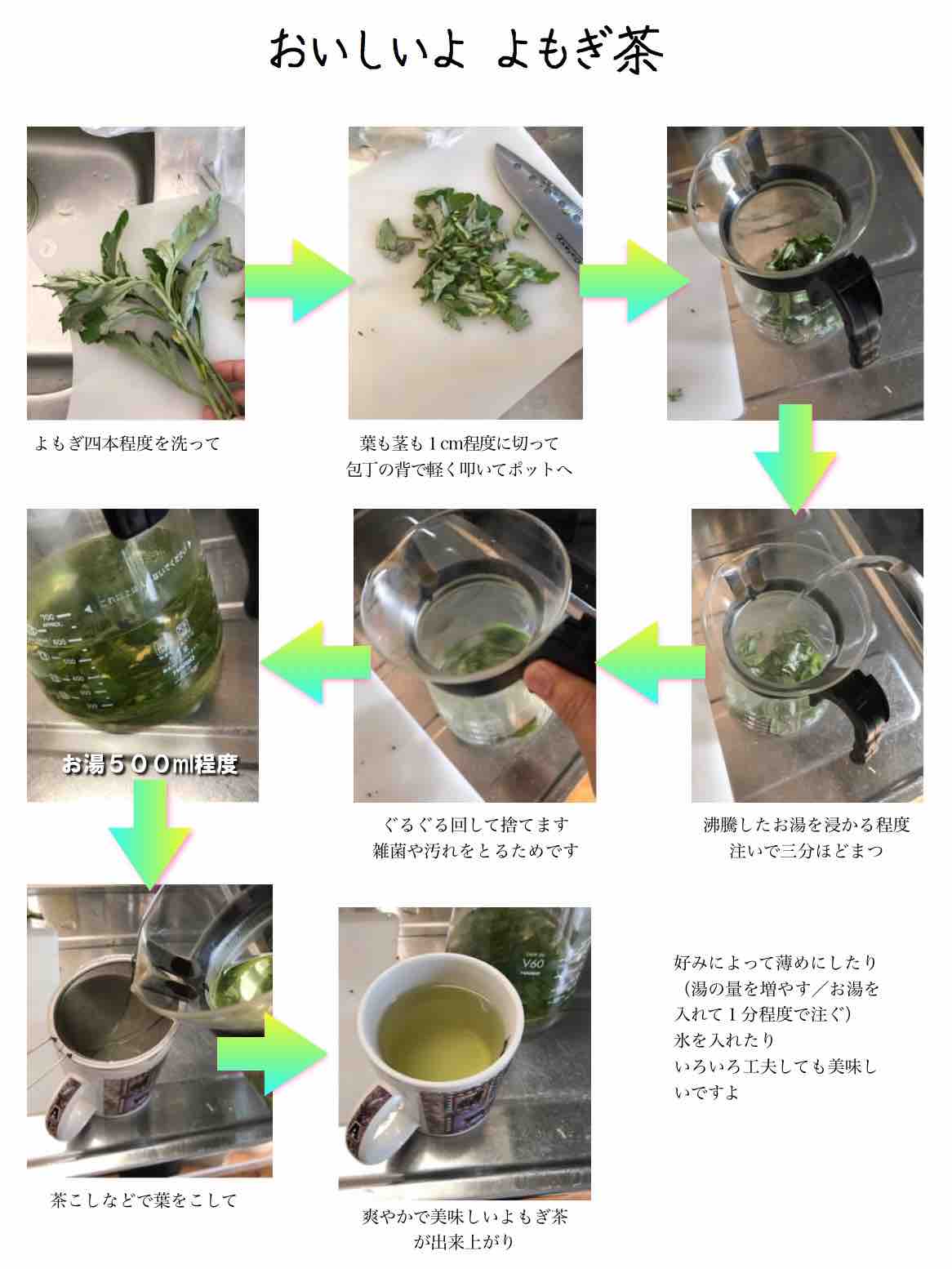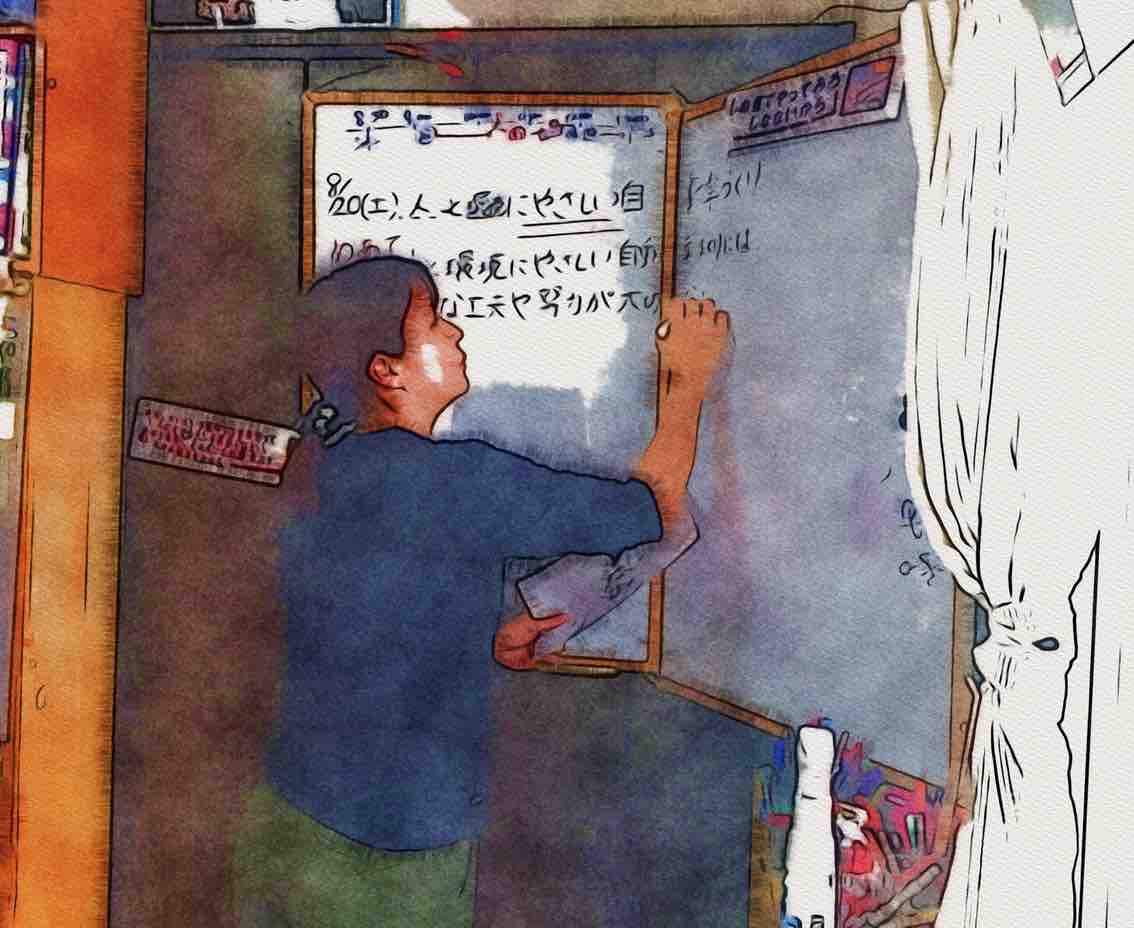よもぎがたくさんあったので、よもぎ茶にしたところ、かんたんな上にとてもおいしかったので、研究所に来てくれる人たちに飲んでもらったら、これが大好評でした。
研究所のテーマの一つが「たのしいアウト・ドア=たのしい環境教育」です。
よもぎ餅などを食べたり、沖縄の伝統的な料理「フーチバー・ジューシー(よもぎ おじや)」などで味わっている子ども達もいるので、もしかすると、大人だけでなく子ども達も「意外といけるね」と言ってくれるかもしれません。
興味のある方は、ためしてみませんか。
つくり方をかんたんにまとめてみました。
子ども達に味わってもらうなら、薄めがよいでしょう。
よもぎは、わたしの授業プラン「アウト・ドア入門」で、天ぷらにしても大好評の食材です。しかも日本中どこでも手に入る、といってよいほどいろいろなところに生えています。研究所の近くの公園にも生えていますし、立山の山嶺にも生えていました。
キャンプのときの食材にもうってつけのすぐれものです。
お茶にしても美味しいので、さらにわたしの評価が高くなりました。
スタッフが調べたところによると、健康にも良いということで、ガンを予防するとかいろいろな効能があるようですけど、そこらあたりは、わたしはよくわかりません。
たのしいことがいっぱいの
「たのしい教育研究所」です