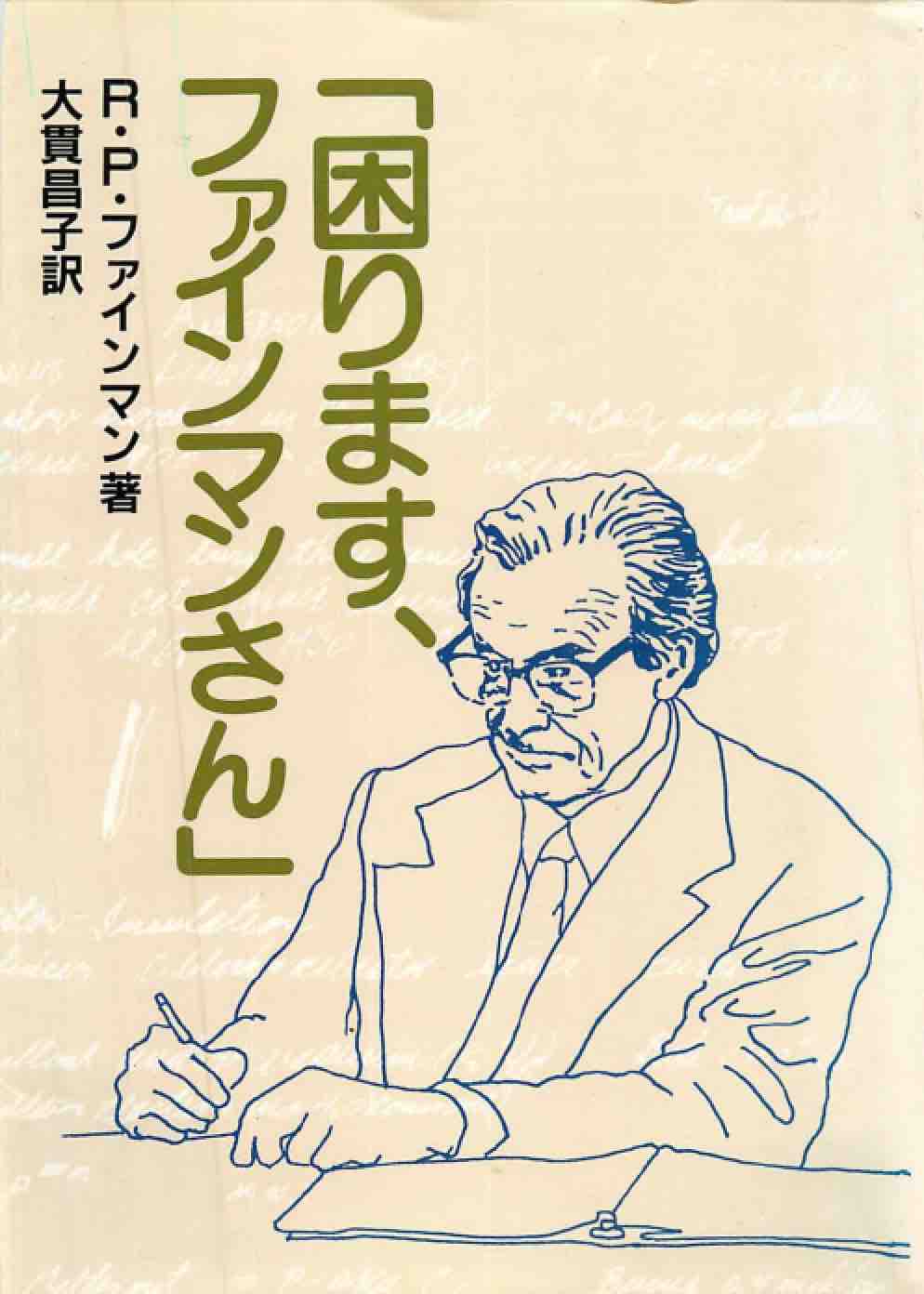LEAPカウンセリング入門「自分の行動は自分の選択。その行動の責任を受け入れることで成長する」
前段の「科学的とはどういうことか」の続きです。
まず、カウンセリングに科学的な手法が必要なのか?
ということをお話ししたかったので、長々と書かせていただきました。
わたしがLEAPカウンセリングを開発する際に重視したのが「科学的でありうるか」ということでした。
科学的だということは、「予想・仮説⇨実験・確かめ」を経てすすむので、それが一回だけの現象に終わらず、周りの人たちも再現できるのです。
もちろん悩みや課題は人それぞれ違っていますから、同じようにすすむカウンセリングというものは考えられません。それは、海の波がまったく同じ動きで、同じ形で押し寄せることはないに等しい、ということと似ています。
しかし、大きく眺めれば、その波の形は似ています。
しかもそのカウンセリング手法がうまくすすむのか、どこかで混乱してストップしてしまうのか、についての実験結果はしっかり出せるのです。
LEAPカウンセリングの流れそのものが、実は「予想・仮説⇨実験・確かめ」そのものとなっているのですが、それはいずれ「入門講座」などで実技研修を受けていただけたらと思っています。
さて、タイトルの
「自分の行動は自分の選択。その行動の責任を受け入れることで成長する」
という話に進みたいと思います。
長い教師生活と、その半分ほどはカウンセラーとして、いろいろな問題や課題と向き合ってきましたが、「自分に起こった問題を、周りの誰かのせいにしてしまう」ことでこじれてしまう状況に数え切れないほど関わってきました。
も のごとにはたくさんの要素が絡みますから、その一部をとって、周りのどれそれのせいにする、ということは可能です。しかしそういう思考パターンを続けてい ると、「私は被害者で悪いのは全部周りの人・状況」という大きな迷路に入ってしまいます。そういう中で「自分はまったく悪くない」と主張してしまうことに もなるのです。
逆に「どういう状況があったにせよ、その行動を選択したのは自分自身だ」ということを基本にしておくと、解決のいろいろな手立てが見つかってきます。自分の行動を変えるのは、周りの状況や周りの人を変えるより何百万倍も簡単なのです。
私は時々、たのしい教育研究所に学びにくる先生たちに「天気まで自分のせいにする必要はないけれど、沖縄の子ども達の学力が低いのは自分のせいかもしれない、と考えてみることも大切だと思う」と話すことがあります。
目の前の自分のクラスの子ども達でなく、沖縄全体のことまで自分のせいなのか?
そう不思議に思う人たちも多いのでしょうけど、思考実験としては十分考えるに足るテーマだと思います。
自分の育てる子どもがたのしく賢くなる。そして、目の前の子ども達だけでなく、ひろくいろいろな子ども達をたのしく賢くできる。それはとてもたのしい活動となります。
沖縄県全体のことまで考えることはないにしても、せめて自分が選択した行動は全て自分の責任で選んだものだ、と考える。
そして「その選択した行動の結果おこったことは、全て自分で責任をとる」という形で暮らしていけたら、その人はきっと、どんどんたくましく成長していくことでしょう。
「だれだれが、そう言ったから自分はそれを選んだのだ」とか「こういう状態だから、しかたなかったのだ」とは言わず、そういう中で、その行動を選び取ったのは自分だ、ということです。
LEAPカウンセリングのはじめの段階では、そのところをとても丁寧に扱います。
自分の責任として受け入れる人は、いろいろなアイディアを出して、解決のための行動に進む事ができます。そうやって、人間としてたくましく賢く成長していくのです。そうすれば、次に起こる問題に対しても、冷静に行動ができる様になると思います。
少し長くなりました。
たのしい研究所は、いろいろな方達の悩みとも
真剣につきあっていきます。