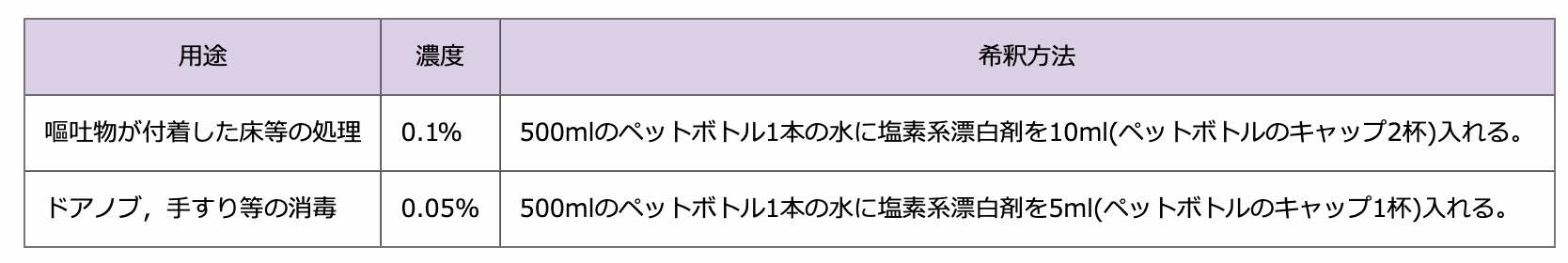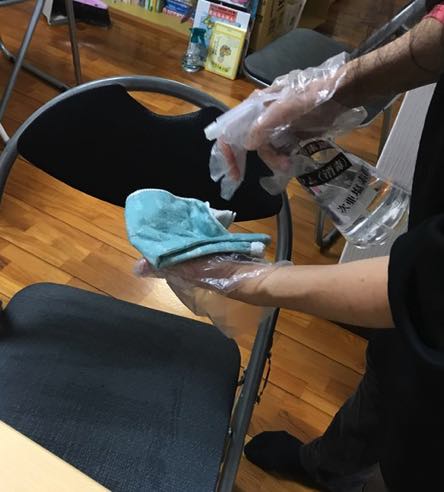準備期間ほぼ無しで休校に入った混乱はもともとあったコロナパニックを加速して、マスクがなくなり、外で咳払い一つしただけで睨まれるとう状況、花粉症で咳をした人が殴られたという話、加速してトイレットペーパー騒動という考えられない状況まで出ています。
新型コロナより恐ろしいのは間違いなく人間集団のヒステリー状態/集団パニックです。
新型コロナよりインフルエンザの危険度が上です、これまではあまり真剣に考えていなかったかもしれないインフルエンザ対策に力を入れていきましょう。新型コロナにも有効です。
さて、私が教師をしていた頃、〈あやしい実験俱楽部〉という団体を人気のあった授業を思い出しています。教育課程の中の週一の俱楽部でもっていた科学クラブの延長だったのですけど、それに入ることができなかった子どもたちもいっぱい入ってきて、放課後の理科室で賑わっていました。
スポーツなどの部活の担当の方たちから、子ども達の集まりが遅くなっているのでなんとかならないかという相談もあり、期間限定になりましたけど、子ども達はとてもたのしんでくれていました。
考えてみると、その後文科省等で〈放課後子ども教室〉が推進されて、それぞれの学校で空き教室を使って子ども達を集めていましたから、その魁だったわけです。
そこで取り上げた一つが〈分解〉です。
廃棄したパソコンがある教室に山積みになっていたので、それをもらって子ども達で分解していくのです。
メインで使う工具は〈メガネ用のミニドライバーセット〉です。普通サイズのドライバーが必要な時もあります。

MACのパソコンは特別な工具が必要ですけど、windowsはそうではありません。もしも特別な工具が必要な場合は、大人でその部分は壊すなどして外しておくとよいでしょう。マイナスドライバーとハンマーでなんとかなります。
何しろ、組み立て直す必要がないので安心してバラバラにすることができます。
大きいパソコンはこうやってネジを外していきます。

中ががらんどう状態で、子どもたちは大抵びっくりすると思います。熱を逃すためだという話ですけど、Macを使っている私からするとそれはおかしいと思います。iMacなどは、ほぼディスプレイなのかと思える本体に機器が詰まっていて、とてもスリムです。

ノートパソコンの方はぎっしり詰まっています。

一体、何をどうやって外せば良いのか、知恵の輪を解くような難しいたのしさです。ネジを外して、いろいろな向きに〈ゆっくり〉と力を加えていってください。ドライバーなどをテコにして動かしてみるのもよいですね。

まれに接着してあるパーツがあります。
頭脳の中枢CPUはそうなっている場合もあるでしょう。
でも外れます。
1日でほぼ分解してパーツをバラバラにする、というのは無理だと思います。つまり数日たのしめます。
分解の初めと途中、おわりで写真をとっていき、パーツを並べたり、数を数えたりして、自由研究として提出するのもいいですね。
毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所(RIDE)です。みなさんの応援クリックをお待ちしています➡︎この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援の1票」が入ります☆いいね☆➡︎もっと深くたのしい教育を味わいたい方は〈有料メルマガ〉をどうぞ!



 他にも魅力的な人物がたくさん出てきます。
他にも魅力的な人物がたくさん出てきます。