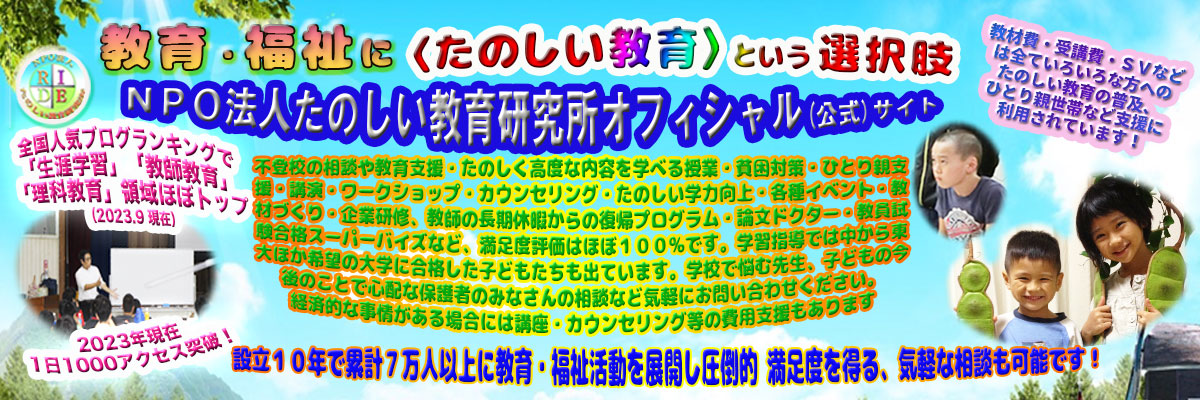もの心つくころから書棚にたくさんの本が並んでいたのは、とても幸いなことでした。親にとても感謝していることの一つです。本に対する親しみと同時に、自然にそれを手に取る様になっていったからです。
私は周りの友人たちと違って小学校一年生にあがるまで五十音を勉強していなかったのですけど、勉強をはじめると、身近にあるたくさんの本が読めることが嬉しくてどんどん言葉を学んでいったのを覚えています。小学校12年で江戸川乱歩の〈怪人二十面相〉シリーズを読み始めていたのですけど、おそらくみんな読み仮名がついていたのでしょう。わからないところは辞書を引いたり家族に聞いたりしていたに違いありません。それにしても、読書人生の始まりの頃に、あれだけドキドキする様な体験をしたことも幸いでした。ある先生の残念な指導でその後数年、本から遠ざかるのですけど、本そのものを嫌になったことはありません。人生全体として、本から得た感動は数えられないほどです。
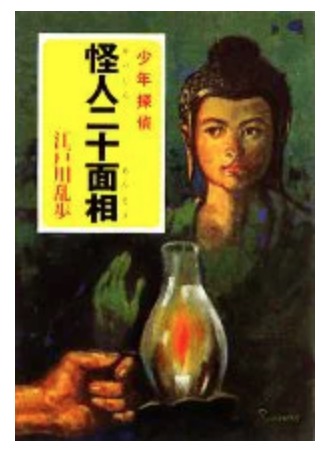
さて、私の読書生活の本格的なスタートの頃に出会って、その後の読書人生を大きく決定づけた江戸川乱歩の「怪人二十面相」は〈青空文庫〉で全文読むことができます。私もまた読み返しています。
変装の名人の怪人二十面相と探偵明智小五郎、その右腕の小林少年の活躍に没頭したあの日々が思い起こされます。
読書生活のスタートの頃の小説の中身を覚えているのか?
それも興味深いことです。
青空文庫という〈社会運動〉に敬意を評して、はじまりのところを少し紹介します。気に入ったらぜひ青空文庫を開いてみてください。男性でも女性でも、小学生でも大人でもたのしめると思います。
そのころ、東京中の町という町、家という家では、ふたり以上の人が顔をあわせさえすれば、まるでお天気のあいさつでもするように、怪人「二十面相」のうわさをしていました。
「二十面相」というのは、毎日毎日、新聞記事をにぎわしている、ふしぎな盗賊のあだ名です。その賊は二十のまったくちがった顔を持っているといわれていました。つまり、変装がとびきりじょうずなのです。
どんなに明るい場所で、どんなに近よってながめても、少しも変装とはわからない、まるでちがった人に見えるのだそうです。老人にも若者にも、富豪にも乞食にも、学者にも無頼漢にも、いや、女にさえも、まったくその人になりきってしまうことができるといいます。
では、その賊のほんとうの年はいくつで、どんな顔をしているのかというと、それは、だれひとり見たことがありません。二十種もの顔を持っているけれど、そのうちの、どれがほんとうの顔なのだか、だれも知らない。いや、賊自身でも、ほんとうの顔をわすれてしまっているのかもしれません。それほど、たえずちがった顔、ちがった姿で、人の前にあらわれるのです。
そういう変装の天才みたいな賊だものですから、警察でもこまってしまいました。いったい、どの顔を目あてに捜索したらいいのか、まるで見当がつかないからです。
ただ、せめてものしあわせは、この盗賊は、宝石だとか、美術品だとか、美しくてめずらしくて、ひじょうに高価な品物をぬすむばかりで、現金にはあまり興味を持たないようですし、それに、人を傷つけたり殺したりする、ざんこくなふるまいは、一度もしたことがありません。血がきらいなのです。
しかし、いくら血がきらいだからといって、悪いことをするやつのことですから、自分の身があぶないとなれば、それをのがれるためには、何をするかわかったものではありません。東京中の人が「二十面相」のうわさばかりしているというのも、じつは、こわくてしかたがないからです。
ことに、日本にいくつという貴重な品物を持っている富豪などは、ふるえあがってこわがっていました。今までのようすで見ますと、いくら警察へたのんでも、ふせぎようのない、おそろしい賊なのですから。
この「二十面相」には、一つのみょうなくせがありました。何かこれという貴重な品物をねらいますと、かならず前もって、いついく日にはそれをちょうだいに参上するという、予告状を送ることです。賊ながらも、不公平なたたかいはしたくないと心がけているのかもしれません。それともまた、いくら用心しても、ちゃんと取ってみせるぞ、おれの腕まえは、こんなものだと、ほこりたいのかもしれません。いずれにしても、大胆不敵、傍若無人の怪盗といわねばなりません。
このお話は、そういう出没自在、神変ふかしぎの怪賊と、日本一の名探偵明智小五郎との、力と力、知恵と知恵、火花をちらす、一騎うちの大闘争の物語です。
大探偵明智小五郎には、小林芳雄という少年助手があります。このかわいらしい小探偵の、リスのようにびんしょうな活動も、なかなかの見ものでありましょう。
さて、前おきはこのくらいにして、いよいよ物語にうつることにします。鉄のわな
麻布の、とあるやしき町に、百メートル四方もあるような大邸宅があります。
四メートルぐらいもありそうな、高い高いコンクリート塀が、ズーッと、目もはるかにつづいています。いかめしい鉄のとびらの門をはいると、大きなソテツが、ドッカリと植わっていて、そのしげった葉の向こうに、りっぱな玄関が見えています。
いく間ともしれぬ、広い日本建てと、黄色い化粧れんがをはりつめた、二階建ての大きな洋館とが、かぎの手にならんでいて、その裏には、公園のように、広くて美しいお庭があるのです。
これは、実業界の大立者、羽柴壮太郎氏の邸宅です。
羽柴家には、今、ひじょうな喜びと、ひじょうな恐怖とが、織りまざるようにして、おそいかかっていました。
喜びというのは、今から十年以前に家出をした、長男の壮一君が、南洋ボルネオ島から、おとうさんにおわびをするために、日本へ帰ってくることでした。
壮一君は生来の冒険児で、中学校を卒業すると、学友とふたりで、南洋の新天地に渡航し、何か壮快な事業をおこしたいと願ったのですが、父の壮太郎氏は、がんとしてそれをゆるさなかったので、とうとう、むだんで家をとびだし、小さな帆船に便乗して、南洋にわたったのでした。
それから十年間、壮一君からはまったくなんのたよりもなく、ゆくえさえわからなかったのですが、つい三ヵ月ほどまえ、とつぜん、ボルネオ島のサンダカンから手紙をよこして、やっと一人まえの男になったから、おとうさまにおわびに帰りたい、といってきたのです。
壮一君は現在では、サンダカン付近に大きなゴム植林をいとなんでいて、手紙には、そのゴム林の写真と、壮一君の最近の写真とが、同封してありました。もう三十歳です。鼻下にきどったひげをはやして、りっぱな大人になっていました。
おとうさまも、おかあさまも、妹の早苗さんも、まだ小学生の弟の壮二君も、大喜びでした。下関で船をおりて、飛行機で帰ってくるというので、その日が待ちどおしくてしかたがありません。
さて、いっぽう羽柴家をおそった、ひじょうな恐怖といいますのは、ほかならぬ「二十面相」のおそろしい予告状です。予告状の文面は、「余がいかなる人物であるかは、貴下も新聞紙上にてご承知であろう。
貴下は、かつてロマノフ王家の宝冠をかざりし大ダイヤモンド六個を、貴家の家宝として、珍蔵せられると確聞する。
余はこのたび、右六個のダイヤモンドを、貴下より無償にてゆずりうける決心をした。近日中にちょうだいに参上するつもりである。
正確な日時はおってご通知する。
ずいぶんご用心なさるがよかろう。」というので、おわりに「二十面相」と署名してありました。
そのダイヤモンドというのは、ロシアの帝政没落ののち、ある白系ロシア人が、旧ロマノフ家の宝冠を手に入れて、かざりの宝石だけをとりはずし、それを、中国商人に売りわたしたのが、まわりまわって、日本の羽柴氏に買いとられたもので、価にして二百万円という、貴重な宝物でした。
その六個の宝石は、げんに、壮太郎氏の書斎の金庫の中におさまっているのですが、怪盗はそのありかまで、ちゃんと知りぬいているような文面です。
その予告状をうけとると、主人の壮太郎氏は、さすがに顔色もかえませんでしたが、夫人をはじめ、お嬢さんも、召使いなどまでが、ふるえあがってしまいました。
ことに羽柴家の支配人近藤老人は、主家の一大事とばかりに、さわぎたてて、警察へ出頭して、保護をねがうやら、あたらしく、猛犬を買いいれるやら、あらゆる手段をめぐらして、賊の襲来にそなえました。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!