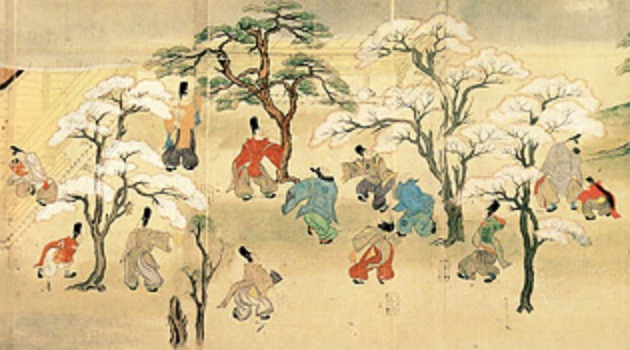ほとんどの人はやっていないと思うのですけど、私の毎朝のルーティーンの一つが「人生で残された日数の確認」です、スマホのアプリをセットしておくと、毎朝「あなたに残された日は◯◯日◯◯時間◯◯分◯◯秒です」と通知してくれます。
以前利用していた〈余命電卓〉というアプリは、それに加えて「あと何回食事できて、あと何回満月をみることができて・・・」という様に具体的に知らせてくれたので、さらに気に入りだったのですけど、今のアプリはシンプルです。
「そんな恐ろしい数字は見たくない考えたくもない」という人も多いのですけど、残された日々は間違いなく今ここにあって、それは掛け替えのない大切な日々であることも間違いないのです。
さて、最近メルマガの四つの賞の一つ〈映画の賞〉で書いた手塚悟監督「Every Day」がとても好評です。映画はまさに冒頭の(残された日々〉がテーマです。
でもご心配なく、暗く深刻な作品ではありません。監督の才能と俳優陣の力量と制作過程のすばらしさが相乗して、奇跡的な軽やさで、まるで音楽の様にストーリーが流れていきます。

私はすでに10回以上見ています。最近、ラストの受け取り方が二つに分けられることを(強引に)発見しました。
本筋ではないエピソードも味わい深いものがあります。
不思議な、そして実は私が鍵を握っている人物だとにらんでいる〈吉田さん〉の「おむすびとおにぎりの違い」の話。
主人公三井の友人、菊池のパートナー〈きなこ〉のセリフ
「わかってる? 見えるのと見るのは違うのよ!」
インディーズ中のインディーズ、つまり大手資本のつかない自主制作で作り上げた珠玉の名作だと言ってよいでしょう。みなさんもこれを見て、人生について考えてみませんか。こども達と接する時にも少なからず違いがでてくると思います。
五年くらい前の作品なので安い費用でDVDレンタルできると思います、アマゾンプライムでも視聴できまする。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!