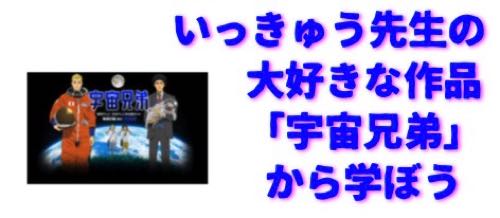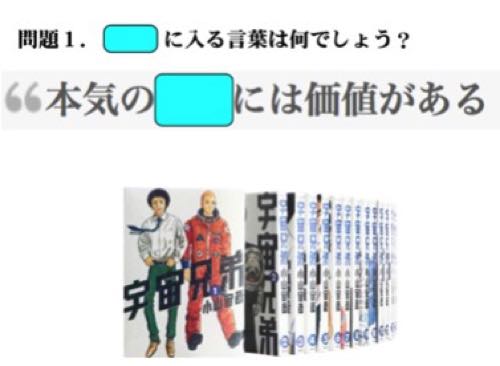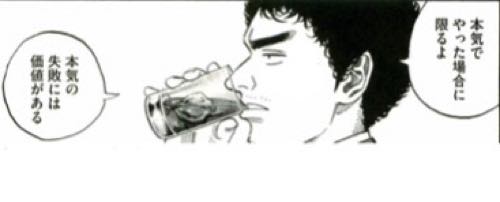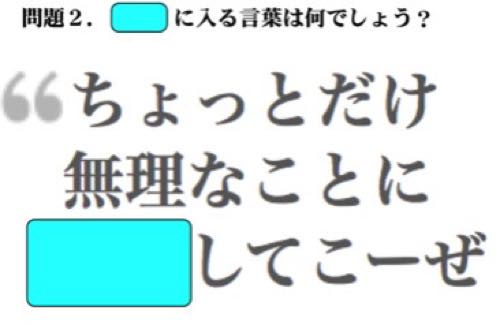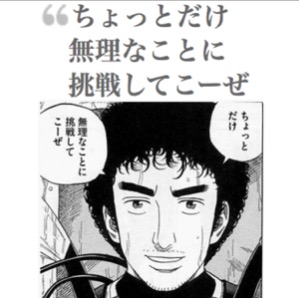何年か前、ふらりと入った本屋さんで手にした本がありました、「本を守ろうとする猫の話」夏川草介 小学館(2017)です。猫も好きで本も好きなのでは自然に手にしたのでしょう、確か飛行機の中で読み終えたと思います。
中身は〈読書道徳〉物語というようなものです。不思議なネーミングですけど、それがあっていると思うな。邪(よこしま)な読書をたしなめ、読書の良さを伝える物語です。
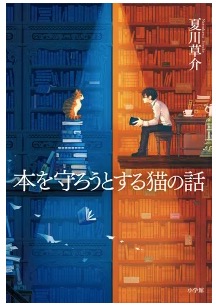
読みやすい文章で、著者はテレビで大ヒットしたらしい「神様のカルテ」も書いています、私は読んでいませんけど。
最近ある人と話したことがあるのですけど、私が活字中毒になりはじめた頃、たくさんの本を読みたくて自然に読むスピードが早くなっていきました。
けれどしだいにその速さがイヤになって、強引な方法で速度を落としたことがありました。実際に時計で測ってたいたので、今の読むスピードもほぼはっきりわかります、〈一時間で100ページ〉くらいです。それは結果的にとても便利で、手にした本を今から読むと、だいたい何時くらいに読み終えるか予想できます。
どうやって速度を落としたかというと、本を読む時、蛍光ペンを持って全ての文章にラインしながら読むという面倒な方法です。
その時は早く読むことが感覚的に〈イヤ〉だったのですけど、もう少し詳しくいうと「風を感じる気持ちよい散歩のように、本をじっくり味わいながら読めなくなった」と感じるようになっていったからです。
実はその時の私の感覚を、この本「本を守ろうとする猫の話」の主人公、高校生の〈夏木林太郎〉がとてもみごとに表現してくれています。
第二章〈切り刻むもの〉の中にベートーベンの第九を聴きながら速読でたくさんの本を読んでいる人物が登場します。
林太郎はその人物のBGM機器に手を伸ばして〈第九〉を三倍速にしてしまいます。それを聴いた速読にかける人物は反射的に「何をする、第九が台無しじゃないか」と叫びます。
ベートーベンの〈第九〉を三倍速にして聴いて、それで第九を聴いたことになるのですか?
みごとです。
古本もたくさん出ている様です、この冬、読みたくなった方は手に取ってみてください。
② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります