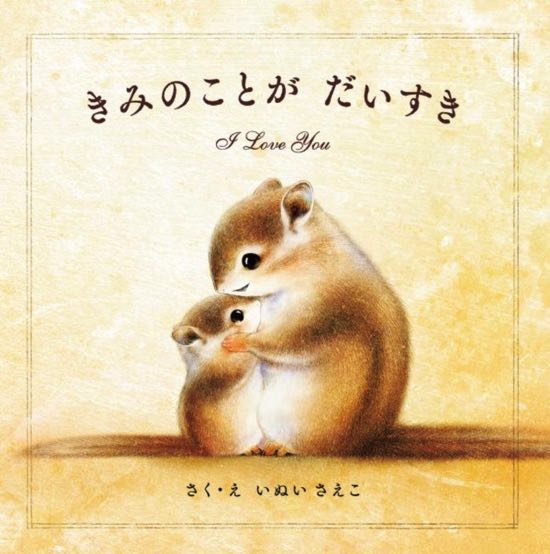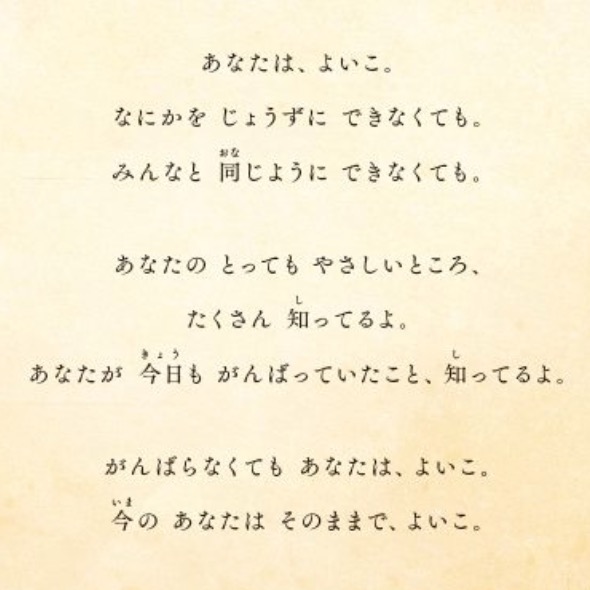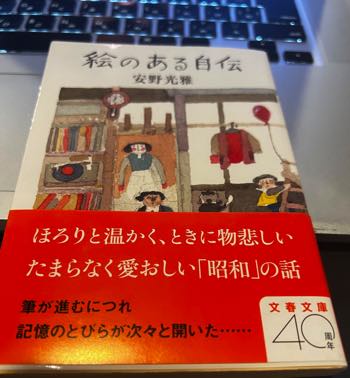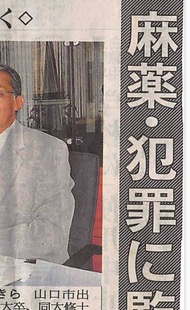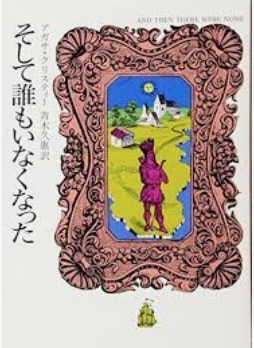今週の〈たのしい教育メールマガジン〉の発想法の章で紹介する内容をいろいろにつくろっています。先週はアドラー心理学の師匠〈野田俊作〉先生が著書で語った内容を紹介しました。

野田
ときどき私の家へ宗教の勧誘が来ます。
「神様に関心はありますか?」と。
その人たちの顔を見るとたいてい不幸そうな顔をしている。
・・・
という言葉から始まる内容です。大阪人の野田先生は特有のノリがある刺激的な表現も多用するのですけど、その根幹はシンプルです。
野田先生の言葉にリンクさせて、もう一人の師〈板倉聖宣〉先生の「願うことで真実には至らない」という話にしようかと考えはじめています。
板倉先生は東京の下町出身で、語り口は野田先生とかなり違うのですけど、同じ様に言葉の根幹にあるものはシンプルです。
それを私たちが納得できるように丁寧に言葉を重ねてくれます。
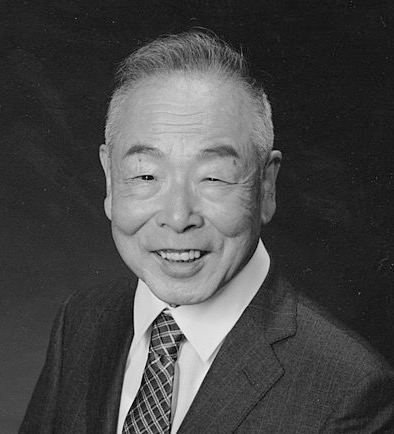
始まりのところを少し紹介しましょう。
板倉
〈科学の大衆化〉というのは、それを望む人がやると科学の大衆化 ができるとは限らない。
「大衆化を望めば大衆化する」というのであれば非常に簡単な話です。
「人間性豊かな人間になろう」、そう望んで教育すればそうなるということなら簡単なことです。
自然科学は「そうではない」ということを教えている。
このサイトでは始まりの部分を少し紹介しただけなので、野田先生の言葉と板倉先生の言葉がリンクする様には思えないかもしれません。
祈りや願い、救いという部分で両者が結びついていきます。
願いや祈りが叶ったり、平和になったり、自分が犯した罪を許してもらえるというのが宗教だとすると、たくさんの人たちが宗教を信じているロシアやウクライナで最も悲惨な戦争が続いているのはどうしてだろう。
宗教と科学が対立するのではなく、〈宗教が人々の心をおちつけ、科学的に確かめられたものに従って淡々とすすめていくプロセスとして二つが結びついていく〉としたらどんなによいだろう。
そういうことを考えています。
① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!
② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります