〈たの研〉の活動を応援してくださっている方たちがいます、夏のある日、その方からドラゴン・フルーツが届きました。

火の竜のくだもの〈火竜果〉という別名もある、爽やかな甘みの美味しいくだもので、サボテンの仲間です。

そういえば以前、畑の道を歩いた時に撮った写真がありました。
花は終わった後で、ドラゴン・フルーツの雄しべ(おしべ)と雌しべ(めしべ)がありました。この髪の毛に見えるものが雄しべで、その中央に雌しべがあります。

これはしだいに実が大きくなってきたところです、これが赤く熟して食べごろになります。

これが切った状態・・・、ドラゴン・フルーツには白やピンクもあるのですけど、赤は強烈な色です。※赤ムラサキと呼ぶ人もいます

この色素は強くて、口紅や染料としても使われることがあるというのですから、すごいですよね。
これくらい強い赤を出す食べ物は〈赤のビーツ(サトウダイコン)〉くらいしかないんじゃないかなぁ。
これはビーツのサラダ・・・

これがビーツです。

自由研究(ものづくり系)のテーマで
⭕️ドラゴン・フルーツで染めもの
https://kodo-rika.hatenablog.com/entry/2014/12/07/065139
というのもたのしいと思います。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

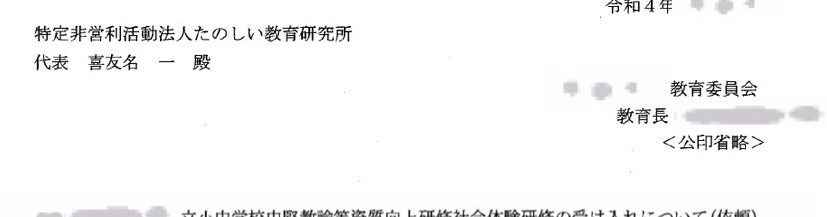


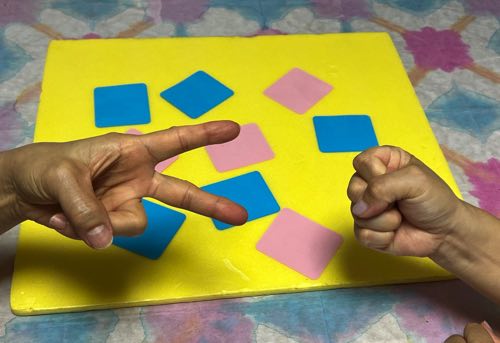 「つまらない」という評価はこれまで皆無です、A先生も「とてもたのしいです」と喜んでくれています。
「つまらない」という評価はこれまで皆無です、A先生も「とてもたのしいです」と喜んでくれています。








