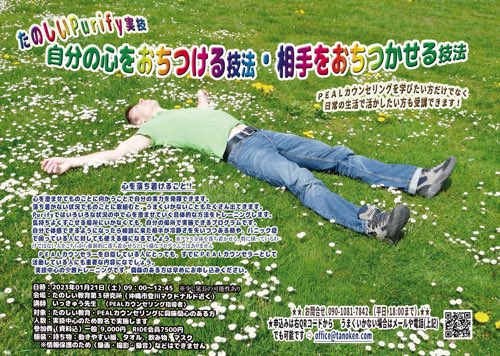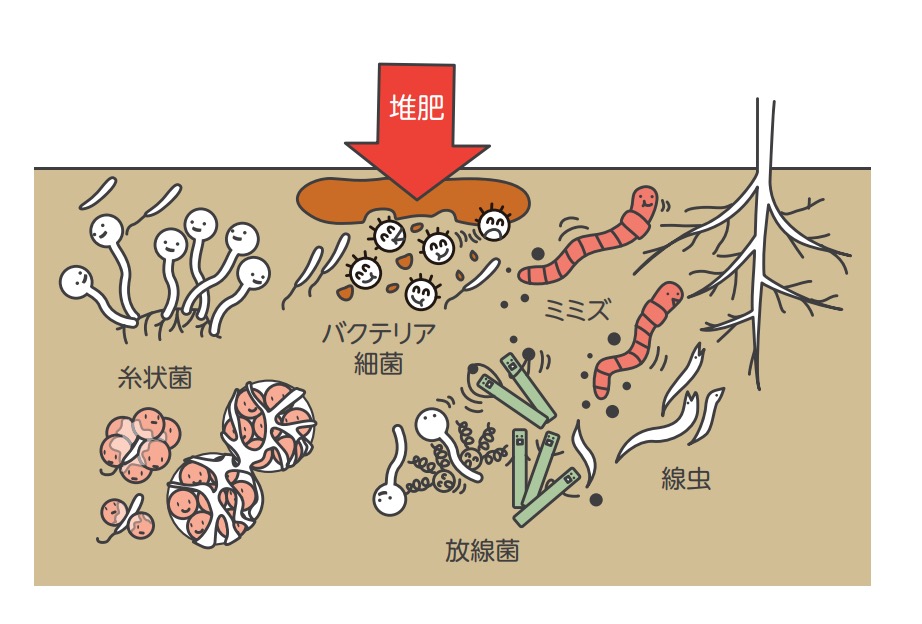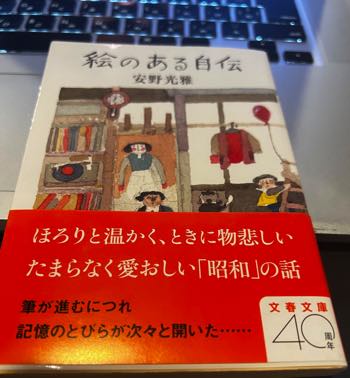年が明けて〈たの研〉の活動も活発になってきました。
すでにお伝えした様にカウンセリング系の〈Purify2〉を1月に開催し、2月は恒例の〈出会いも別れもたのしい教育〉を開催します。
別れの春に子ども達と思い出に残る授業をする、出会いの春も子ども達が「先生に受け持ってもらえてよかった」と感じてくれる、そういう授業ができたら、別れの時も出会いの時もいい思い出に彩られます。それは子どもたちと先生の関係だけでなく、保護者との関係もよくなるきっかけになるでしょう。
※Purify2は予定人数に達しました
近々、事務局から案内が届き次第、こちらにも広報させていただきます。
さてこれは、日頃からたのしい教育を実践してきた先生たちが集まって、こういう授業はどうだろう、こういうものづくりはどうだろうというアイディアを寄せ合っているアイディアミーティングの様子です。

これはその中で私いっきゅうが構想している授業書のスタートのところをみんなにみてもらっているところです。

一人ひとり測定したり、外に出てのワークも含むので一時間の流れとしてまとめられるのか、少し流れを整理してから決めることになるのですけど、いずれにしてもこれまで子ども達がたのしんでくれた内容はたくさんあります。
〈たの研〉が実施する授業は「こども達が笑顔になって〈もっとこういう授業をしたい〉」と感じてくれるという実験結果がハッキリしているものばかりです。
参加希望の方は、期日を空けていていただけると嬉しいです。
※
教師がたりない、不登校のこども達が増える、いわゆる問題行動と呼ばれるものも増えている、クラスでじっとできずに特別支援のクラスに行くことになる子ども達も増えているetc.
そういう問題は、沖縄なら沖縄の子ども達の「達成度得点」が上がっていけば解決するのでしょうか?
たとえば〈達成度得点が全国一位〉になったらそういった問題は解決するのでしょうか?
そうではないことはたくさんの人たちが気づいているでしょう。
それでも教育界全体がなかなか変われないのはどうしてなのか?
そういう原因論的なものを云々するより、本質的な解決である(子ども達が笑顔になって自ら勉強にのめり込んでいく様な教育〉の普及をはかる、それができる力ある先生たちを増やしていく、それがたのしい教育研究所の考え方です。
達成度得点が上がって、全国トップレベルになると、県外の有名大学に入る子ども達も増えていくでしょう。そういう人材が一定数出てきて中央官庁にも沖縄県出身者が入っていく、それは政治的にも経済的にもメリットがあることかもしれません。
では〈たのしい教育〉をすすめていくとどうなるのか?
たくさんの子ども達の目が輝き、可能性が伸びていく。
今まで学校を休んでいた子どもたちも「どうも学校にいくとたのしい勉強を教えてもらえそうだ。家にこもってゲームするのもいいけど勉強もたのしそうだ」という様にして、不登校のこども達の数も次第に減っていくでしょう。
そうやって広く全体としての教育を押し上げる突破口になるのが〈たのしい教育〉です。
そうやって子ども達の興味関心を高めるのはよいけれど、有名大学に入る子どもたちが減っていいのか? という人もいるかもしれません。
いいえ、たのしい教育で子ども達の学力は確実に伸びていきます。
以前、〈たの研〉で学んだ子ども達のほとんどが東大ほか、県外の大学に進学していった話を書きました。そういう様にして、知的な楽しさや可能性を求めて有名大学に入る子ども達も増えていくでしょう。すると今より中央官庁・省庁に進む人たちも増えるでしょう。
たのしい教育をしたいと考えていても、それだけではたのしい教育はできません。講座などで、具体的に体感して、その方法を学ぶことが近道です。
〈たの研〉の講座は、はじめての人たちが明日にでも真似て授業できる様にプログラムしています。
ぜひご参加ください。
新年なので少し大風呂敷を広げた話をしてみました。
賛同してくれるみなさんが増えていくことで、〈たのしい教育〉で自分たちの周りのこども達の笑顔と賢さを高めてくれる先生たちが増えていくことは間違いありません。
地道な取り組みですけど「このサイトいいよ、読んでね」と周りの人たちに広めてくれることを期待しています。
可能な方はメルマガを購読し、それを自分たちの周りで実践してください、自分の力で笑顔と賢さを増やしていく取り組みになります。
② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります