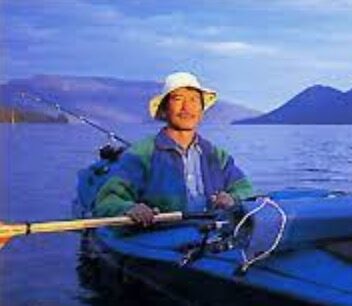車を走らせているとスクスク気持ちよく空に伸びるサトウキビの穂をみつけて写真を撮りました、凛々(りり)しい姿です。

子どもの頃からなぜか私はサトウキビの穂と江戸時代の火消しの〈まとい〉を結びつけて思い出してしまいます、同じ様なひともいるのでしょうか?

サトウキビは砂糖の原料になるのでより甘く、より丈夫な、より大きなものを育てる様になってきました、普通のサトウキビは人間よりずっと大きく成長します。

生き物に興味をもったら、その植物の〈名前〉を調べることで、より親しみがわきます。
その次に〈何のグループなのか〉をみていくことをおすすめします。
グループの分類はいろいろな分け方が存在するのですけど、まず〈◯◯科〉というものをみていくとよいでしょう。
さてさて、サトウキビは何のグループ、何科の植物でしょう?
グループの名前が思いつかなくても「あ、あの植物と同じじゃないかなぁ~」という様に頭に浮かんでくるものはありませんか・・・、少し考えてみてください。
予想を立てたら、外れてももちろん賢くなりますよ。
あなたの予想。

茎をみてみましょう、何かに似ていませんか?
 私は〈竹〉に似ている様に見えます。
私は〈竹〉に似ている様に見えます。
とすると竹の仲間なのでしょうか?
そうです竹の仲間です。
でもグループの名前は〈竹科〉ではありません。
竹もサトウキビも、ある植物の名前のグループになっています。
それは私たちの暮らしに古くから身近な植物だったので、その植物の名前がグループの名前になったのでしょう。
これです。

田んぼで栽培されているイネ、日本人の主食〈コメ〉が実ります。
サトウキビや竹とあまりにも大きさが違います。
「似ているかなぁ」と思う人もいるでしょう。
第一、竹やサトウキビには目立つ〈節〉があるのに、イネにはないのじゃないか。
・・・
どうでしょう。
あるんですよ、イネにも〈節〉が。
これはイネの穂のスケッチです、〈第 I 節間〉〈第 Ⅱ 節間〉とありますね、節と節の間ということです。

これはイネの茎をタテに割った写真です。
しっかり〈節〉で区切られています。

大きさや見た目からあまり似てない様に思えても、身体のつくりの基本的な部分は似ているというのがグループです。
みなさんも、植物や動物をみつけたら「これは何のグループかな」という様に考えをすすめていくと、いろいろな発見があると思います。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!



 「菜の花」というのはアブラナ科の植物の花の総称です。アブラナ科のキャベツもハクサイもそのままにして置くと菜の花が咲きます。
「菜の花」というのはアブラナ科の植物の花の総称です。アブラナ科のキャベツもハクサイもそのままにして置くと菜の花が咲きます。