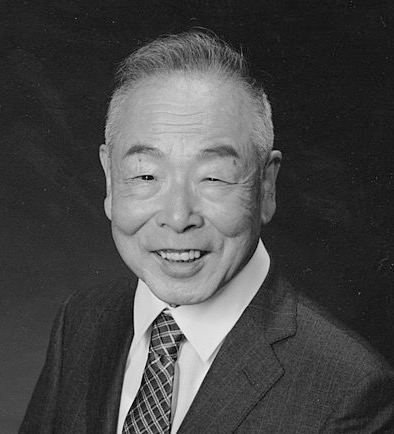発想法について読みたいです、というリクエストが届きました。自由研究をテーマにすることが多かったので、今回は〈たのしい教育メールマガジン〉の発想法の章でとりあげた板倉聖宣(仮説実験授業研究会初代代表)先生の歴史の見方から少し紹介しましょう。歴史の見方考え方についての話です、その考え方は普通の暮らしの何気ない変化の中でも役立つものだと思います。

出典は仮説実験授業の大会で入手した資料からで、1994.6大阪たのしい授業塾で語った内容の一部です。
文責 喜友名一(いっきゅう)
板倉
世の中というのは不思議なものです。いま関西国際空港が問題になっていて、それがもうすぐできます。ある時期までは「空港ができればいいなぁ」という夢がある。それがある時期になると、「空港ができると公害が起こってマイナスばかりだ」という話になって「関西国際空港できるのには反対だ」とか「反対することが良識なんだ」と思ったりする。
でも出来てしまったら「便利だな、乗ろうか」とか「東京へ行くのなら新幹線で行くより飛行機の方安くていいよ」という話になって、それまで反対していた人たちが便利さを謳歌したりする、なかなか複雑です。
江戸時代の人たちは自分の物は自分の家で作っていたんです。綿花を自分のところで栽培している農家は自分のところでとれるからいいのですが、栽培していない農家の人たちは綿花を買わなくてはいけません。
実際には、ほとんど現金収入がありませんから変えません。
どうするかというと、行商人が来て
「綿花を買いませんか」
「お金がないから買えないよ」
「じゃあ2着分置いていくので2着分糸を紡いでください。今度来たときにその1着分を私にくだされば1着分を差し上げます」
となる。
つまり1着分を紡いだ労力で1着分の綿花を買うわけです、そしてこれを織る。そうやって現金収入がなくてもいいようになっていたわけです。
これも悪いように見る人は「木綿資本が農村にまで手をのばして人民を支配した」というようなことを言える。
けれどそうではない見方もできる。
〈時代の進歩〉というものは全部〈呪う〉ことに決めていたり、逆に〈歓迎する〉ことに決めていたりする人がいます。
しかし早い頃に〈社会の科学〉を学んだ人は両面のことをちゃんと考えていたと思います。
そういう流れの中で、たとえば「いろいろな機械が発明されることはとてもいいことなんだ。しかしそれがしばしば社会に不平等や不幸を生み出す。だから不幸を生み出さないように科学や技術の進歩に手心を加え、社会的規制を加えるのも必要だ」という考え方だったりするんです。
いっきゅう
立場による一方的な見方ではなく、両方あるいは三方からの見方をしてみる。そして、より多くの人たちの笑顔につながるところにすすんでいく、それが歴史の発展だと思います。
ピンポインで見れば〈悪〉であっても巨視的にみると〈善〉であることはたくさんあります、またその逆も。
この板倉先生の話で小川未明の〈とうげの茶屋〉という物語を思い出しました。
付録としてつけておきます。
ちょうど夏休み期間です、自分の休みではなくても教材研究などの時間は多くなったと思います。ぜひ、読んでみてください。
青空文庫に感謝して引用させていただきます
とうげの茶屋
小川未明https://www.aozora.gr.jp/cards/001475/files/51624_63351.html
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!