以前からずっと心にあった
「電子書籍」の作成に、やっと歩をすすめています。
デザインなど、まだまだですけど、0から1になった大いなる一歩です。
出版まではまだ知恵と工夫を重ねる必要がありますけど、遠からず試作版を出してみる予定です。
特別のツールは必要なく、スマホやタブレット端末、もちろんパソコンなどで、インターネットを閲覧する感覚で簡単に読めるものを作成する予定です。
立ち読みなども出来るように設定します。
ご期待ください。
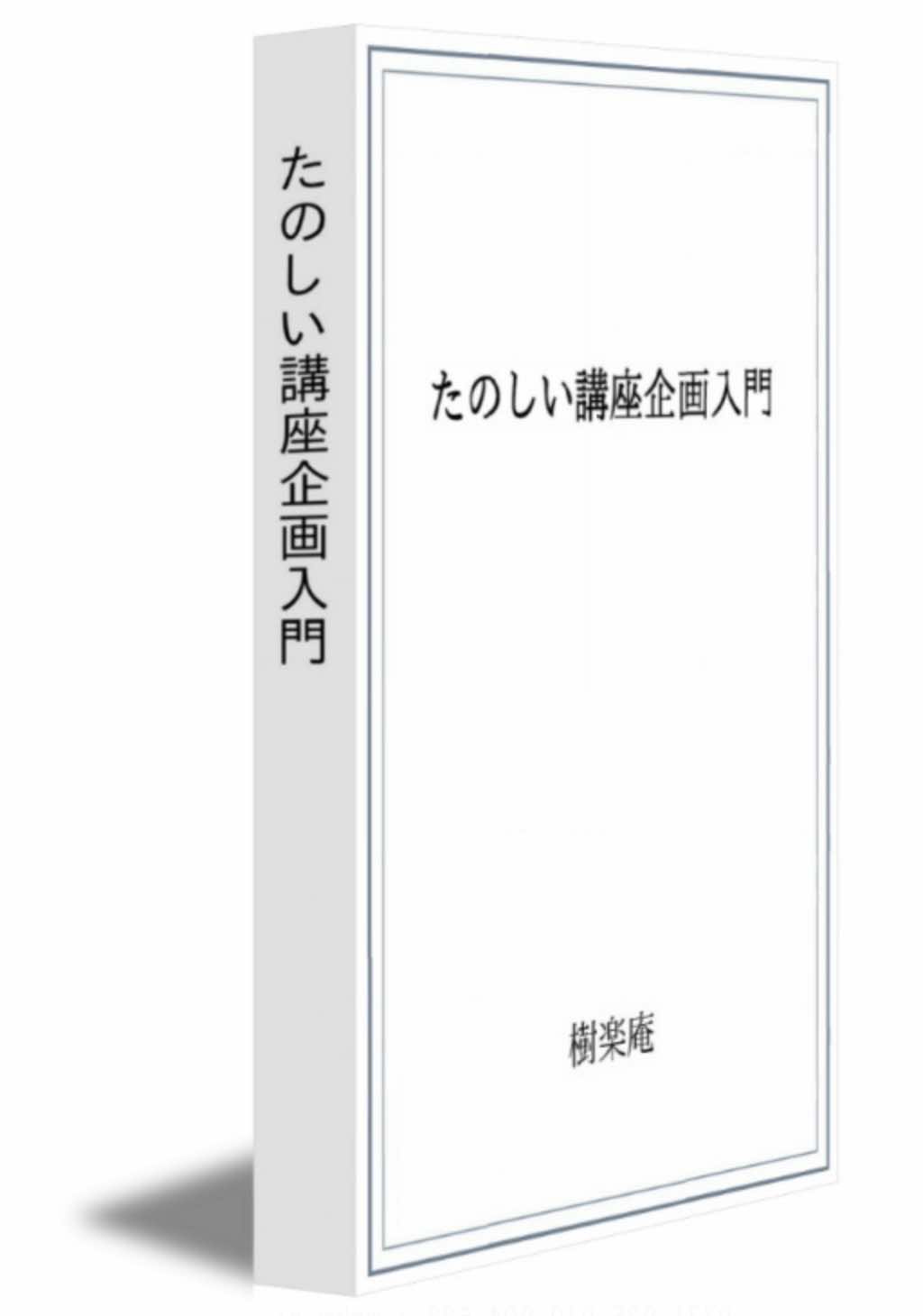
たのしくかしこく=「たのかし」プロジェクト進行中!
着実にひろがるたのしい教育です。

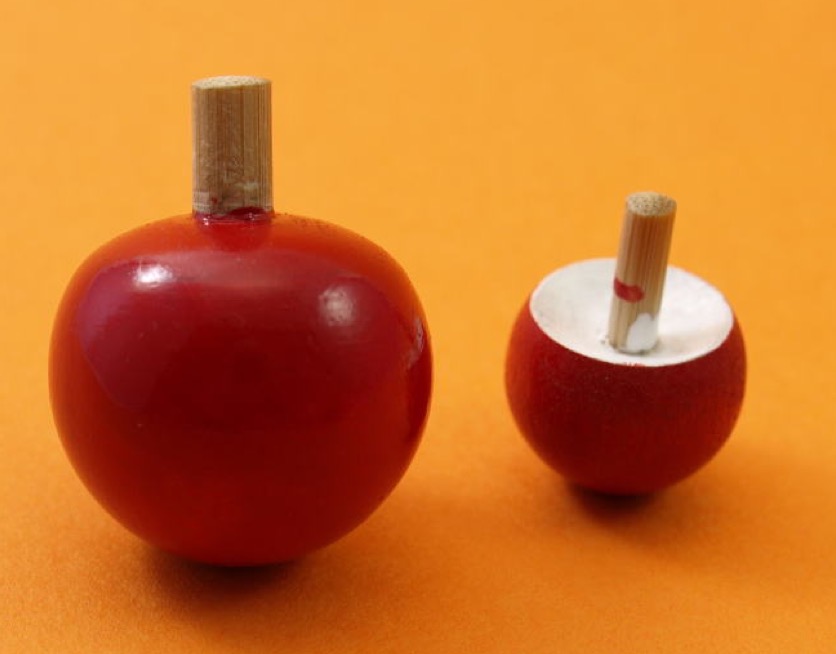 できると思いますか?
できると思いますか?


 考えてみると、扇風機も電気の力で回しているコマの様なものですね。
考えてみると、扇風機も電気の力で回しているコマの様なものですね。




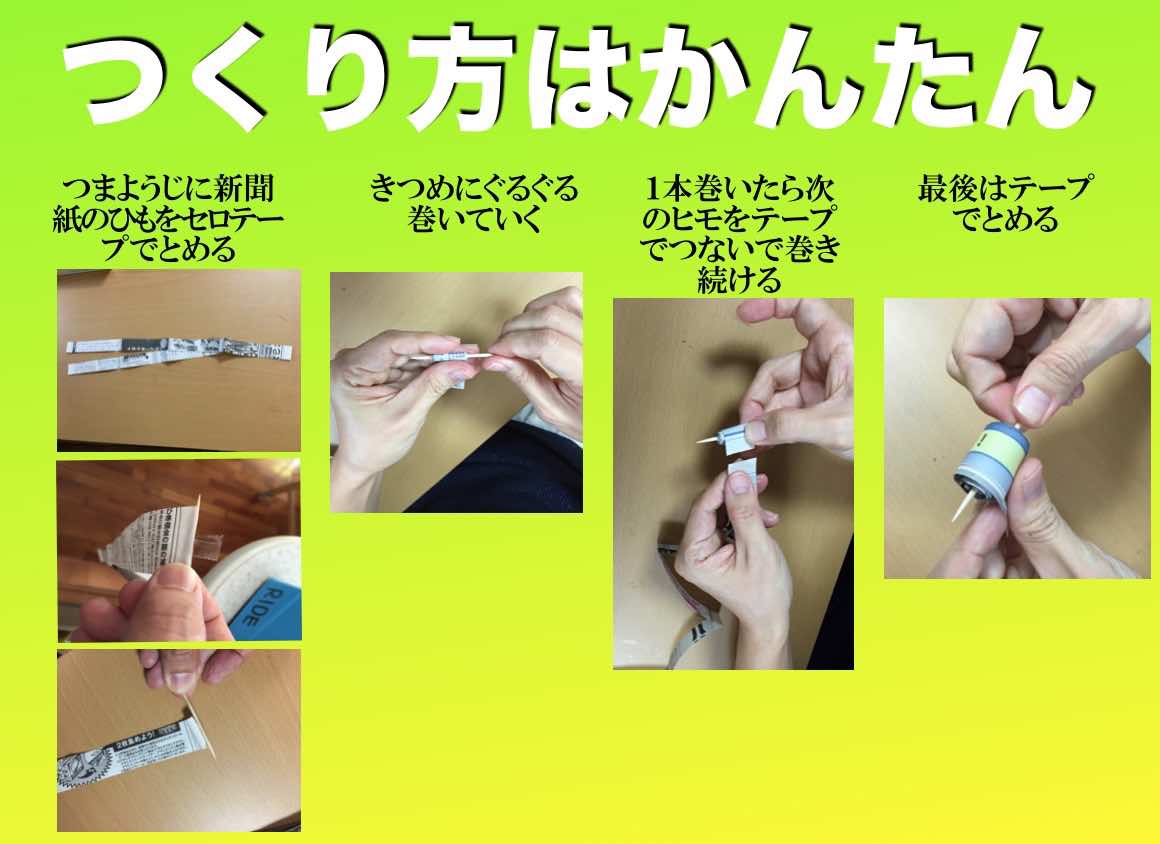 たのしんでいただけたら、その時の写真をぜひ一〜二枚送ってください。
たのしんでいただけたら、その時の写真をぜひ一〜二枚送ってください。