たのしい教育研究所を応援してくれている方たちはとてもたくさんいて、このサイトを毎日読んでくださっている方たちも、その一人です、感謝しています。農業をしているHさんは野菜で〈たの研〉メンバーを応援してくれています。
今年は寒さが長引く年だと知っていたらしく、冬野菜も例年より長く収穫が続いているというので、またたっぷり持ってきてくれました。
私が子どもの頃、時どき、野菜を持ってきて売りにきてくれるおばあちゃんがいたのですけど、Hさんは、土から採りたての野菜を入り口外で広げて説明してくれるので、子どもの頃の懐かしい様子を思い出します。下の写真に写った野菜以外にも袋に入ったたくさんの野菜が運ばれてきました。

これはHさんが新しく育てた〈球ちゃんタマネギ〉です、柔らかくて美味しそうです。

今回一番驚いたのがサツマイモです。熊本原産(左)のものと沖縄の読谷村原産のもの2種類を持ってきてくれたのですけど、なんと鉢で育てたそうです。

今年退職するという学校管理職の先生から聞いた話によると、学校では〈学級園〉や理科・生活科の〈教材園〉がなくなってきているとのこと、 地植えでなくこんなりっぱなサツマイモができるなら、学校でも子どもたちと試せると思います。
「もしかすると2Lのペットボトルでできるかも」と思い立ち、さっそく〈たの研〉でも実験してみることにしました。
興味のある方は、自分で、プランターなどを利用して栽培してみませんか。結果も教えてもらえると嬉しいです。
Hさんの農業は「たのしさ優先」、たのしい教育研究所の基本方針とぴったり一致しています。
説明会の後は、中に入っていっぱい笑いながらいろいろなお話をしました。元気の出る日々です。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!






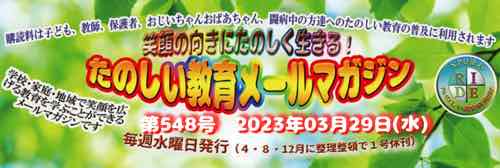

 このカヤツリグサの別名を、〈たの研〉のスタッフAさんから教えてもらいました、Aさんはお花の先生から教えてもらったそうです。
このカヤツリグサの別名を、〈たの研〉のスタッフAさんから教えてもらいました、Aさんはお花の先生から教えてもらったそうです。
 これは別に破れた傘には見えないなぁ・・・
これは別に破れた傘には見えないなぁ・・・ シュロガヤツリと甲乙付けがたいですね。
シュロガヤツリと甲乙付けがたいですね。