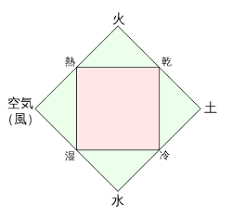昆虫を見にと近くの公園に行った時、サクランボがたくさん実りはじめていることに驚きました、こんなに早いんだ。

二週間くらい前はまだ花がいっぱい咲いていたのに・・・

赤く色づきはじめた実もあります。

サクランボの中にはタネがあります、いろいろなところに運んでくれることを期待して鳥などに食べてもらう作戦で子孫を広げていきます。
ところが沖縄の寒緋桜は人間が食べても渋くて美味しくありません。
早期退職して〈たの研〉を設立する前、学校でこども達とジャム作りに挑戦したのですけど、子どもたちも私も「これは美味しくないね」という意見で一致して、一回でチャレンジはおわりました。
最近、たの研のナノ先生が言うには「前にいた用務の方がさくらぼジャムをつくっておいしく食べることができるって言ってましたよ」とのこと。
いろいろ調べてみると赤々としている時より黒くなってきたころが甘いとのこと、渋みの成分なども調べてみました。
サクランボの中の渋みの成分は、主にタンニンと呼ばれるポリフェノールの一種です。
タンニンは、植物の細胞壁や果実などに含まれる成分で、渋みや苦味の原因となります。
サクランボに含まれるタンニンは、カテキン型のものが主になります。
カテキン型タンニンは、ポリフェノールの中でも特に高い抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素を抑制する効果があります。また、タンニンは、消化器系の働きを促進する効果もあります。
ただし、サクランボに含まれるタンニンは、食べ過ぎると胃腸に負担をかけることがあるため、適量を守って食べることが大切です。
また、渋みを減らすために、熟したサクランボを選んだり、凍らせたりする方法もあります。
ChatGPT
なにぃ、凍らせると渋みが減るのか・・・
10数年ぶりくらいに挑戦してみようかな。
うまくいったら、学校でも子ども達と挑戦する先生たちが出てくると思います。
読者の皆さんの中で寒緋桜のサクランボでジャムを作ったことがある方がいたら教えてください!
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか。たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただけませんか!