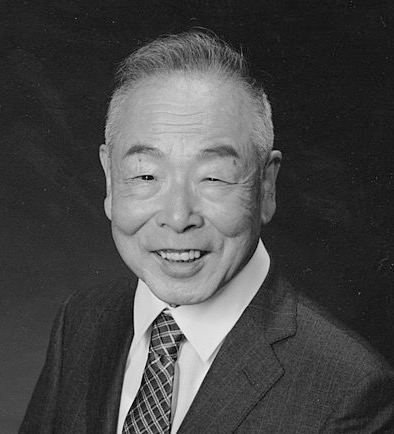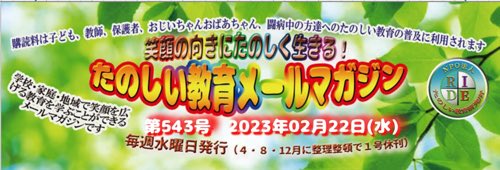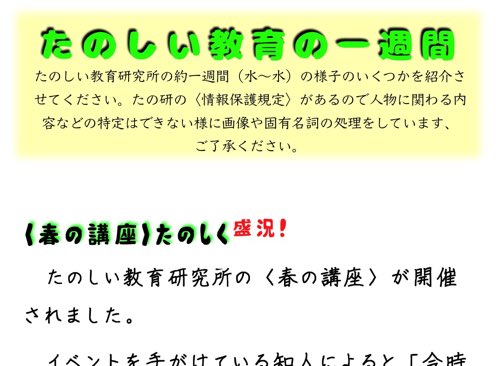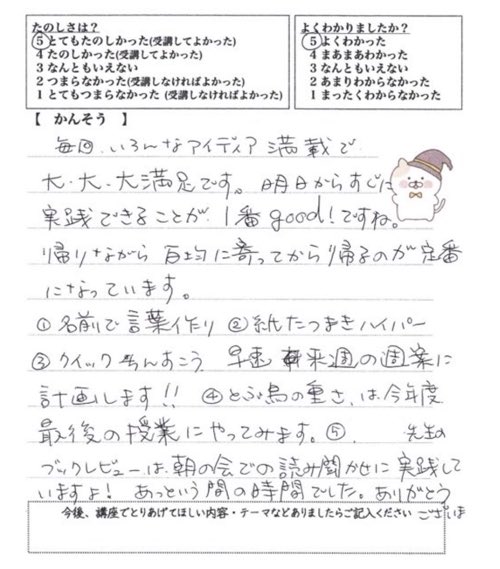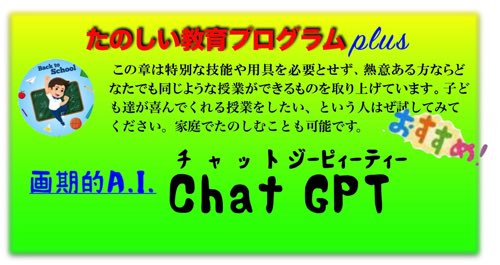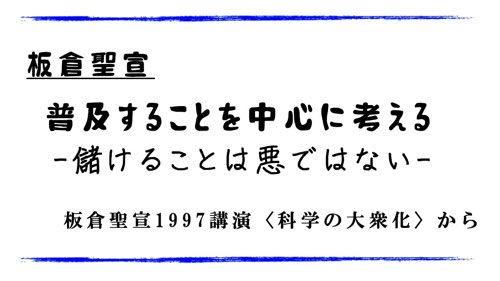楽しい教育をたのしんでくれているK先生から笑顔の写真が届きました。こども達と〈スッ飛びストロー〉を作った時の様子です。みんなとてもいい笑顔です。

スッ飛びストローは〈スーパーボール〉と〈竹串〉と〈ストロー〉で作るたのしい教材で、このまま指を離して落下させると、ストローがビュンと高くとんでいきます。講座の売り場でも早めになくなっていく人気教材の一つです。

バランスよく落とすと、自分の頭の上を超えていくこともあって、シンプルでワクワクどきどきしながら楽しむことができます。
作るのは5分くらいで済むので、たのしむ時間をたっぷり取ることができます。
たのしく完成品1個、作成パーツ10個セット、30個セットなど、いろいろ揃えています、興味のある方はおといあわせください。
大量作成しているわけではないので、在庫が切れたらしばらく待っていただくことになります、ご了承ください。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!