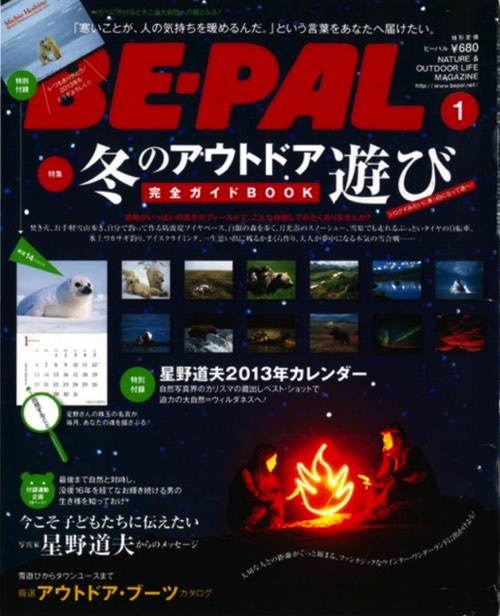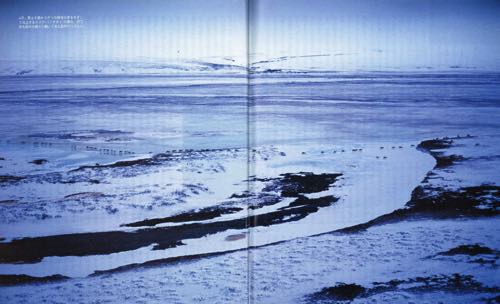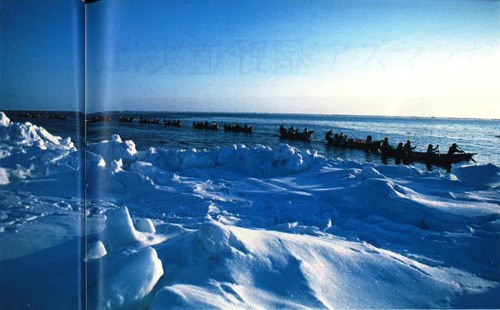沖縄市のたのしい教育研究所は高速インター近くにあるので、いろいろな方たちが足を運びやすい位置にあります。
そしていろいろな教育相談やスーパーバイズの要請などが届きます。
最近写真を整理していると懐かしいものがいろいろ見つかりました。
これは一番街の活性化イベントに呼ばれて、スタッフがものづくりをしているところです。
ひっきりなしに参加者が訪れて、準備した100人分くらいの材料がなくなり「もっと持ってきてほしい」という電話があったのを覚えています。

これは沖縄市の生涯学習フェスタに呼ばれてものづくりをしているときの一コマです。
たくさんの人たちが一気に訪れて、その人だかりに「何かおもしろいことをしているらしい」と、さらにたくさんの人たちがきてくれました。
スタッフがフル稼働だった1日でした。

たのしい教育は街の活性化にも大きく力を発揮することができるという実験結果でもあります。
コロナがおちついて、またこういうイベントができるとよいなと思っているところです。
たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!