夏休み、たの研のメンバーのA先生の元にある先生から「親子で折染めを体験したいです!」というお話が来て一緒にたのしんだそうです。
その時の写真が届きました、画像処理したものからも〈笑顔〉が伝わるのではないでしょうか。

テーブルの上には清々しい作品が並んでいます。

折染めを体験した人たちはわかると思うのですけど、想像を超えた作品がどんどん出てくるので、おもしろくて次々に作品を作っていったのでしょう。

頭の中にあるデザイン、たとえば〈服のデザイン〉や〈家の設計〉などを形にすることも素晴らしいことです。
そういうデザインと違って、折染めは偶然性が大きく作用します。
選んだ色、その重なり、そして染み込ませる時の量、色の濃さ、折り方、つまむ時の指の力 etc.
A.I.でも計算できない多様な条件が生み出す世界です。


折染めワークショップも開催可能です。
また原液で利用できる染料もセットで提供しています。
興味のある方は気軽にお問い合わせください。
① たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!
② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

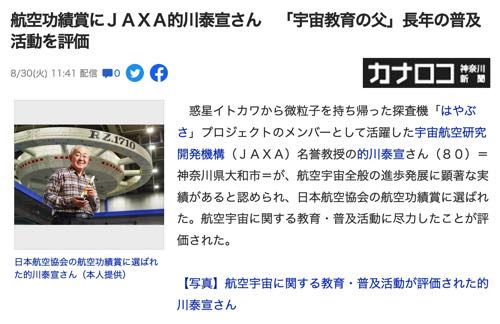

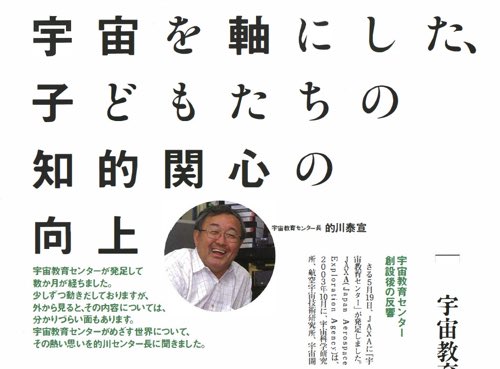








 沖縄ではサンダンカと呼ばれ、植物図鑑では〈サンタンカ〉とあります。
沖縄ではサンダンカと呼ばれ、植物図鑑では〈サンタンカ〉とあります。
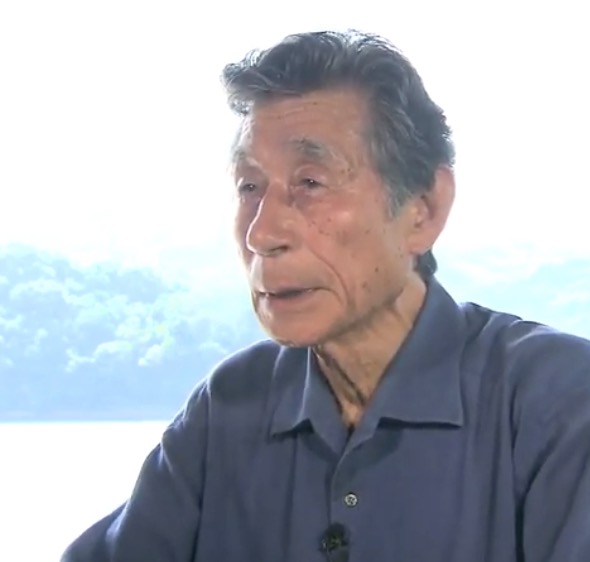
 池田武邦さんのことを知ったのは〈たの研〉がとても忙しい時期でした。
池田武邦さんのことを知ったのは〈たの研〉がとても忙しい時期でした。