前回、かるく池田武邦さんの紹介をしてからこの内容に入ろうと思っていたのですけど、どっしりと触れてしまいました。
自然に感動できる心は大切です、レイチェル・カーソンの〈センス・オブ・ワンダー〉の世界は私たちのすぐ近くで扉を開いてくれています。
最近歩いた時の植物たちの様子を紹介させてください、広いフィールド草木の間にポツリと咲いている花たちは、花屋さんの様に密集してたくさんの彩りをみせているわけではないのですけど、私にとって大きな花屋さんにいるようです。
※
傘をさしてフィールドを歩いた時の一枚です。ビニールハウスのそばに花開いた美しい花がありました、蘭の様な彩りで、目を引きます。
お店の花屋さんのたくさんの花の中に置かれていたら、みとれることもなかったと思います。フィールドの広がる空間の中でこその素晴らしさの一つです。

調べてみると、いろいろな呼び名がある様です。
和名では〈ルリハナガサモドキ〉、ところが私は個人的に〈~モドキ〉という名称が嫌いです、その生物に失礼だと思っています。
学名で覚えようと思ったら、〈もどき〉を意味する〈pseudo/スードー〉とつくので困っています。気に入りの呼び名が見つかるまで覚えるのはひかえておこうかな。
※
これも同じ日に見つけた鮮やかな紅の花、〈ベニツツバナ〉です。


※
夏の盛りから終わりにかけてよくみる〈サルスベリ〉の花も満開です。

やわらかないろあいで好きな花の一つです。

※
沖縄では野生の〈ランタナ〉の花をたくさんみることができます。
元気に咲いていました、イシガケチョウが蜜を集めています。

お店の花屋さんではこういうシーンは見ることができませんね。

※
サンダンカ・サンタンカも見つかりました。
これも鮮やかな紅色を見せています。
 沖縄ではサンダンカと呼ばれ、植物図鑑では〈サンタンカ〉とあります。
沖縄ではサンダンカと呼ばれ、植物図鑑では〈サンタンカ〉とあります。
気になって調べてみると、こうありました。
沖縄には古い和語が残っているという話を時々しているのですけど、その足跡の一つですね。
サンタンカが日本にやってきたのは江戸時代中期で、当初は三段花(さんだんか)と呼ばれていました。大陸から琉球経由での渡来と言われます。ちなみに沖縄では露地でふつうに見られる花木で、オオゴチョウ、デイゴと並び沖縄三大名花のひとつに数えられています。
植物の育て方図鑑
※
なんとビックリ、八月後半なのに梅雨時5月後半~6月の花〈イジュ〉の花が咲いていました。時々、こういう姿にも巡り会えます、これもまたフィールドこその出逢いです。

長くなりました。
まだまだ見てほしい写真がたくさんあるので、機会をあらためて紹介させてください。
環境問題を真剣に考えていろいろな知恵を出し、たくさんの生物が共存する社会を作っていくことも、こういう体験がベースにある人たちが増えていくことで実現するのだと思います。
それがたのしい学力・たのしい学習で生きた力になるのでしょう。そういうことを自由に研究していく人たちを増やしていきたいと考えています。
ぜひみなさんも近くにあるセンスオブワンダーの宝庫へ足を運んでみてください。
① たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!
② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

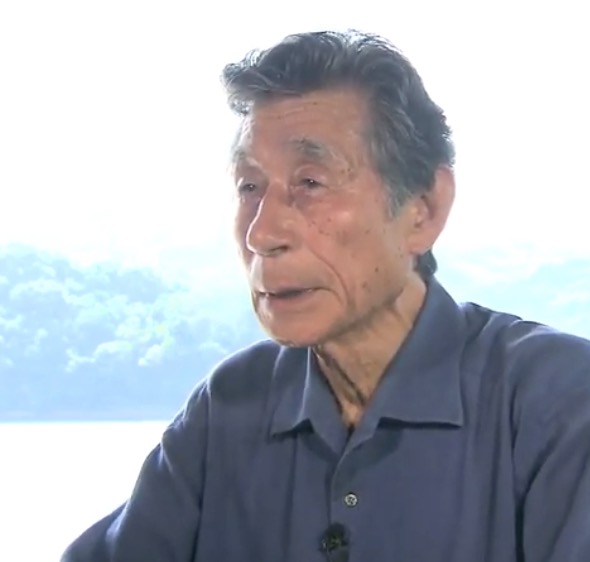
 池田武邦さんのことを知ったのは〈たの研〉がとても忙しい時期でした。
池田武邦さんのことを知ったのは〈たの研〉がとても忙しい時期でした。







