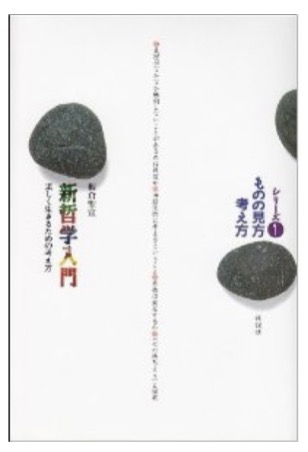〈たの研〉の設立当初から強く応援してくださった師の板倉聖宣(元文科省教育研究所室長/元日本科学史学会会長仮説/実験授業研究会初代代表)から学んだことはいくつもあります。
初期の〈たのしい教育メールマガジン〉で書いたものです。
「理想を掲げて妥協する」ということ 板倉聖宣
新哲学入門 p180から
私が私なりに築いてきた人生論的な教訓の一つに
「理想を掲げて妥協する」
という言葉があります。
「理想のためにガムシャラに頑張る」という考え方とは違った生き方を示す言葉です。
私は小さいときから
「理想というのは妥協を許さないものだ」
と教えられてきたような気がします。
「理想というのは、いつでも貫き通さずにはいられないものだ。そうしなければ理想の意味がない」と教わったような気がします。そこで、私も少しはそのように頑張ろうとしたことがあります。
しかし、そういう生き方をしようとすると、すごくくたびれるのです。たとえば、「科学的な生き方をする」というのが私の理想の一つでした。
そこで、私は「非科学的なものとは非妥協的に闘わなければならない」と思いました。私はなんでも徹底的にやらないと気がすまないところもあるので、反科学的な迷信はもちろん、非科学的な宗教も認めたくありませんでした。
しかし、人々が迷信に左右されているのをいちいちチェックしていたら大変です。それに、宗教的行事の一つひとつに反発していたら、これまた大変です。
それでも私は「自分の思想に忠実に生きたい」と思い、自ら「無神論者」と称して、そういう問題をあまり気にしていない大人たちに反発を感じたものでした。
でも私のように、徹底的に生きていこうとしたら大変なのは明らかです。
そこで、多くの大人たちは、社会のしきたりに大幅に妥協して生きていくことを余儀なくされたことは明らかです。私も、自分が大人になるにつれて、そのことを理解しないわけにはいきませんでした。そこで私は「自分の思想は思想として、他人の考えも認め、多くの人々と妥協して生きていくことが大切だ」ということを認めるようになりました。
こういうと「そんなのは誰もがやっていることで、ことさら新しい考えでもなんでもない」といわれそうです。
たしかにそうです。
しかし、私はこれまで理想と妥協をセットにして考えて生きるといったものに出会ったことがありません。
そこで私は、若い人々に対して「理想を掲げて妥協する」という生き方の重要性について語るようにしました。
すると、かなり多くの人々から喜ばれたので、改めて「これまで多くの人々が私と同じように、理想と現実との間にはさまって、どう考えたらいいか戸惑っていたのだなあ」と思い知ったものでした。「理想を掲げて妥協する」というのは、そんな言葉は知らなくとも、実際に多くの人々がやっていることです。
しかし「はっきりとそのことを自覚して行動するのと、自覚しないで行動するのとでは、まったく違うところがある」ようです。
たとえば、私は
「大きな数は234,567などと三桁区切りで書くよりも、23,4567などと四桁区切りにしたほうが読みやすくていい」
「昭和とか平成などという元号は、年代がわかりにくいから西暦で書いたほうがわかりやすい」
と思います。
そこで「できることならみんなに四桁区切り、西暦表示にしてほしい」と思っています。
これも、私のちょっとした〈理想〉のひとつなのです。
しかし、いくら私がそう思ったところで、世の中の人々はなかなか西暦表示や四桁区切りにしてくれません。仕方なしに、現実と妥協しているのですが、
「妥協をしつつも理想を守る」
「理想を実現できるチャンスがあったらどしどし実行する」
という気持ちで生きていると、けっこう四桁区切り、西暦表示を実行することができます。たとえば、私自身が「編集代表」となっている『たのしい授業』(仮説社)という教育雑誌では、数表示は四桁区切りを通し、西暦表示にしています。自分たちで決めて差し支えのないことは、自分の理想通りに実現できるからです。
世の中には、私と同じように「数字は四桁区切り、西暦表示が便利だ」という意見の持ち主は少なくありません。ところが、それなのに、部分的にも四桁表示、西暦表示がなかなか広がらないのは不思議なことです。
元号法制定のときにはそれに反対した歴史学者でさえ、自分の著書の奥付を元号表示にしていることが少なくありませんが、これはどうしたことでしょう。
法律がどうであるにせよ、自分の著書ぐらい元号を使わないで西暦表示する自由はあるはずなのです。
多くの人々は「自分の理想がそのまま現実化しない」ことを知って、理想を忘れてしまったように思われてなりません。私だって公務員ですから、「元号法」の手前、公式文書だけは元号で書かないと法律違反に問われることもあるわけですが、自分たちの編集・発行している雑誌などは公式文書ではないのですから、そこまで妥協する必要がないわけです。
「理想を掲げて妥協する」というのは、「妥協せざるを得ない事情が支配するところでは妥協する」ということであって、「理想を捨てる、忘れる」ということではありません。自分の理想にばかりこだわっていると摩擦が大きくなりすぎるときは妥協し、「妥協しなくてすむような条件下では、日頃の自分の考え、理想をどしどし実現する」ということなのです。
多くの人々はそういう考え方ができないように思われてなりません。
「理想を掲げて妥協する」
みなさんの生き方にも関わってくるものかもしれません。
もっと読みたい方はこちらから⇨https://amzn.to/3FX8Axh
① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています
⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!