たのしい教育研究所〈春の講座〉「出会も別れもたのしい教育」が開催されました、毎回人気の講座の一つです。
参加者の満足度評価(楽しさ度・理解度評価)も100%でした。
今回の流れは〈ほぼ完成形〉だろうなと思えるほど、スムーズな展開で、以後の講座のモデルになっていくと思います。

今回は那覇地区のK先生が新しく講師に加わり、クイックちんすこうを担当してくれました、流れもスムーズで、おいしさもバッチリ。

毎回新しい目玉のコーナーが登場するのですけど、この春の講座で「おたのしみ広場」を新しく設置したところ、大盛況。
これはその一つ〈くるくるコーナー〉で、皿回しをたのしんでくれている様子です。

難し目の皿回し用具なのですけど、子どもたちも回していました。

この子は一年生、一生懸命練習していた大人たちもびっくりしています。
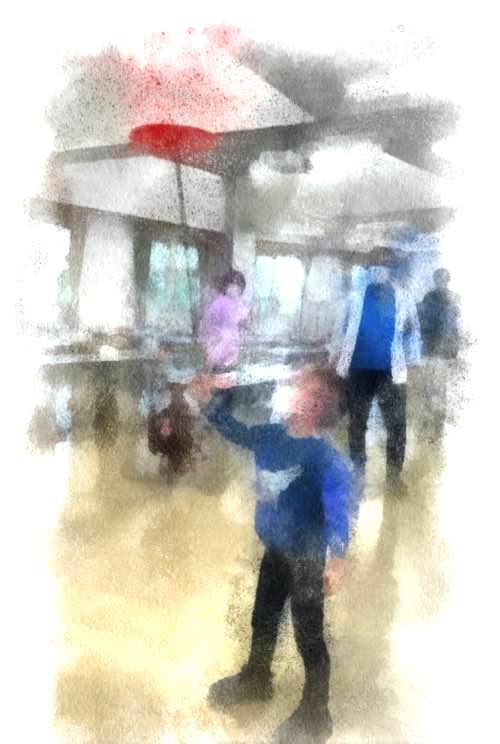
いくつかリサーチしてきたのですけど、コロナの影響なのか、今の頃は〈学び系〉の講座は、無料でも人数を集めるのは大変なのだと聞いています。〈たの研〉の講座はそれなりに費用がかかるのですけど、うれしいことにこうやってたくさんの方たちが集まってくれます。
講師スタッフの皆さん、たくさんの笑顔を広げてくれてありがとうございました。
また一緒に楽しみましょう。
② たのしい教育をより深く応援するために〈SNSや口コミ〉等でこのサイトを宣伝していただければ幸いです
③ たのしい教育を本格的に学ぶために〈たのしい教育メールマガジン〉を購読しませんか、有料コンテンツです。たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章など充実した内容です。講座・教材等の割引もあります

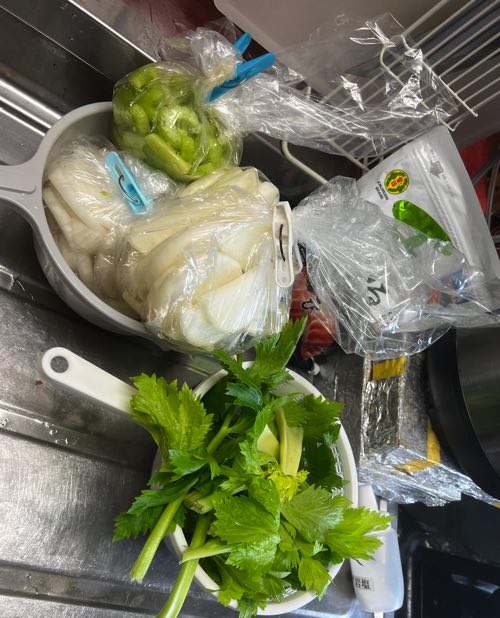




 しばらく置いていてもぜんぜん漬物っぽくならず、苦味が増す感じで食べるのは困難でした。以前、薄めの醤油で煮たゴーヤーの漬物を食べたことがあるのだけど、そこまでしないといけないのかな?
しばらく置いていてもぜんぜん漬物っぽくならず、苦味が増す感じで食べるのは困難でした。以前、薄めの醤油で煮たゴーヤーの漬物を食べたことがあるのだけど、そこまでしないといけないのかな?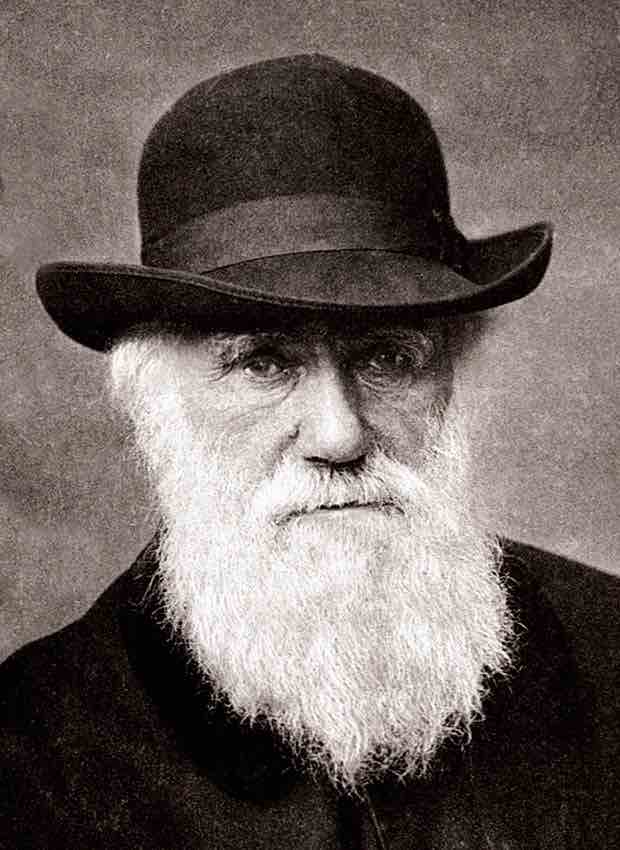




 そうか日本食品標準成分表2015ならアスパラガスのアスパラギン酸が〈430mg〉って書いてある、これなら普通のモヤシでも勝ってますね。
そうか日本食品標準成分表2015ならアスパラガスのアスパラギン酸が〈430mg〉って書いてある、これなら普通のモヤシでも勝ってますね。