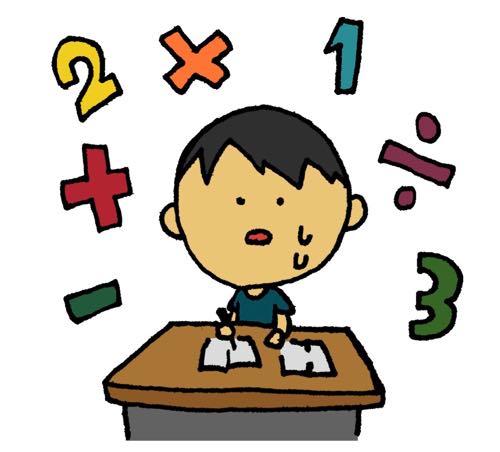メルマガに気軽に綴った文章についての反応が届くことがあります、メルマガの定番項『ア~ルとたのしい教育の日々』の書き出し部分に、さっそくメールが届いています。
〈たの研〉のメンバーはほとんどホモサピエンス、ヒト属ヒト科です。
唯一ア~ルがネコ科ネコ族から仲間に入ってくれています。
メルマガ第549号はじめの章から
私たちはホモ・サピエンスです、ヒト属の中で唯一生き残っている種族です。

wikipediaに感謝して引用
ネコ族はとてもたくさんの種が生息しています、そしてとても美しい。

wikipediaに感謝して引用
私たち人間はついつい、他の生物とは違う様に考えてしまうところがあります。けれどダーウィンが進化論でアイディアを出し、その後、分子生物学が次々に明らかにし続けている様に、生物進化の過程でそれぞれが今の姿になってきました。
メールにあったのは「同じ生物同士という目でみることができました」という内容でした。
いろいろな条件が重なり、私たち人間は大脳が発達したので、いろいろなことを自分たちで考えることができる様になりました。ユヴァル・ノア・ハラリも明らかにしている様に、その過程で「神という物語・フィクション」も作り出しました。
これから前に進んでいく中で、一度、同じ生物の仲間たちという見方・考え方も、大切なものだと思います。
私が何気なく綴った一言も、こういう気持ちが奥の方にあるからなのでしょう。
① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック
② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)
③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!